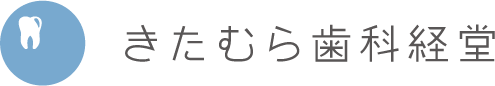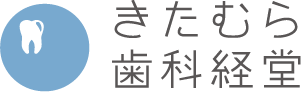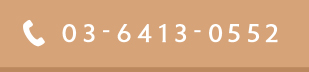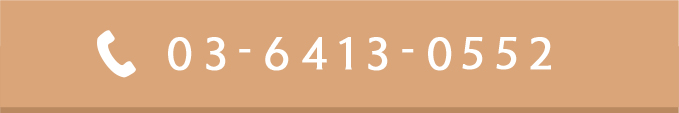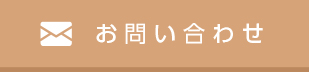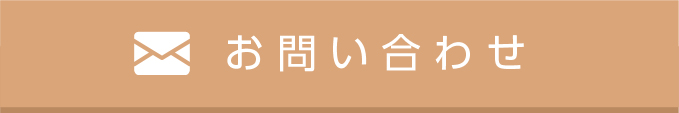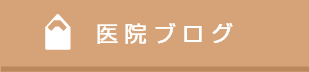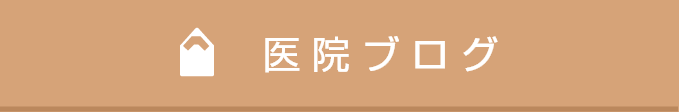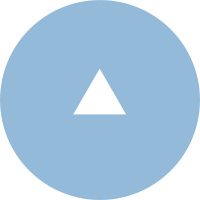2025.06.24更新
噛み合わせの治療にはいくらかかる?治療法ごとの費用を解説
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

「噛み合わせが悪い」と感じていても、具体的にどんな治療が必要なのか、また費用がどのくらいかかるのかが分からず、不安に思う方も多いでしょう。噛み合わせの悪さは、顎や肩の痛み、頭痛、食事のしづらさといったさまざまな不調の原因になることがあります。
症状の程度や原因によって治療法は異なり、治療法によって費用も大きく変わります。
この記事では、噛み合わせ治療の主な方法と、それぞれの費用の目安について分かりやすく解説します。
噛み合わせを治療する方法とそれぞれの費用

噛み合わせの乱れは、虫歯や歯周病だけでなく、顎関節症や肩こり、頭痛などの全身症状にも関係するといわれています。こうしたトラブルを未然に防ぐためには、原因に合わせた適切な治療が欠かせません。
ここでは、主に行われている噛み合わせ治療の方法と、それぞれにかかる費用の目安について解説します。
スプリント治療
スプリント治療は、透明なマウスピースのような装置を就寝時に装着することで、顎の位置を安定させたり、歯ぎしりや食いしばりによる負担を軽減したりする方法です。軽度の噛み合わせのズレに用いられることが多く、体への負担も少ない点が特徴です。
費用は保険適用であれば約5,000円前後、自費診療では3万円から5万円程度が相場とされています。顎関節症の治療を目的とする場合は、保険が適用されるケースがあります。
矯正治療
歯並びの乱れや顎の骨格に起因する噛み合わせの問題には、矯正治療が選択されます。ワイヤーを使った一般的な矯正のほか、近年では透明なマウスピース矯正も普及しています。歯列全体を整えることで、自然な噛み合わせへと導きます。
費用は自費診療となるため高額になりやすく、全体矯正であれば70万円〜120万円程度、部分的な矯正でも20万円〜40万円程度が目安です。マウスピース型矯正は装置の枚数や治療期間に応じて変動しますが、一般的には80万円前後になることが多いです。
補綴治療(被せ物・詰め物による調整)
噛み合わせの不具合が、詰め物や被せ物の高さや形状によるものであれば、補綴治療によって調整することが可能です。過去の治療で作られた人工物が原因となっている場合、その部分を作り直すことで改善が期待できます。
費用は使用する素材によって大きく異なり、保険適用の銀歯であれば数千円程度、自費のセラミックなどを選択すると1本あたり5万円〜15万円程度になることもあります。審美性や耐久性を重視する場合は、自費治療を選ぶ方が多いです。
咬合調整
歯の表面をわずかに削り、高さの微調整を行うことで噛み合わせを整える方法が咬合調整です。特に、治療した歯が他の歯よりも高くなっている場合などに有効とされています。施術は短時間の場合が多く、即効性があるのも特長です。
費用については、保険適用で数百円〜数千円程度、自費診療の場合は5,000円〜1万円程度が一般的です。
ただし、繰り返し調整が必要になるケースもあります。歯科医師の指示に従って継続的に受診することが大切です。
インプラント治療を併用する
歯を失ったことで噛み合わせのバランスが崩れている場合には、インプラントを用いた治療が選ばれるケースもあります。人工歯根を顎の骨に埋め込み、上部構造を装着することで、自然な噛み合わせを回復します。
インプラント治療は自費診療となり、1本あたり30万円〜50万円程度が一般的です。また、補綴物の素材や骨造成の有無によっては、さらに費用がかかる場合があります。
噛み合わせの治療に保険は適用される?

噛み合わせの治療は、目的や治療内容によって保険が適用されるかどうかが異なります。たとえば、スプリント治療や咬合調整など、顎関節症や痛みの改善を目的とした治療であれば、医師の診断のもとで保険が適用されることがあります。
一方で、見た目を整えるための矯正治療は、原則として自費診療になります。重度の噛み合わせ異常や先天的な顎の変形と診断された場合には、厚生労働省が定める施設での治療に限り、保険が適用されるケースもあります。
適用条件は厳密に決められているため、事前に歯科医師とよく相談することが大切です。
噛み合わせの治療にかかった費用は医療費控除の対象?
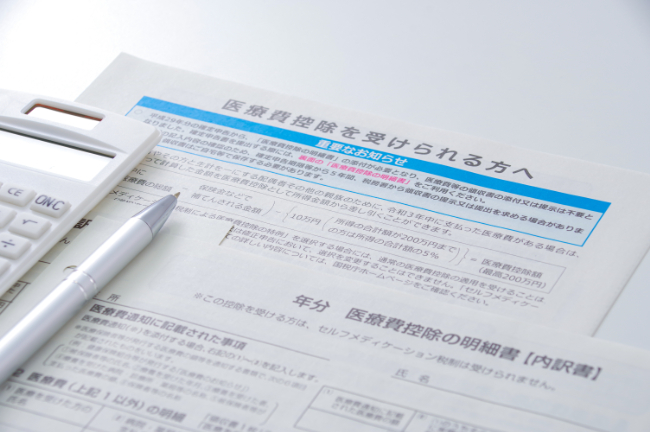
噛み合わせの治療費が医療費控除の対象になるかどうかは、治療の目的によって判断されます。噛み合わせの異常によって食事や発音に支障が出ているなど、機能改善を目的とした治療であれば、医療費控除の対象として認められる可能性があります。
たとえば、顎関節症の治療や成長期の子どもに対する矯正などが該当します。
一方で、審美目的の矯正や見た目を良くするためだけの治療は、医療費控除の対象外とされます。判断に迷う場合は、治療前に歯科医師に確認してみましょう。
噛み合わせが悪いまま放置するリスク

噛み合わせの乱れは、見た目や食べにくさといった表面的な問題だけにとどまらず、全身のさまざまな不調を引き起こす原因となることがあります。ここでは、噛み合わせが悪いままの状態を放置することで生じるリスクについて詳しく解説します。
虫歯や歯周病のリスクが高まる
噛み合わせが乱れていると、食べ物のかすがたまりやすく、歯ブラシが届きにくい部分が生じます。その結果、清掃が不十分となり、プラークや歯石が蓄積しやすくなります。これが原因となって虫歯や歯周病が発症・悪化しやすくなるのです。
また、噛む力が一部の歯に集中して加わることで、歯の摩耗が進み、詰め物や被せ物が壊れやすくなるケースも見られます。日常的なケアをしっかり行っていたとしても、噛み合わせに問題がある限り、トラブルを繰り返す可能性があるため注意が必要です。
顎関節や筋肉への負担が蓄積する
噛み合わせのズレは、顎の動きや筋肉のバランスにも影響します。上下の歯が正しくかみ合わない状態では、咀嚼運動のたびに顎の関節に余計な負担がかかり、長期間にわたって続くと顎関節症へとつながるおそれがあります。
具体的には、口を開けるときに音が鳴る、顎が痛む、スムーズに開閉できないなどの症状が現れることがあります。加えて、噛む筋肉が常に緊張状態になることで、慢性的な肩こりや首のこり、頭痛を引き起こすケースも少なくありません。
見た目や発音に影響を及ぼすこともある
噛み合わせの状態は、顔の印象や輪郭にも影響を与えることがあります。歯並びが乱れていると口元が出て見えたり、顎が左右非対称になったりすることがあり、これがコンプレックスの原因になるのです。
また、前歯がかみ合っていない開咬と呼ばれる状態では、発音が不明瞭になる場合があり、会話の際に支障が出ることもあります。仕事や接客などで人と話す機会が多い方にとっては、社会的なストレスの一因となりかねません。
消化機能にも影響を及ぼすおそれがある
通常、しっかりと噛んで食べ物を細かくすることで、消化器官への負担を軽減しています。
しかし、噛み合わせが悪いと噛む力が不十分になり、十分に咀嚼されないまま飲み込んでしまうことが増えます。その結果、胃腸にかかる負担が大きくなり、消化不良や胃もたれなどを引き起こすかもしれません。
特に高齢の方や持病を抱える方にとっては、こうした影響が体全体の健康に直結する可能性があります。
心理的なストレスや生活の質の低下
噛み合わせの問題は、見た目や発音、痛みや違和感などを通して、心理的なストレスを生み出すことがあります。食事が楽しめなかったり、人前で話すのが億劫になったりすることで、日常生活の質が下がる可能性もあるでしょう。
また、慢性的な痛みや不調を抱えながら生活を続けることは、精神的な疲労にもつながりやすいです。気づかないうちに心身に負担をかけていることもあるのです。
長期的には全身の健康状態にも影響する
噛み合わせの不調が引き起こす影響は、局所的なものにとどまりません。顎関節や筋肉への負担が全身の姿勢バランスに影響し、結果として背骨や骨盤の歪みにつながることもあります。
これが足腰の痛みやしびれを引き起こすこともあり、単なる口腔内の問題では済まされない状況に陥る可能性もあります。
まとめ

噛み合わせの治療には、スプリント療法や咬合調整といった負担の少ない方法から、矯正治療やインプラントのように費用が高額になるケースまで幅広い選択肢があります。治療の目的や歯の状態によって方法は異なり、費用も大きく変わってきます。
保険が適用される治療もあるため、自己判断で放置せず、まずは歯科医師に相談することが大切です。
噛み合わせの乱れを放置すると、口腔内のトラブルや全身の不調にもつながるおそれがあります。違和感を抱えている方は早めに専門の診察を受け、将来の健康へのリスクを減らす一歩を踏み出しましょう。
噛み合わせの治療を検討されている方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2025.06.17更新
審美歯科で理想の前歯に!治療法やメリットを解説!
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

前歯の黄ばみや形、歯並びの乱れが気になり、人前で思いきり笑えないと感じている方もいるのではないでしょうか。口元に悩みを抱える方に選ばれているのが、見た目の美しさに焦点をあてた審美歯科治療です。
この記事では、前歯を美しくするための審美歯科治療と費用の目安について解説します。口元の印象を変えたい方は、ぜひ参考にしてください。
審美歯科治療とは

審美歯科治療とは、歯や口元の見た目を美しく整えることを目的とした治療です。一般歯科では、歯の機能の回復や維持を目的として治療を行います。審美歯科は、歯の機能回復や維持に加え、歯の色や形、歯並びなど見た目の美しさも追求している治療です。
口元が美しく整うと、心から自信を持って笑えるようになり、日常生活にも良い影響を与えるでしょう。また、治療によっては口腔内が清潔になり、虫歯や歯周病の予防につながることもあります。歯を美しく、健康に維持するために行われるのが審美歯科治療です。
審美歯科で前歯を美しくする方法と値段

ここでは、審美歯科で前歯を美しくする方法と、費用の目安についてご紹介します。
セラミック治療
セラミック治療は、透明感やツヤがあり天然歯に近い見た目をしたセラミックの詰め物や被せ物を使用した治療です。前歯の変色やすきっ歯、歯並びの軽度なずれがある場合に、セラミックを使って理想の状態に整えられます。
ただし、セラミック治療では、天然の歯を削らなくてはなりません。セラミックは割れることがあり、耐久性を高めるために厚く作成します。歯列におさまるように、土台となる歯を削る必要があるのです。
使用する部位やセラミックの種類によって異なりますが、費用の相場は1本あたり8万〜15万円程度です。
ラミネートベニア
ラミネートベニアは、歯の表面をわずかに削って、薄いセラミックの板を貼り付ける治療です。前歯の形を整える場合や、軽度のすきっ歯や変色を改善するケースに選択されています。歯を削る量が少なく、短期間で仕上げられるのが特徴です。
デメリットは、割れたり剥がれたりする可能性がある点です。また、軽度のすきっ歯であれば対応できるケースもありますが、歯並び自体を整えることはできません。費用は、1本あたり10万〜15万円程度が一般的です。
ホワイトニング
ホワイトニングは、薬剤を使用して歯を白くする方法です。着色汚れだけでなく、歯の内部の黄ばみを漂白して本来の白さを取り戻します。歯を削ったり動かしたりしないため、負担の少ない治療といえるでしょう。
ホワイトニングには、自宅でマウスピースと薬剤を使用して行うホームホワイトニングと、歯科医院で行うオフィスホワイトニングがあります。
ホームホワイトニングの場合は初回2万〜5万円程度が相場です。マウスピースを一度作成すると、薬剤代のみで継続できます。効果は6ヶ月程度持続することが多いです。
オフィスホワイトニングの費用相場は、1回あたり2万〜4万円程度です。理想の白さになるまでに3〜5回程度かかり、3〜6ヶ月程度効果が持続します。
PMTC
PMTCは、歯科医師や歯科衛生士が行う専門的な歯のクリーニングです。専用の器具を使ってコーヒーやタバコのヤニなどによる着色汚れを取り除きます。また、歯の表面に付着した歯垢や歯石を徹底的に除去できるため、虫歯や歯周病のリスクを低減できるのもメリットです。
費用の相場は、1回あたり5,000円〜1万5,000円程度です。
矯正治療
歯並びが気になる場合には、矯正治療も選択肢のひとつです。噛み合わせに問題がなく、前歯のガタつきやすきっ歯を治療したい場合は、部分矯正で対応できる場合があります。
ただし、歯並び全体が悪い場合や、噛み合わせを調整する必要がある場合は、全体矯正が必要です。全体的に治療する場合は費用が高額になります。
費用はワイヤー矯正やマウスピース矯正といった治療方法によって異なりますが、部分矯正は30万〜60万円程度、全体矯正は60万〜120万円程度です。
審美歯科で前歯を美しくするメリットは?

審美歯科で前歯を整えると、見た目の変化に伴い、日常生活にも良い影響が期待できます。ここでは、前歯を美しくするメリットについて解説します。
笑顔に自信を持てる
前歯が変色していたり、形が崩れていたりすると、口元を気にする方もいるはずです。審美歯科で前歯を整えると、コンプレックスを解消でき、笑顔に自信を持てるきっかけになります。笑顔が増えると周りにポジティブな印象を与え、人間関係にも良い影響を与えます。
人との会話時や、人前で話す際にも前向きになり、コミュニケーションが円滑に進みやすくなるでしょう。
第一印象が良くなる
口元は第一印象を決める大きな要素となります。整った歯並びや白い歯は、清潔感や親しみやすさを感じさせやすいです。審美歯科で前歯を整えると、ビジネスや接客業など、人と接する場面で好印象を与えやすくなるでしょう。
虫歯や歯周病の予防につながる
審美歯科で使用するセラミックは、ツルツルとして汚れがつきにくい素材です。虫歯の治療でセラミックの被せ物をした場合、歯との間に隙間ができにくく、汚れがつきにくいため銀歯と比べて虫歯の再発リスクを抑えられます。
また、歯列矯正で歯並びが整うと、歯磨きがしやすくなり、歯垢が溜まりにくくなるため、虫歯や歯周病の予防につながります。治療方法によっては、見た目の改善だけでなく、お口の健康を守るうえでも役立つのです。
長期的な美しさが期待できる
セラミッククラウンやラミネートベニアなどの審美歯科で使用されるセラミック素材は劣化しにくく、耐久性が高い素材です。例えば、保険が適用される銀歯やレジンの寿命は5年程度とされています。
一方で、セラミックは10年以上使用できることが多いです。定期的にメンテナンスを行うと、長期間美しい状態を維持できるのは大きなメリットでしょう。
審美歯科で前歯を美しくするデメリットは?

ここでは、審美歯科で前歯を美しくするデメリットについて解説します。
歯を削る場合がある
セラミック治療では、歯を削らなくてはなりません。歯を削ると歯の内側にある象牙質が露出しやすくなり、知覚過敏の症状が現れる場合があります。また、歯がもろくなり、欠けやすくなる可能性もあります。一度削った歯は元に戻せないため、慎重に検討しましょう。
費用が高額になる
審美治療は見た目の改善を目的とした治療であるため、原則として保険が適用されず、全額自己負担となります。1本の歯を治療するだけでも、数万円以上の費用がかかることは珍しくありません。
費用が高額になる理由は、保険適用外の高品質な素材を使い、より専門的な器材を使って治療するためです。例えば、セラミックの被せ物やラミネートベニアでは1本あたり10万円前後かかり、複数の歯を治療すると、さらに費用負担は大きくなります。
審美治療で行った仕上がりを維持するためには、定期的に歯科医院を受診し、トラブルがないかチェックを受けたりクリーニングを受けたりする必要があります。治療費用だけでなく、治療後のメンテナンス費用も考えておくと良いでしょう。
セラミックは割れるリスクがある
審美歯科で使用されるセラミック素材は、強い衝撃を受けると破損するリスクがあります。
硬いものを強く噛んだり、転倒して強い衝撃を受けたりすると、割れたり欠けたりする場合があるのです。特に、歯ぎしりや食いしばりの癖があると、セラミックに対して継続的に大きな負担がかかり、破損するリスクが高まります。
破損して再治療が必要になると、追加で費用がかかります。硬いセラミック素材を使用する、ナイトガード(就寝用のマウスピース)を作製するなどの対策が必要です。歯ぎしりや食いしばりのある方は、治療を始める前に歯科医師に相談しておきましょう。
メンテナンスが必要である
審美歯科治療によって前歯を整えたあと、何もせずに一生維持できるわけではありません。美しい状態を維持するためには、メンテナンスが不可欠です。
例えば、ホワイトニング後の白くなった歯は、飲食物の影響で少しずつ色味が後戻りします。理想の白さを維持するためには、定期的に再施術が必要になるのです。
また、セラミックは耐久性に優れた素材ですが、経年劣化や破損のリスクがあります。トラブルがあった際に適切な処置を行うためにも、歯科医院での定期的なチェックとクリーニングを受けることが大切です。
まとめ

審美歯科治療は、歯の機能回復だけでなく、歯や口元の美しさを整えることを目的とした治療です。前歯をきれいにして口元を整えると、見た目のコンプレックスを解消して笑顔に自信を持てるようになり、人間関係にも良い影響を与えられるでしょう。
治療方法には、歯を内側から白くするホワイトニングや、着色汚れや歯石を徹底的に除去するPMTC、ツヤと透明感のあるセラミックを歯に貼り付けるラミネートベニアなどがあります。
治療を検討する際は、見た目だけでなく、治療上のリスクやメンテナンスの費用も考慮することが大切です。前歯の審美治療が気になった方は、歯科医院で相談してみてください。
審美歯科治療を検討されている方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2025.06.10更新
子どもが虫歯になったらどうやって治療する?予防法も
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

子どもの歯は虫歯になりやすく、進行が早いです。乳歯だからといって放置すると、永久歯や噛み合わせに悪影響を与えるおそれもあります。
「子どもの虫歯はどのように治療するの?」「虫歯にさせないためにはどうすればよいの?」と考えている保護者の方もいるでしょう。
この記事では、子どもが虫歯になったときの治療法や虫歯を予防する方法、虫歯治療を受けられる年齢について解説します。お子さまの健康な歯を守るために、ぜひ参考にしてください。
子どもの虫歯の特徴

子どもの虫歯には、以下の特徴があります。
進行が早い
乳歯は石灰化が進んでいないため、永久歯に比べて歯質がやわらかいです。また、乳歯の表面のエナメル質は、永久歯のエナメル質の半分ほどの厚さしかありません。そのため、虫歯の進行が早く、短期間で神経に到達する恐れがあります。
気づきにくい
初期段階の虫歯は白っぽく濁った色をしていることが多く、保護者の方が見ても気づきにくいです。また、虫歯が進行して軽度の痛みが生じても、子どもは痛みをうまく訴えられないことがあります。
痛みが激しくなるまで、保護者の方が気づかず時間が経過することも多いでしょう。乳歯の虫歯は進行が早いため、痛みが激しくなった頃には神経まで到達していることも少なくありません。
永久歯に悪影響を与える
乳歯が虫歯になった場合、永久歯に悪影響を与えかねません。歯の根元まで虫歯菌が感染して膿が溜まると、変色した永久歯が生えてきたり、本来の歯の形ではない状態で生えてきたりする場合があります。
また、虫歯を放置して早期に乳歯を失うと、隣の歯が倒れてきて永久歯が生えてくるスペースがなくなり、歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼす恐れもあります。
子どもが虫歯になったらどうやって治療する?

前述したとおり、子どもの虫歯は気づきにくく進行が早いため、早めに治療することが大切です。ここでは、子どもが虫歯になったときの治療方法について、虫歯の進行段階別に解説します。
初期の虫歯
歯の表面のエナメル質が溶けている虫歯の初期段階であれば、フッ素を塗布して再石灰化を促し、様子を見ることが多いです。再石灰化とは、溶け出したカルシウムやリンが再び歯の表面に取り込まれ、エナメル質が修復されることです。
再石灰化は、唾液によっても行われます。そのため、歯科医院でのフッ素塗布だけでなく、間食を控えて普段のブラッシングをきちんと行うことも大切です。家庭で適切に歯磨きを行えるよう、ブラッシング指導も行います。
エナメル質の虫歯
エナメル質が溶け、穴が空いた段階になると、虫歯の部分を削ってレジン(歯科用プラスチック)や金属で詰め物をします。状態によっては、フッ素を塗布して様子をみる場合もあります。自覚症状は少なく気づきにくいため、歯科検診で発見されることも多いです。
歯の表面のみの治療なので、通院回数は1回程度です。
象牙質の虫歯
エナメル質の内側にある象牙質まで虫歯が進行すると、冷たいものや甘いものがしみることがあります。エナメル質の虫歯と同様に、虫歯の部分を削って詰め物をします。
歯を大きく削った場合は、詰め物をするための型取りが必要です。小さく削って詰めるだけなら1回の通院で治療できますが、型取りをする場合は2回の通院が必要となります。
神経まで達している虫歯
虫歯が神経まで進行すると、何もしていなくても強い痛みを生じることがあります。この段階になると、根管治療が必要です。
根管治療とは、神経や血管が入った根管の内部を取り除き、清掃する治療です。虫歯の部分を削ったあと根管治療を行い、被せ物をして噛む機能を回復させます。早くに歯を失うと、歯並びや噛み合わせに影響する場合があるため、生え変わりまで歯を維持させることが大切です。
根管治療は何度かに分けて行うため、4〜6回程度の通院が必要となります。
歯根まで進行している虫歯
虫歯が進行して歯根まで到達し、ほとんど残っていない場合は抜歯が必要です。乳歯を早期に失うと、隣接する歯が倒れてくる可能性があります。そのため、永久歯が正しい位置に生えるスペースを確保するための治療を行う場合があります。
虫歯の治療は何歳から受けられる?

子どもが虫歯治療を受けられる年齢は3歳頃が目安になります。3歳頃になると、歯科医院の椅子に座り、口を開けてじっとしていられるようになる子どもが多いためです。
治療を受けられるかどうかは、子ども自身が協力して治療が受けられるかどうかがポイントです。4〜5歳頃になると、歯科医師とのコミュニケーションがとりやすくなるため、治療を進めやすくなるでしょう。
治療を行う際は、無理に治療を進めるのではなく、歯科医院の椅子に座ったり、口を開けたりして歯科医院に慣れることから始めます。恐怖心を抱くと治療をスムーズに進められなくなるためです。
また、小さい頃から定期検診を受けておくと、虫歯になったときにスムーズに治療を始められます。乳歯が生え始める生後6ヶ月ごろ、遅くても乳歯が生えそろう1歳半頃には受診するとよいでしょう。
子どもが虫歯になるのを防ぐためには

子どもが虫歯になるのを防ぐためには、保護者がサポートすることが大切です。ここでは、子どもの虫歯を予防する方法を紹介します。
毎日の歯磨きを習慣づける
子どもの虫歯予防の基本は、毎日の歯磨きです。毎食後と寝る前に行うのが理想ですが、最低でも1日1回は歯を磨きましょう。就寝中は唾液が少なくなり虫歯のリスクが高まるため、寝る前の歯磨きは習慣にしてください。
歯磨きは歯が生え始めた頃から開始し、自分で歯ブラシを握れるようになったらストッパーがついた歯ブラシを持たせましょう。歯磨きの絵本を読んだり、子どもが好きなキャラクターの歯ブラシやフルーツ味の歯磨き粉を使用したり、楽しく取り組めるよう工夫しましょう。
保護者の仕上げ磨きを徹底する
永久歯が生える12歳頃までは保護者が毎日仕上げ磨きを行いましょう。子どもは、大人に比べて手先を器用に動かせず、歯のすみずみまで丁寧に磨くことは難しいためです。毎日最低でも1日1回、就寝前に仕上げ磨きを続けると、虫歯予防につながります。
子どもは上顎の真ん中の歯と歯の間や、奥歯と奥歯の間、奥歯の溝に虫歯ができやすいため、特に注意して歯を磨いてあげましょう。
食生活を整える
子どもの虫歯を予防するために、食生活を整えることも大切です。虫歯の原因になる細菌は糖分をエサにして酸を作り出し、歯を溶かします。甘いお菓子やジュースを頻繁に摂っていると、口の中に糖分が長時間留まるため、虫歯のリスクが高まるのです。
おやつは決まった時間に与え、だらだらと時間をかけて食べたり飲んだりしないよう声をかけましょう。焼き芋やおせんべいなど、糖分が少なく歯にくっつきにくい食べ物を選ぶのも虫歯予防に効果的です。
フッ素を塗布する
歯が生え始めた生後6ヶ月頃から、フッ素の塗布を行うのも虫歯予防として有効です。フッ素は、歯の表面のエナメル質を強化し、虫歯になりにくい歯にします。また、歯から溶け出したカルシウムやリンを取り込んで修復させる再石灰化も促す効果もあります。
効果は3ヶ月程度持続するといわれているため、虫歯予防のためには3ヶ月に一度程度フッ素を塗布しましょう。また、普段の歯磨きにも市販のフッ素入りの歯磨き粉を使用すると虫歯予防になります。
定期的に歯科医院を受診する
子どもの虫歯を予防するためには、歯科医院での定期検診を受けることも大切です。虫歯は初期段階では見た目で判断しにくく、痛みや違和感などの症状もほとんどありません。子どもは虫歯の進行が早いため、痛みが生じたときには神経まで達している場合もあります。
定期的に歯科医師がチェックすれば早期に発見でき、負担の少ない治療で済む可能性が高くなります。また、歯科医院ではクリーニングやフッ素塗布、ブラッシング指導などを通じて虫歯を予防することも可能です。
痛みや違和感などの症状がなくても、3〜4ヶ月に一度程度は受診するとよいでしょう。
まとめ

子どもの虫歯は進行が早く気づきにくい特徴があります。虫歯になった場合、初期段階で発見できればフッ素の塗布のみで様子をみることもありますが、虫歯が神経まで進行した場合は、虫歯を大きく削って根管治療が必要です。
虫歯を予防するには、毎日保護者が丁寧に仕上げ磨きをし、できるだけ甘いものを減らしましょう。
定期的に歯科医院を受診すると、虫歯になっても早期に発見でき、治療の負担も少なく済みます。フッ素の塗布やクリーニングによって虫歯予防につながるため、症状がなくても歯科医院を受診しましょう。
子どもの虫歯治療を検討されている方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2025.06.03更新
治療期間はどのくらい?マウスピース矯正を始める前に知っておきたいこと
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

透明で目立ちにくいマウスピース矯正は、近年多くの方に選ばれている矯正治療のひとつです。見た目や使いやすさだけでなく「治療にどのくらいの期間がかかるのか?」という点も、治療を検討するうえで気になるポイントではないでしょうか。
今回は、マウスピース矯正の一般的な治療期間や、治療が長引く原因、効率的に治療を進めるためのポイントについて、わかりやすく解説します。
マウスピース矯正の治療期間

「マウスピース矯正はどのくらいの期間がかかるの?」と気になっている方は多いのではないでしょうか。見た目が自然で、取り外しもできる人気の治療法ですが、治療の流れや完了までのスケジュールをイメージしづらいと感じる方もいるかもしれません。
ここでは、マウスピース矯正の主なステップごとの期間と、症例によって治療期間に差が出る理由についてわかりやすく解説します。
マウスピース矯正の治療の流れと期間の内訳
マウスピース矯正は、準備期間・矯正期間・保定期間の3つのステップを経て進行します。
まず、治療前には精密検査やシミュレーションを実施します。この準備に1〜2週間、その後マウスピースの作成に2〜4週間ほどかかるため、準備期間としては1〜2ヶ月程度を見込んでおきましょう。
マウスピースの装着が始まると、歯を動かす矯正期間に入ります。この期間は症例によって異なりますが、平均的には6ヶ月〜3年程度が目安です。1〜2週間ごとに新しいマウスピースへ交換し、段階的に歯を動かしていきます。
歯並びが整ったら治療完了ではなく、後戻りを防ぐための保定期間に移行します。この段階ではリテーナーと呼ばれる保定装置を使用し、歯の位置を安定させていきます。保定期間は通常1〜2年程度が目安です。
このように、マウスピース矯正は複数の段階を経て進行します。それぞれに必要な時間を把握することで、治療全体の流れをイメージしやすくなります。
治療期間に差が出る理由
マウスピース矯正の治療期間は6ヶ月〜3年程度が一般的ですが、実際の治療期間は患者さまの歯並びや治療の目的によって大きく変わります。たとえば、軽度の歯列不正であれば6ヶ月程度で完了することもあるでしょう。
しかし、歯を大きく移動させる必要があるケースや、噛み合わせの調整を伴う場合には2〜3年かかることもあります。治療の難易度によって必要なマウスピースの枚数が異なるため、期間にも差が生じるのです。
また、歯の動きやすさには個人差があるほか、装着時間の管理状況や通院頻度など、日ごろの協力度合いも治療の進み具合に影響します。治療期間を正しく把握するには、歯科医師による精密な検査と、個別に合わせた治療計画を立てることが大切です。
マウスピース矯正の治療が長くなるケース

いくつかの要因により、当初の計画より治療が長引くこともあります。治療期間が延びる可能性をあらかじめ理解しておくことで、納得感を持って取り組みやすくなるでしょう。
ここでは、マウスピース矯正が予定より長くなるケースについて、原因とともに解説します。
症例が複雑なケース
マウスピース矯正では、歯列の状態が複雑であるほど治療に時間がかかる傾向があります。たとえば、前歯が噛み合わない開咬や、噛み合わせが深い過蓋咬合、歯が重なっている叢生などが挙げられます。
これらの歯列不正の場合は慎重な調整が必要になるため、治療期間が長くなることがあります。
また、奥歯の位置関係を大きく変える必要がある症例では、特に成人の場合、骨格の成長が完了しているために治療が進みにくくなるケースもあります。さらに、歯の動きには個人差があり、必ずしも計画どおりに進まないこともあるため、柔軟な対応が必要となります。
複雑な症例では、治療を始める前に歯科医師と十分に話し合い、期間の見通しや可能な範囲を理解しておくことが重要です。
装着時間が不足したケース
マウスピースは、1日あたり20〜22時間の装着が基本とされています。学校や職場で外したまま過ごす時間が長くなった、旅行やイベントで装着を怠る日が続いたなど、装着時間が不足すると、歯の移動が進みません。
その結果、歯の移動にズレが生じ、追加のマウスピース作製や治療計画の見直しが必要になるケースも考えられるでしょう。治療期間の延長を避けるためにも、装着時間を意識しながら、安定した使用習慣を保つことがポイントです。
計画どおりにマウスピース矯正を進めるためのポイント

マウスピース矯正をスムーズに進め、計画通りの期間で治療を終えるには、いくつかの重要なポイントがあります。装着時間の管理や通院のタイミング、日常生活での取り扱いなどに気を配ることで、治療の進行が安定しやすくなります。
ここからは、マウスピース矯正を順調に進めるための実践的なポイントについて解説します。
指示された装着時間を守る
マウスピース矯正において最も重要なのは、適切な装着時間の確保です。治療計画を順調に進めるためには、1日20〜22時間の装着時間を守ることが重要です。
取り外しが可能なマウスピースは便利な反面、自己管理が必要になります。装着時間が不足すると歯の移動が予定より遅れ、治療の延長につながるおそれがあります。
たとえば、食事のあとに装着を忘れたり、話しづらさを理由に長時間外したままにしたりすると、マウスピースが合わなくなり、再作製が必要になる可能性があります。こうしたトラブルを避けるためには、装着を習慣化することがポイントです。
専用のアプリやタイマー機能を活用すると、装着忘れを防ぎやすいでしょう。装着時間の記録や交換時期の通知機能を活用することで、自分の使用状況を客観的に把握できます。
特に、治療の初期段階では、装着と取り外しの記録をつけることで継続しやすくなります。
定期的な通院を欠かさない
マウスピース矯正は自宅での管理が中心ですが、定期的な歯科医院への通院も治療成功のための重要なポイントです。一般的には2〜3ヶ月に一度のペースで通院し、歯の動きやマウスピースの適合状態を確認します。
診察では、計画通りに歯が移動しているかをチェックし、必要に応じてアタッチメントの追加や調整を行うこともあります。こうした細かな調整によって、歯の移動効率が高まりやすくなります。
さらに、新しいマウスピースがきちんとフィットしているかの確認も、治療の精度を保つために欠かせない工程です。定期的なチェックを怠ると、マウスピースの不適合や歯の動きのズレに気づくのが遅れ、治療計画の修正が必要になるおそれもあります。
通院のスケジュールはできる限り守り、気になることがあればその都度担当医に相談しましょう。また、受診できない場合でも、早めに次回の診察日を確保するよう心がけましょう。
通院間隔が空きすぎると、治療全体に影響が出ることもあるため注意が必要です。
マウスピースの取り扱いに注意する
マウスピースは熱や乾燥に弱く、変形や破損が起こると使えなくなってしまいます。日々のお手入れや保管にも気をつけ、丁寧に取り扱うことが大切です。
洗浄の際はぬるま湯を使い、熱湯やアルコール消毒は避けるようにしましょう。また、食事中にティッシュに包んで置いておき、うっかり捨てたというケースも少なくありません。そうした紛失を防ぐためにも、専用の保管ケースを活用しましょう。
もし破損や紛失が起きてマウスピースを作り直すことになれば、その分治療期間が延びる可能性があります。毎日の取り扱いを丁寧に行うことが、スムーズな治療につながります。
まとめ

マウスピース矯正は、目立ちにくく取り外しも可能な点から、幅広い年代の方に選ばれている矯正方法です。治療期間は一般的に6ヶ月〜3年程度とされますが、歯並びの状態や装着状況によっては、当初の想定より長引く場合もあります。
治療を計画通りに進めるには、1日あたり20時間以上の装着時間を守ること、定期的に通院して経過を確認することが重要です。マウスピースの取り扱いを丁寧に行うことも欠かせません。
マウスピース矯正を検討されている方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
ARTICLE
SEARCH
ARCHIVE
CATEGORY
- CAD/CAM冠
- IPR
- MTM
- インビザライン
- インビザライン・エクスプレス
- インビザライン・コンプリヘンシブ
- インビザライン・モデラート
- インビザライン・ライト
- インビザライン矯正
- インプラント治療
- オールセラミック
- カウンセリング
- ジルコニア
- ジルコニアセラミック
- セラミック
- セラミック歯
- セラミック治療
- デメリット
- デンタルローン
- ハイブリッドセラミック
- ブラケット
- ブリッジ
- ホワイトニング
- マウスピース
- マウスピース型
- マウスピース矯正
- メタルタトゥー
- メタルボンド
- メリット
- メンテナンス
- ラミネートベニア
- リスク
- ワイヤー
- ワイヤー矯正
- 予防歯科
- 二酸化ジルコニウム
- 人工ダイヤモンド
- 仮歯
- 保定期間
- 保険適用
- 健康保険
- 入れ歯
- 全体矯正
- 出っ歯
- 前歯
- 医療費控除
- 受け口
- 口腔外科
- 噛み合わせ
- 噛み合わせ治療
- 嚙み合わせ
- 外科治療
- 天然歯
- 失敗
- 奥歯
- 定期検診
- 定期診察
- 審美
- 審美性
- 小児歯科
- 抜歯
- 歯ぎしり
- 歯並び
- 歯列矯正
- 歯周病
- 歯周病菌
- 歯型
- 歯科技工士
- 歯科検診
- 歯科矯正
- 歯茎
- 治療期間
- 症例
- 矯正期間
- 矯正歯科
- 矯正装置
- 精密検査
- 自由診療
- 自費診療
- 虫歯
- 虫歯治療
- 虫歯菌
- 被せ物
- 親知らず
- 詰め物
- 費用
- 通院
- 通院頻度
- 部分入れ歯
- 部分矯正
- 金属
- 金属アレルギー
- 銀歯
- 顎関節症
- 食いしばり