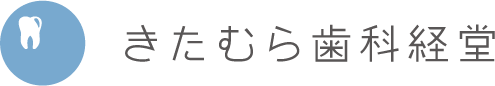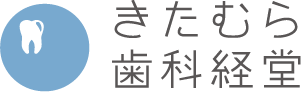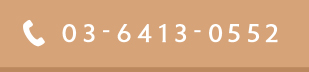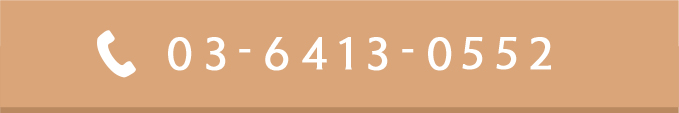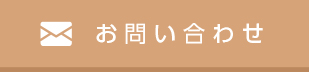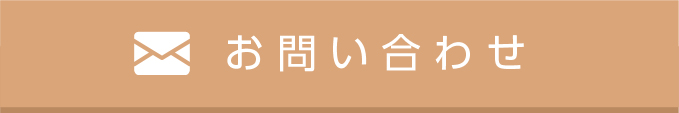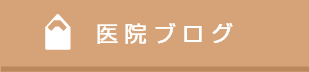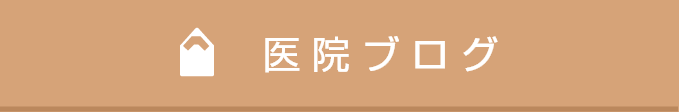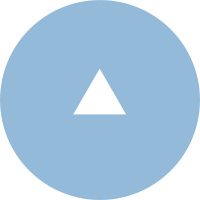2025.04.29更新
入れ歯の寿命はどれくらい?長持ちさせるためのポイントとは
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

入れ歯は、歯を失った際に噛む力や見た目を回復するための大切な治療法です。「入れ歯の寿命はどれくらい持つのだろう?」「ずっと使い続けられるのか不安」と感じている方も多いのではないでしょうか。
入れ歯には耐用年数があり、使い方やメンテナンスの方法によって寿命が大きく左右されます。
この記事では、入れ歯の平均的な寿命や、長く快適に使い続けるために押さえておきたいケアのポイントについて詳しく解説します。
入れ歯の寿命

入れ歯の寿命は、使用する素材や種類によって異なります。一般的には、保険診療の入れ歯で約5年、自費診療の入れ歯で約7〜10年程度が目安とされています。
ただし、これはあくまでも目安であり、使用状況や口腔内の変化によって寿命は前後します。入れ歯は毎日の食事や会話で使われるため、経年劣化や変形、すり減りが生じやすく、時間の経過とともに噛み合わせやフィット感が合わなくなることもあります。
また、顎の骨や歯ぐきの形状が変化することによって、入れ歯自体の調整や作り直しが必要になるケースもあります。快適に長く使うためには、定期的な点検と必要に応じたメンテナンスが不可欠です。
入れ歯の寿命が短くなる原因

入れ歯は毎日使う医療装置であるため、長く快適に使用するためには適切な取り扱いや定期的なケアが欠かせません。
しかし、いくら丁寧に扱っていても、思わぬ原因で寿命が短くなることがあります。ここでは、入れ歯の寿命が縮まる主な原因について解説します。
噛み合わせの変化に気づかず使用を続けた
入れ歯を作製した時点ではぴったりと合っていたとしても、時間の経過とともに口腔内の状態は変化します。歯ぐきや顎の骨は加齢や咀嚼の力によって徐々に痩せていき、それにより入れ歯との適合が悪くなります。
合わない入れ歯を無理に使い続けると、入れ歯本体にかかる負担が偏り、ヒビや破損の原因となることがあります。また、噛み合わせのズレが続くと、口腔内の粘膜や周囲の健康な歯にも悪影響を与える恐れがあります。
過度な咬合力や歯ぎしりの影響
無意識のうちに行われる歯ぎしりや食いしばりは、入れ歯に過度な力を加える原因のひとつです。特に、夜間に強く歯を食いしばる癖がある方は、入れ歯に大きなダメージを与える可能性があります。
強い圧力が長時間加わることで、人工歯が欠けたり、床の部分がたわんで変形するなど、入れ歯の破損リスクが高まります。こうしたケースでは、ナイトガードの併用や、噛み合わせの調整が必要となることがあります。
不適切な清掃や保管による劣化
入れ歯は食べ物のカスや細菌が付着しやすく、毎日の清掃が不可欠です。歯ブラシで強くこすりすぎたり、研磨剤入りの歯磨き粉を使うと、表面に細かい傷がつき、菌の温床になりやすくなります。
また、就寝中に水に浸けずに放置したり、高温のお湯で洗浄するなど、適切でない方法で保管することも劣化の原因となります。入れ歯の素材は繊細で、急激な温度変化や乾燥に弱いため、正しい洗浄と保管方法を守ることが大切です。
不注意による破損や変形
日常生活の中で、入れ歯をうっかり落としてしまうというケースは少なくありません。落下の衝撃で人工歯が外れたり、床が割れることもあり、修理が必要となる場合があります。
また、噛み切る力が強くかかる硬い食べ物を頻繁に食べると、入れ歯が歪んだり摩耗することもあります。特に、部分入れ歯で金属のバネを使っている場合、無理な方向からの力が加わると変形しやすく、装着時の違和感につながります。
定期検診を受けていない
入れ歯は使っているうちに徐々に摩耗し、形状もわずかに変化していきます。その変化を放置すると、知らず知らずのうちに不適合となり、寿命を縮める結果となります。
歯科医院での定期的な検診は、入れ歯の状態を確認するだけでなく、口腔内の健康を維持するためにも欠かせません。異常があった場合には早期に調整や修理を行うことで、大きなトラブルを防ぎ、結果として入れ歯の寿命を延ばせます。
入れ歯を長く使い続けるためのポイント

入れ歯は、歯を失った際の噛む力や発音、見た目を補うために欠かせない医療器具です。
しかし、入れ歯は消耗品であり、永続的に使えるものではありません。だからこそ、できるだけ長く快適に使い続けるためには、日頃の正しい使い方とメンテナンスが重要です。
以下に、入れ歯の寿命を延ばすために押さえておきたいポイントについて詳しく解説します。
毎日の清掃を丁寧に行う
入れ歯は、天然の歯と同様に食事のたびに汚れが付着します。そのままにしておくと、口臭や歯周病、口内炎の原因になり、入れ歯自体も劣化しやすくなります。清掃は1日1回ではなく、毎食後を基本とし丁寧に行うことが理想です。
清掃時には、入れ歯専用のブラシを使用し、やさしい力で磨くことが大切です。歯磨き粉には研磨剤が含まれていることが多く、入れ歯の表面に細かい傷をつける恐れがあるため、使用しないようにしましょう。
汚れをうまく取り除けないときは、入れ歯用の洗浄剤を併用するのも効果的です。
正しい保管方法を守る
入れ歯は乾燥や熱に弱いため、使用していないときの保管方法にも注意が必要です。特に就寝時には、乾燥による変形を防ぐために水に浸けて保管することが基本です。
また、入れ歯を熱湯で洗ったり、高温になる場所に置いたりすることも避けましょう。熱により素材が変形し、フィット感が損なわれる原因になります。
持ち運ぶ際や外出先で外す場合にも、専用のケースを使って清潔かつ安全に保管することが大切です。
入れ歯に過度な負担をかけない
入れ歯の素材は繊細で、強い力や衝撃には弱い一面があります。硬い食べ物を無理に噛もうとしたり、歯ぎしりや食いしばりの癖がある場合、入れ歯に強い負担がかかって破損する可能性があります。
また、部分入れ歯を使っている方は、バネ部分に不自然な力が加わらないよう注意が必要です。破損や変形が生じると、修理が必要になるだけでなく、口腔内に不快感を与える原因にもなります。
違和感を覚えた場合は自己判断で使い続けず、早めに歯科医院で診てもらうようにしましょう。
定期的な歯科検診を受ける
時間の経過とともに使用者の顎の骨や歯ぐきの形が変化し、徐々に入れ歯は合わなくなっていきます。見た目に変化がなくても、少しずつズレが生じているケースは少なくありません。
ズレた入れ歯を使い続けると、口内の粘膜が傷つきやすくなるほか、他の健康な歯にも負担がかかりやすくなります。このような問題を未然に防ぐには、半年から1年に1回の頻度で歯科医院での定期検診を受けることが重要です。
入れ歯の状態だけでなく、口腔内の健康状態や噛み合わせのチェックもあわせて行ってもらうことで、トラブルの早期発見と対応につながります。
装着中の違和感を放置しない
「少し痛いけれど我慢できる」「食べにくいけれど仕方がない」と違和感をそのままにしていると、症状が悪化して口内炎や炎症の原因になることがあります。装着時にズレを感じたり、食事中に違和感があったりする場合は、我慢せず早めに受診しましょう。
違和感がある状態で使用を続けると、入れ歯の変形だけでなく、咬合バランスの崩れや他の歯の損傷にもつながる恐れがあります。定期的な調整を行うことで、入れ歯の機能と快適性を保てます。
夜間の使用について考える
入れ歯は就寝時に外すことが基本ですが、顎の状態や個人の習慣によっては夜間も装着する必要があるケースがあります。
ただし、常に装着していると歯ぐきに休息を与える時間がなくなり、炎症や感染のリスクが高まるため注意が必要です。夜間も使用する場合は、定期的に歯ぐきの状態を確認し、必要に応じて歯科医師の指導を受けましょう。
入れ歯と歯ぐきの間に食べカスが残ったまま放置すると、細菌が繁殖しやすくなるため、毎晩の清掃と朝の装着前の確認が欠かせません。
まとめ

入れ歯の寿命は、一般的に保険診療で約5年、自費診療で7〜10年程度が目安とされています。
しかし、使用状況やメンテナンスの有無によって大きく左右されます。寿命を縮める原因には、噛み合わせの変化や強い咬合力、不適切な清掃・保管、定期検診の不足などが挙げられます。
入れ歯を長く快適に使い続けるには、毎日の丁寧な清掃、正しい保管方法、無理な力をかけないこと、そして定期的な歯科受診が欠かせません。入れ歯を正しく扱い、変化に気づいたら早めに対応することで、寿命を延ばし、口腔内の健康も維持できます。
入れ歯治療を検討されている方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2025.04.22更新
今日から実践!歯周病を予防するためにできること
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

「歯磨きの時に歯茎から出血する」「歯周病は治療できるの?」「歯周病って予防できるの?」など、歯周病に関して悩んでいる人は多いのではないでしょうか。歯周病はプラークによる細菌感染が主な原因となり、歯茎に炎症を起こす病気です。
将来的に歯を失うこともある歯周病には、正しい予防と適切な治療が必要です。
今回は、歯周病の原因や歯周病の予防と早期発見が大切な理由、歯周病を予防する方法について詳しく解説します。
歯周病の原因

歯周病は炎症性疾患で、主な原因は歯と歯茎の間に蓄積するプラーク(歯垢)です。プラークは細菌の塊で、適切に除去されないと歯石へと変化し歯周組織を破壊します。
また、生活習慣なども歯周病のリスクを高める要因となります。ここでは、歯周病の主な原因について詳しく解説します。
喫煙
ニコチンやタールなど、たばこに含まれる有害物質が口腔内の粘膜や歯肉から体内に吸収されると、免役力が低下します。十分な血液が歯茎に届かなくなることから、細菌に対する抵抗力が低くなり歯周病のリスクがアップします。
タバコは歯周病を悪化させるだけでなく、治りにくくする特徴もあります。また、受動喫煙も歯周病に影響を及ぼすとされています。
よく噛まずに食べる
食事の際に食べ物をよく噛まないと、唾液が十分に分泌されないことから、口内の自浄作用が低下して細菌が繁殖しやすくなります。食べ物をよく噛むことで顎の筋肉が鍛えられ、血液の循環が良くなり免疫力がアップし、歯周病の予防につながります。
食事の際は、よく噛んで食べることを心がけましょう。
不適切な口腔ケア
毎日のケアで、適切にブラッシングが行われないとプラークが蓄積しやすくなります。また、歯ブラシだけのお手入れでは、歯と歯の間に汚れが残りやすいです。
歯間に残った汚れが歯周病の原因となることがあるため、歯周病を予防するためにはデンタルフロスや歯間ブラシの使用が欠かせません。
歯周病の予防と早期発見が大切な理由

歯周病は、初期段階での治療が非常に重要な病気です。放置して進行すると、歯を支える骨や歯茎が破壊され、最終的には歯を失うリスクが高まります。
ここでは、歯周病の予防と早期発見が大切な理由についてまとめます。
歯の喪失を防げる
歯周病が進行すると、歯を支える歯槽骨や歯茎が徐々に破壊されます。歯がぐらつき、最終的には抜け落ちることもあります。歯周病の進行を食い止め、歯を支える組織を回復させるためには早期に治療することが望ましいです。
しかし、治療が遅れると外科的な治療が必要になるケースが多く、治療の負担が増加します。また、回復までの時間も長くなる傾向があります。
治療費を節約できる
歯周病が悪化すると、歯周外科治療や歯周再生療法など、高度で費用のかかる治療が必要になるケースがあります。必然的に通院回数も増え、時間的な負担も大きくなります。
早期に発見すると、スケーリングや日常的なケアの指導が主な治療内容となるので、治療にかかる時間はもちろん費用も抑えられます。歯周病を早期に発見すると、治療も早い段階で開始できるため、経済的負担を軽減し時間を効率的に活用できます。
口腔内の快適さが向上する
歯周病が進行すると、歯茎の腫れや出血、口臭、歯のぐらつきや痛みなどの不快な症状を引き起こします。これらの症状は、食事や会話を楽しめないなど、日常生活に大きな支障をきたします。
早期に発見し治療を開始すれば、口腔内の快適さを取り戻せるでしょう。
全身の健康を守れる
歯周病は、口腔内だけでなく、全身の健康にも影響を及ぼします。進行した歯周病は、糖尿病の悪化、心筋梗塞や脳梗塞、妊娠中の早産や低体重児出産などのリスクを高めることが分かっています。
早期に発見し治療すれば、これらの全身疾患のリスクを減らすことが可能です。歯科治療を通じて全身の健康が守られるのは、早期発見・早期治療の大きなメリットといえるでしょう。
再発予防が容易になる
慢性的な疾患の歯周病は、治療後も再発の可能性があります。早期に治療を受けることで、健康な状態を維持しやすくなり、再発のリスクを最小限に抑えられるでしょう。
歯周病を予防するためには

ここでは、歯科医院で行う予防法と、自宅でできる予防法について詳しく解説します。
歯科医院で行われる予防法
歯周病は、適切な予防策をとることで発症を抑えられます。まずは、歯科医院で実施される予防策をご紹介します。
定期的な歯科検診
歯周病の予防では、定期的な歯科検診が欠かせません。歯科検診では、歯茎の出血の有無、歯周ポケットの深さなどをチェックします。初期段階では自覚症状が乏しいため、定期検診で歯周病の有無を確認することが重要なのです。
定期検診の目安は3~6か月に一度ですが、個々の口腔状態やリスクに応じて歯科医師と相談して適切な頻度を決めるようにしましょう。万が一、歯周病に罹患していても、初期のうちに治療を開始できるメリットがあります。
クリーニング
国家資格を保有する歯科医師や歯科衛生士が行うクリーニングでは、専用の機械や薬剤を使用して歯の隅々まで汚れを除去できます。毎日丁寧に歯を磨いても、歯と歯の間や歯と歯茎の境目などには磨き残しが生じます。
特に、奥歯の裏側や小臼歯などは歯ブラシの毛先が届きにくく、歯の形が丸いので磨き残しが多い箇所です。
汚れをそのまま放置していると徐々に歯石に変化し、歯周病の原因になります。プラークを歯石化しないためにも、定期的なクリーニングが重要です。
定期的にクリーニングを行うことで健康な歯茎を維持しやすくなるため、歯周病の予防につながります。
ブラッシング指導
歯磨きが得意でないと感じている場合は、必要に応じてブラッシング指導を受けるようにしましょう。利き手の違いや歯の形、歯並びなど、さまざまな要素が重なり、磨き方には一人一人癖があります。
そのため、同じ個所を磨き残す人は少なくありません。また、患者様の口腔内や歯並び、歯の形状、サイズに合わせた歯ブラシの選び方や当て方、動かし方を意識するだけで、きれいに磨けるようになる人も珍しくありません。
歯周病の予防には、デンタルフロスや歯間ブラシなどのツールを併用することも不可欠です。ブラッシング指導の際に、歯ブラシの動かし方だけでなくツールの使い方も教われば、毎日のセルフケアのクオリティを高められるでしょう。
自宅でできる予防法
歯周病の予防には、歯科医院で行う定期検診のほかに、生活習慣の改善など、自宅でできる予防法があります。
正しく歯磨きを行う
自己流の磨き方では、歯に付着した汚れをしっかり落とせない可能性があります。プラークを除去することを意識して、しっかり歯磨きしましょう。
歯を磨くというよりも、歯と歯茎の間や歯間のプラークを除去するイメージでブラッシングすると良いかもしれません。デンタルフロスや歯間ブラシを使用することも忘れないようにしましょう。
歯ブラシが届きにくい部分は、デンタルフロスや歯間ブラシも併用しながら、隅々まできれいにブラッシングしてください。歯磨きだけでは届かない部分の清掃が可能になり、より効果的にプラークを除去できます。
生活習慣を見直す
バランスの取れた食事や、抗酸化作用のあるビタミンCやカルシウムを含む食品を積極的に摂取することで、歯周病を予防できます。栄養の偏った食事は、身体の抵抗力を弱める恐れがあります。
食事を取ったり取らなかったりするような生活や、ダラダラといつまでも食事を続けることのないようにしましょう。いつまでも口内に食べ物が入っている状態が続くと、虫歯のリスクが上がるため、1日3食できるだけ決まった時間に食事を取るようにしてください。
また、十分な睡眠をとりストレスを適切に管理することで、免疫力を高められます。良い睡眠をとるためのポイントは、以下のとおりです。
- 起床時間と就寝時間を決める
- 朝日をしっかり浴びる
- 就寝前にスマホを見ない
- 就寝前の飲食を控える
- 入浴は寝る2~3時間前に終わらせる
毎日、7~8時間の睡眠時間を確保することが望ましいでしょう。健康的な生活習慣は、歯周病の予防だけでなく全身の健康維持にも重要です。
禁煙
喫煙は歯周病のリスクを高めるため、歯周病の予防として禁煙が推奨されます。喫煙者は非喫煙者に比べ、歯周病に罹患するリスクが高いです。そのため、禁煙することで歯周病の発症リスクを大幅に減少させられるでしょう。
患者様自身で禁煙が難しい場合は、禁煙をサポートするプログラムやカウンセリングを活用し、禁煙を成功させましょう。
まとめ

歯周病は自覚症状に乏しく軽視されがちですが、口腔内だけでなく全身疾患にも関連する怖い病気です。歯周病の予防と悪化防止には、歯科医院での定期検診はもちろん、患者様自身でのセルフケアが欠かせません。
歯周病は罹患する前に予防することが大切なので、まず歯科医院で定期検診を受け、現状の歯や歯茎をチェックして適切な治療を受けるようにしましょう。
歯周病予防に興味がある方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2025.04.15更新
審美歯科治療の費用はどれくらい?保険が適用されるのかも解説
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

「審美歯科は高いのではないか?」「審美歯科を保険で受けられないか」など、審美歯科の治療費について気になっている方も多いかもしれません。審美歯科は、一般歯科とは異なり、歯を綺麗にすることを目的とした治療を行います。
そのため、保険が適用される治療は少なく、治療費が高額になる傾向にあります。審美歯科治療の費用相場は、どれくらいなのでしょうか?
ここでは、審美歯科治療の費用や、保険適用の可否などについて解説します。
審美歯科とは

歯医者は大きく分けると、一般歯科と審美歯科の2種類があります。一般歯科は、虫歯や歯周病などの歯科疾患を治療するためのものであり、審美歯科は見た目を綺麗にすることを目的としたものです。
一般歯科では、虫歯や歯周病などの症状や機能を改善することを中心とした治療を実施します。そのため、見た目の改善に関しては最低限といえます。
一方で、審美歯科は見た目を綺麗にすることを重要視した治療です。具体的には、ホワイトニングや歯並びを綺麗にするための歯列矯正などが挙げられます。
一般歯科と審美歯科のどちらの治療を行う歯科医院もありますが、近年では審美歯科のみを扱う歯科医院も増えています。
審美歯科治療に保険は適用される?

結論から言うと、審美歯科治療は基本的に保険の適用外です。
保険診療は、病気やケガを改善することを目的とした治療のみが対象です。治療方法や治療範囲、使用する薬剤や量などは、公的に決められています。治療費用も決められているため、基本的にどの病院で治療を受けても同じ費用になります。
一方で、保険が適用されない治療は、自由診療と呼ばれています。自由診療には、治療方法や使用する薬剤に制限がありません。そのため、最新の技術を用いた治療を受けることができ、患者さまの希望に沿った治療を受けられます。
ただし、保険が適用されなければ費用は全額患者さまの自己負担になるため、費用は保険診療よりも高額になります。
審美歯科治療の費用

審美歯科にはさまざまな治療があり、治療内容ごとに費用が異なります。また、自由診療なので歯科医院が費用を自由に決定することができます。同じ施術でも、歯科医院によって費用に違いが生じます。
ここからは、審美歯科治療の主な治療法別の、費用相場を解説します。
ホワイトニング
ホワイトニングは、黄ばんだ歯を白くするための治療です。オフィスホワイトニング・ホームホワイトニング・デュアルホワイトニングの3種類があります。
オフィスホワイトニング
費用相場は、1回あたり1万円~7万円です。
歯科医院で専用の薬剤を歯に塗布し、ライトを当てることで歯を白くする治療です。高濃度の薬剤を使用するため、一度でも効果を実感しやすいという特徴があります。
効果の持続期間は3~6カ月程度です。
ホームホワイトニング
費用相場は、3万円~5万円です。
歯科医院でマウスピースを作成し、自宅でマウスピースに薬剤を塗布して装着するホワイトニング方法です。マウスピースの装着時間は1日1~2時間程度で、徐々に歯が白くなっていくため効果を実感できるまでに時間がかかります。
効果の持続期間は半年~1年ほどです。
デュアルホワイトニング
費用相場は、5万円~8万円です。
オフィスホワイトニングとホームホワイトニングを組み合わせた方法です。オフィスホワイトニングによって早い段階で効果を実感でき、ホームホワイトニングによってホワイトニング効果の持続期間を長くできます。
効果の持続期間は1~2年ほどです。
クリーニング
費用相場は、5,000円~1万円ほどです。
日常の歯磨きでは取り除ききれない歯垢やプラーク(歯石)を除去します。審美目的の場合は、歯の着色汚れなども丁寧に除去していきます。ホワイトニングのように歯を漂白する効果はありませんが、歯が持つ本来の白さを取り戻せます。
歯列矯正
歯並びを綺麗に整えるための歯列矯正は、ワイヤー矯正とマウスピース矯正の2種類があります。それぞれの矯正方法の特徴と費用は、以下の通りです。
ワイヤー矯正
費用相場は、表側矯正で60万円~100万円、裏側矯正80万円~150万円です。
ワイヤー矯正は、歯の表面にブラケットという装置を取り付け、そこにワイヤーを通して負荷をかけることで歯を徐々に動かしていく方法です。ブラケットを表側につける治療を表側矯正といい、矯正装置が目立ちますが費用を抑えられます。
一方で、裏側矯正は歯の裏側に矯正装置を取り付ける方法です。矯正装置が目立ちにくくなる反面、高度な技術と知識が必要なため費用が高額になります。
マウスピース矯正
費用相場は、50万円~120万円です。
マウスピースを1日20時間以上装着し、1~2週間ごとに新しいマウスピースへ交換することで歯を動かしていく方法です。マウスピースは透明なので矯正をしていることが目立ちにくく、取り外せるので食事や歯磨きの負担がないというメリットがあります。
セラミック治療
虫歯などで歯を削った場合の詰め物(インレー)や、歯が欠損した部分に被せる被せ物(クラウン)の治療です。セラミックは陶器で作られた素材で、保険診療の銀歯や白いプラスチック材よりも天然歯に近い色やツヤを再現でき、自然な仕上がりになります。
セラミック治療で使用される素材は複数あり、費用と特徴が異なります。
オールセラミック
費用相場は、詰め物(インレー)で5万円~8万円、被せ物(クラウン)で8万円~20万円です。
セラミックのみで作られており、セラミック素材の中でも高い審美性を誇ります。透明感やツヤ、色調が天然歯と比べても見劣りなく、美しい見た目を求める方に選ばれています。
ただし、強い衝撃を受けると破損するリスクがあります。
ジルコニア
費用相場は、詰め物(インレー)で4万円~7万円、被せ物(クラウン)で10万円~20万円です。
ジルコニアは、人工ダイヤモンドと言われるほどの強度の高さを誇るセラミックです。セラミックの中でも強度が高いため、奥歯や歯ぎしり・食いしばりの癖がある場合などの治療に使用することが多いです。
しかし、オールセラミックに比べると透明感が劣ります。
ハイブリッドセラミック
費用相場は、詰め物(インレー)で3万円~4万円、被せ物(クラウン)で4万円~10万円です。
歯科用ブラスチックとセラミックを組み合わせた素材で、費用をもっとも抑えられる素材です。自然な見た目に仕上がりますが、他のセラミックと比べると強度に劣るので経年劣化する可能性があります。
メタルボンド
費用相場は、8万円~15万円です。
内側が金属で外側がセラミックに覆われた素材で、被せ物(クラウン)の治療でのみ使用されます。金属により強度が高まり、奥歯の治療に選ばれることが多いです。
ただし、金属を使用しているため、経年劣化で金属が溶け出すことや金属アレルギーのリスクがあります。
ラミネートベニア
費用相場は、9万円~15万円です。
歯の表面を薄く削り、色や形を綺麗に整える治療です。削った表面には薄いセラミックのシェルを貼り付けるため、歯の黄ばみを改善しながら自然な綺麗な色に仕上げられます。軽度の歯並びの改善のために実施されるケースもあります。
審美歯科治療にかかった費用は医療費控除の対象?

年間の医療費が一定額を超えた場合、医療費控除を受けることができます。基本的には10万円、その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得の5パーセントの金額を超えた場合に対象になります。
審美歯科治療の費用も、場合によっては医療費控除の対象になります。医療費控除の対象になるのは、見た目だけではなく機能性の回復も兼ねた治療であるケースです。
例えば、虫歯治療で歯の詰め物(インレー)や被せ物(クラウン)が必要になった場合、保険診療の素材ではなくセラミックを選んでも機能性を取り戻すことが目的に含まれます。こうした場合は、医療費控除の対象になる可能性があります。
一方で、ホワイトニングなどは、医療費控除の対象にはなりません。医療費控除の対象になるかどうか知りたい場合は、治療の際に歯科医師へご確認ください。
まとめ

審美歯科には、ホワイトニングや歯列矯正、セラミック治療などさまざまな治療方法があり、口元の美しさを向上することができる治療が中心になります。そのため、保険が適用されず、治療費は保険診療よりも高額になります。
しかし、場合によっては医療費控除を受けられることもあるため、歯科医師に相談してみましょう。
審美歯科を検討されている方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2025.04.08更新
子どもの歯磨きは何歳からはじめる?歯磨きの仕方と仕上げ磨きのコツも
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

「子どもはいつから歯磨きするの?」「歯磨きの方法は?」「歯ブラシの選び方が知りたい」など、子どもの歯磨きについて悩む保護者の方は多いです。子どもは虫歯になりやすいため、適切に歯磨きする必要があるでしょう。
この記事では、子どもの歯磨きを始める年齢や歯磨きの仕方、仕上げ磨きのコツなどを解説します。
子どもの歯磨きは何歳からはじめる?
子どもの歯磨きは、歯が生え始めたら開始しましょう。個人差はありますが、生後6ヵ月頃に下の前歯2本が生え始めます。
初めは、ガーゼを指に巻きつけ、歯を拭くことから始めます。子ども用の小さなブラシで軽く撫でる程度でもかまいません。この時期に意識すべきなのは、汚れを取り切ることではなく、まずは歯磨きに慣れることです。
1歳半頃には上の前歯2本と上下の切歯、1歳半~2歳頃に奥歯が生え始めます。2歳頃には、上下の乳歯20本が全て生え揃う子どもが多いです。乳歯が生え揃った後は、できれば毎食後に歯磨きをしましょう。
ただし、無理やり歯磨きを行うと、お口を開けるのも嫌がったり、歯ブラシを見るだけで泣いたりする可能性があります。子どもの機嫌に合わせ、できるときに歯磨きをするという意識を持つのがよいでしょう。
子どもの歯磨きの仕方

ここでは、子どもの歯磨きの仕方をご紹介します。
子ども用の歯ブラシを使用する
子どもの歯磨きには、子ども専用の歯ブラシを使用してください。大人用の歯ブラシを使用すると、大きすぎて磨けなかったり、毛先が硬くて痛みを感じたりすることがあります。
年齢に合った歯ブラシを選択
子どもの年齢に合わせて、歯ブラシを選択することが大切です。成長には個人差がありますが、歯ブラシのパッケージに記載されている年齢を参考にすると良いでしょう。子どもの手やお口のサイズに合った、歯ブラシを選択できます。
歯科医師や歯科衛生士に相談し、子どもに合わせて歯ブラシを選んでもらうのも方法の一つです。
毛先が丸い歯ブラシを選択
子どものお口の中は敏感で、歯ブラシの毛先のタイプによっては痛みを感じることがあります。そのため、毛先が丸くなっている歯ブラシを選ぶのがよいでしょう。
特に、子どもは力加減が難しく、力強く磨くと痛みを感じることがあります。毛先の丸い歯ブラシを選んでいれば、歯茎を傷つける心配がありません。
子どもの好きなデザインや色のものを選択
毎日使う歯ブラシを、子ども自身に選んでもらうことも良いでしょう。子どもの好きなデザイン、好きな色の歯ブラシを使って歯磨きすれば、歯磨きのモチベーションを保つことができます。
歯ブラシは細かく動かす
歯磨きをする際は、歯ブラシを細かく動かすことを意識してください。1~2本の歯を磨くように、細かく歯ブラシを動かしましょう。
発泡性の少ない歯磨き粉を選ぶ
泡立ちのよい歯磨き粉を使用すると、すぐにお口の中が泡でいっぱいになり、歯磨きがしにくいです。特に、こどもの場合、泡でお口の中がいっぱいになることで、歯磨きがきちんとできていなくても磨き終わったように感じる可能性があります。
そのため、発泡性の少ないジェルの歯磨き粉を選択しましょう。
永久歯が生え揃うまでは仕上げ磨きを行う
子どもだけで十分に歯磨きするのは難しいため、永久歯が生え揃うまでの間は、仕上げ磨きを行うことが推奨されます。「子どもがある程度大きくなっても、仕上げ磨きをするの?」と思われるかもしれません。
しかし、乳歯だけが生えている時期よりも、乳歯と永久歯が両方生えている時期は磨き残しができやすいです。歯並びが変化し続けるため汚れが溜まりやすい場所が変わったり、永久歯と乳歯の大きさが違ったり、しっかりと磨くのが難しいのです。
毎日お口の中をチェックすることで、虫歯の有無や永久歯の生え変わりに異常がないか確認できるのも、仕上げ磨きを実施するメリットです。
仕上げ磨きをしてあげるときのコツ

仕上げ磨きをするときのコツは、以下の通りです。
1歯につき10~20回磨く
磨き残しは粘着性の頑固な汚れのため、1歯につき10~20回は磨きましょう。1本1本丁寧に歯磨きすることで、虫歯を予防できます。
ただし、強い力で歯磨きすると痛みを感じることがあります。毛先が曲がらない程度の力で歯ブラシを握って、優しく磨いてあげてください。
上唇小帯は避ける
上の前歯と前歯の間には、上唇小帯というヒダがあります。上唇小帯に歯ブラシが当たると、強い痛みを感じやすいです。
そのため、上の前歯を磨く際は、上唇小帯に当たらないように気を付けてください。指で上唇小帯を覆いながら、歯磨きをしてあげると良いでしょう。
虫歯になりやすい箇所を重点的に磨く
奥歯の溝や上の前歯の内側など、子どもが虫歯になりやすい箇所は、重点的に仕上げ磨きしましょう。奥歯は「アー」の口、前歯の外側は「イー」の口にしてもらうと、磨きやすいです。
子どもが歯磨きを嫌がるときの対処法

ここでは、子どもが歯磨きを嫌がる際の対処法について解説します。
日頃から口元に触られることに慣れさせる
歯磨きを嫌がる原因の多くが、お口周りや口内を触られるのが嫌いなことです。日頃から子どものお口周りを触り、口元に触れることに慣れさせるとよいでしょう。
日々続ければ、歯ブラシへの抵抗も少なくなるはずです。
歌を歌いながら磨く
歯磨き中に飽きて嫌がる場合、仕上げ磨きの際に話しかけたり、歌ったりするとよいかもしれません。数え歌や歯磨きの歌を歌えば、歯磨きの終わりが分かるようになります。どれくらいで終わるか理解できれば、歯磨きへのモチベーションを維持しやすいといえます。
鏡の前で歯磨きを行う
子どもの歯磨きが嫌いな理由として、歯磨き中に何をされているかわからないという不安も挙げられます。そのため、大きな鏡の前で歯磨きしたり、お子様に鏡を持ってもらいながら歯磨きをしたり、何をしているのか見せてあげましょう。
不安を解消できれば、歯磨きを嫌がらなくなるかもしれません。
ごほうびシールやスタンプラリー
1回の歯磨きごとに、シートにシールを貼ったり、スタンプを押したりと楽しみを作ってみましょう。毎回の歯磨き後に楽しみがあれば、子どもの歯磨きのモチベーションが高まるはずです。
また「シールが何個たまったら大きな公園に行く」など、子どもの願い事を叶えてあげるシステムを作ってもよいでしょう。お子さまが楽しく歯磨きに取り組めるよう、工夫してあげてください。
難しい場合は寝る前だけでも磨く
歯磨きへの苦手意識が強い場合、こまめな歯磨きが難しい場合があります。「毎食後の歯磨きは絶対!」「無理やりにでも歯磨きをする」など、大人が根を詰めすぎると、逆に子どもは嫌がってしまうかもしれません。歯磨きに対する苦手意識が強まることもあるでしょう。
子どもへの無理やりな歯磨きは、子どもにとっても大人にとっても大きなストレスになってしまいます。そのため、1日1回だけは歯磨きするなど、必要最低限の目標を設定しましょう。
子どもが大きくなるにつれ、いずれ自然と歯磨きはできるようになります。歯磨きへの苦手意識がなくなるまでの間は、こまめな水分補給とうがいで汚れを洗い流してください。
また、歯科医院でお口を開ける練習や歯磨きの練習をするのも有効です。
まとめ

子どもの歯磨きは、歯が生え始めたら開始しましょう。お子様が小さいうちは、無理やり歯磨きせず、まずは歯磨きの習慣を身につけることが大切です。
歯が生え揃ったら、年齢に合わせた歯ブラシを選択し、1本1本丁寧に歯磨きしましょう。小学校に入った後も、永久歯が生え揃うまでの間は仕上げ磨きをしてあげてください。
子どもの歯磨きにお悩みの方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
ARTICLE
SEARCH
ARCHIVE
CATEGORY
- CAD/CAM冠
- IPR
- MTM
- インビザライン
- インビザライン・エクスプレス
- インビザライン・コンプリヘンシブ
- インビザライン・モデラート
- インビザライン・ライト
- インビザライン矯正
- インプラント治療
- オールセラミック
- カウンセリング
- ジルコニア
- ジルコニアセラミック
- セラミック
- セラミック歯
- セラミック治療
- デメリット
- デンタルローン
- ハイブリッドセラミック
- ブラケット
- ブリッジ
- ホワイトニング
- マウスピース
- マウスピース型
- マウスピース矯正
- メタルタトゥー
- メタルボンド
- メリット
- メンテナンス
- ラミネートベニア
- リスク
- ワイヤー
- ワイヤー矯正
- 予防歯科
- 二酸化ジルコニウム
- 人工ダイヤモンド
- 仮歯
- 保定期間
- 保険適用
- 健康保険
- 入れ歯
- 全体矯正
- 出っ歯
- 前歯
- 医療費控除
- 受け口
- 口腔外科
- 噛み合わせ
- 噛み合わせ治療
- 嚙み合わせ
- 外科治療
- 天然歯
- 失敗
- 奥歯
- 定期検診
- 定期診察
- 審美
- 審美性
- 小児歯科
- 抜歯
- 歯ぎしり
- 歯並び
- 歯列矯正
- 歯周病
- 歯周病菌
- 歯型
- 歯科技工士
- 歯科検診
- 歯科矯正
- 歯茎
- 治療期間
- 症例
- 矯正期間
- 矯正歯科
- 矯正装置
- 精密検査
- 自由診療
- 自費診療
- 虫歯
- 虫歯治療
- 虫歯菌
- 被せ物
- 親知らず
- 詰め物
- 費用
- 通院
- 通院頻度
- 部分入れ歯
- 部分矯正
- 金属
- 金属アレルギー
- 銀歯
- 顎関節症
- 食いしばり