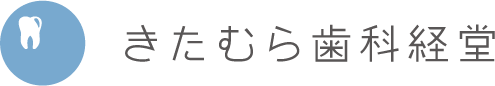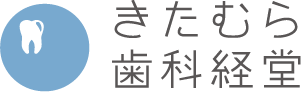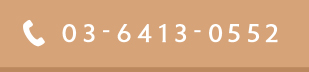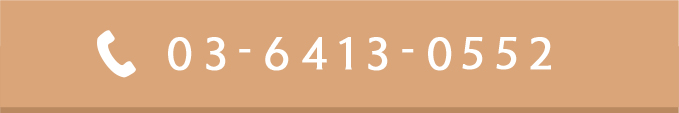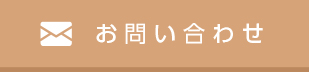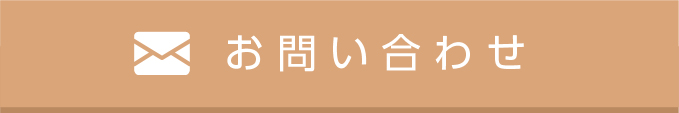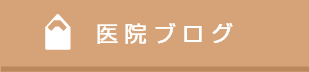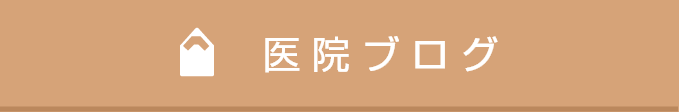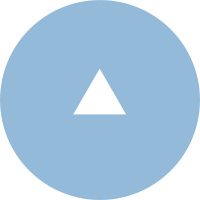2025.04.29更新
入れ歯の寿命はどれくらい?長持ちさせるためのポイントとは
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

入れ歯は、歯を失った際に噛む力や見た目を回復するための大切な治療法です。「入れ歯の寿命はどれくらい持つのだろう?」「ずっと使い続けられるのか不安」と感じている方も多いのではないでしょうか。
入れ歯には耐用年数があり、使い方やメンテナンスの方法によって寿命が大きく左右されます。
この記事では、入れ歯の平均的な寿命や、長く快適に使い続けるために押さえておきたいケアのポイントについて詳しく解説します。
入れ歯の寿命

入れ歯の寿命は、使用する素材や種類によって異なります。一般的には、保険診療の入れ歯で約5年、自費診療の入れ歯で約7〜10年程度が目安とされています。
ただし、これはあくまでも目安であり、使用状況や口腔内の変化によって寿命は前後します。入れ歯は毎日の食事や会話で使われるため、経年劣化や変形、すり減りが生じやすく、時間の経過とともに噛み合わせやフィット感が合わなくなることもあります。
また、顎の骨や歯ぐきの形状が変化することによって、入れ歯自体の調整や作り直しが必要になるケースもあります。快適に長く使うためには、定期的な点検と必要に応じたメンテナンスが不可欠です。
入れ歯の寿命が短くなる原因

入れ歯は毎日使う医療装置であるため、長く快適に使用するためには適切な取り扱いや定期的なケアが欠かせません。
しかし、いくら丁寧に扱っていても、思わぬ原因で寿命が短くなることがあります。ここでは、入れ歯の寿命が縮まる主な原因について解説します。
噛み合わせの変化に気づかず使用を続けた
入れ歯を作製した時点ではぴったりと合っていたとしても、時間の経過とともに口腔内の状態は変化します。歯ぐきや顎の骨は加齢や咀嚼の力によって徐々に痩せていき、それにより入れ歯との適合が悪くなります。
合わない入れ歯を無理に使い続けると、入れ歯本体にかかる負担が偏り、ヒビや破損の原因となることがあります。また、噛み合わせのズレが続くと、口腔内の粘膜や周囲の健康な歯にも悪影響を与える恐れがあります。
過度な咬合力や歯ぎしりの影響
無意識のうちに行われる歯ぎしりや食いしばりは、入れ歯に過度な力を加える原因のひとつです。特に、夜間に強く歯を食いしばる癖がある方は、入れ歯に大きなダメージを与える可能性があります。
強い圧力が長時間加わることで、人工歯が欠けたり、床の部分がたわんで変形するなど、入れ歯の破損リスクが高まります。こうしたケースでは、ナイトガードの併用や、噛み合わせの調整が必要となることがあります。
不適切な清掃や保管による劣化
入れ歯は食べ物のカスや細菌が付着しやすく、毎日の清掃が不可欠です。歯ブラシで強くこすりすぎたり、研磨剤入りの歯磨き粉を使うと、表面に細かい傷がつき、菌の温床になりやすくなります。
また、就寝中に水に浸けずに放置したり、高温のお湯で洗浄するなど、適切でない方法で保管することも劣化の原因となります。入れ歯の素材は繊細で、急激な温度変化や乾燥に弱いため、正しい洗浄と保管方法を守ることが大切です。
不注意による破損や変形
日常生活の中で、入れ歯をうっかり落としてしまうというケースは少なくありません。落下の衝撃で人工歯が外れたり、床が割れることもあり、修理が必要となる場合があります。
また、噛み切る力が強くかかる硬い食べ物を頻繁に食べると、入れ歯が歪んだり摩耗することもあります。特に、部分入れ歯で金属のバネを使っている場合、無理な方向からの力が加わると変形しやすく、装着時の違和感につながります。
定期検診を受けていない
入れ歯は使っているうちに徐々に摩耗し、形状もわずかに変化していきます。その変化を放置すると、知らず知らずのうちに不適合となり、寿命を縮める結果となります。
歯科医院での定期的な検診は、入れ歯の状態を確認するだけでなく、口腔内の健康を維持するためにも欠かせません。異常があった場合には早期に調整や修理を行うことで、大きなトラブルを防ぎ、結果として入れ歯の寿命を延ばせます。
入れ歯を長く使い続けるためのポイント

入れ歯は、歯を失った際の噛む力や発音、見た目を補うために欠かせない医療器具です。
しかし、入れ歯は消耗品であり、永続的に使えるものではありません。だからこそ、できるだけ長く快適に使い続けるためには、日頃の正しい使い方とメンテナンスが重要です。
以下に、入れ歯の寿命を延ばすために押さえておきたいポイントについて詳しく解説します。
毎日の清掃を丁寧に行う
入れ歯は、天然の歯と同様に食事のたびに汚れが付着します。そのままにしておくと、口臭や歯周病、口内炎の原因になり、入れ歯自体も劣化しやすくなります。清掃は1日1回ではなく、毎食後を基本とし丁寧に行うことが理想です。
清掃時には、入れ歯専用のブラシを使用し、やさしい力で磨くことが大切です。歯磨き粉には研磨剤が含まれていることが多く、入れ歯の表面に細かい傷をつける恐れがあるため、使用しないようにしましょう。
汚れをうまく取り除けないときは、入れ歯用の洗浄剤を併用するのも効果的です。
正しい保管方法を守る
入れ歯は乾燥や熱に弱いため、使用していないときの保管方法にも注意が必要です。特に就寝時には、乾燥による変形を防ぐために水に浸けて保管することが基本です。
また、入れ歯を熱湯で洗ったり、高温になる場所に置いたりすることも避けましょう。熱により素材が変形し、フィット感が損なわれる原因になります。
持ち運ぶ際や外出先で外す場合にも、専用のケースを使って清潔かつ安全に保管することが大切です。
入れ歯に過度な負担をかけない
入れ歯の素材は繊細で、強い力や衝撃には弱い一面があります。硬い食べ物を無理に噛もうとしたり、歯ぎしりや食いしばりの癖がある場合、入れ歯に強い負担がかかって破損する可能性があります。
また、部分入れ歯を使っている方は、バネ部分に不自然な力が加わらないよう注意が必要です。破損や変形が生じると、修理が必要になるだけでなく、口腔内に不快感を与える原因にもなります。
違和感を覚えた場合は自己判断で使い続けず、早めに歯科医院で診てもらうようにしましょう。
定期的な歯科検診を受ける
時間の経過とともに使用者の顎の骨や歯ぐきの形が変化し、徐々に入れ歯は合わなくなっていきます。見た目に変化がなくても、少しずつズレが生じているケースは少なくありません。
ズレた入れ歯を使い続けると、口内の粘膜が傷つきやすくなるほか、他の健康な歯にも負担がかかりやすくなります。このような問題を未然に防ぐには、半年から1年に1回の頻度で歯科医院での定期検診を受けることが重要です。
入れ歯の状態だけでなく、口腔内の健康状態や噛み合わせのチェックもあわせて行ってもらうことで、トラブルの早期発見と対応につながります。
装着中の違和感を放置しない
「少し痛いけれど我慢できる」「食べにくいけれど仕方がない」と違和感をそのままにしていると、症状が悪化して口内炎や炎症の原因になることがあります。装着時にズレを感じたり、食事中に違和感があったりする場合は、我慢せず早めに受診しましょう。
違和感がある状態で使用を続けると、入れ歯の変形だけでなく、咬合バランスの崩れや他の歯の損傷にもつながる恐れがあります。定期的な調整を行うことで、入れ歯の機能と快適性を保てます。
夜間の使用について考える
入れ歯は就寝時に外すことが基本ですが、顎の状態や個人の習慣によっては夜間も装着する必要があるケースがあります。
ただし、常に装着していると歯ぐきに休息を与える時間がなくなり、炎症や感染のリスクが高まるため注意が必要です。夜間も使用する場合は、定期的に歯ぐきの状態を確認し、必要に応じて歯科医師の指導を受けましょう。
入れ歯と歯ぐきの間に食べカスが残ったまま放置すると、細菌が繁殖しやすくなるため、毎晩の清掃と朝の装着前の確認が欠かせません。
まとめ

入れ歯の寿命は、一般的に保険診療で約5年、自費診療で7〜10年程度が目安とされています。
しかし、使用状況やメンテナンスの有無によって大きく左右されます。寿命を縮める原因には、噛み合わせの変化や強い咬合力、不適切な清掃・保管、定期検診の不足などが挙げられます。
入れ歯を長く快適に使い続けるには、毎日の丁寧な清掃、正しい保管方法、無理な力をかけないこと、そして定期的な歯科受診が欠かせません。入れ歯を正しく扱い、変化に気づいたら早めに対応することで、寿命を延ばし、口腔内の健康も維持できます。
入れ歯治療を検討されている方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
ARTICLE
SEARCH
ARCHIVE
CATEGORY
- CAD/CAM冠
- IPR
- MTM
- インビザライン
- インビザライン・エクスプレス
- インビザライン・コンプリヘンシブ
- インビザライン・モデラート
- インビザライン・ライト
- インビザライン矯正
- インプラント治療
- オールセラミック
- カウンセリング
- ジルコニア
- ジルコニアセラミック
- セラミック
- セラミック歯
- セラミック治療
- デメリット
- デンタルローン
- ハイブリッドセラミック
- ブラケット
- ブリッジ
- ホワイトニング
- マウスピース
- マウスピース型
- マウスピース矯正
- メタルタトゥー
- メタルボンド
- メリット
- メンテナンス
- ラミネートベニア
- リスク
- ワイヤー
- ワイヤー矯正
- 予防歯科
- 二酸化ジルコニウム
- 人工ダイヤモンド
- 仮歯
- 保定期間
- 保険適用
- 健康保険
- 入れ歯
- 全体矯正
- 出っ歯
- 前歯
- 医療費控除
- 受け口
- 口腔外科
- 噛み合わせ
- 噛み合わせ治療
- 嚙み合わせ
- 外科治療
- 天然歯
- 失敗
- 奥歯
- 定期検診
- 定期診察
- 審美
- 審美性
- 小児歯科
- 抜歯
- 歯ぎしり
- 歯並び
- 歯列矯正
- 歯周病
- 歯周病菌
- 歯型
- 歯科技工士
- 歯科検診
- 歯科矯正
- 歯茎
- 治療期間
- 症例
- 矯正期間
- 矯正歯科
- 矯正装置
- 精密検査
- 自由診療
- 自費診療
- 虫歯
- 虫歯治療
- 虫歯菌
- 被せ物
- 親知らず
- 詰め物
- 費用
- 通院
- 通院頻度
- 部分入れ歯
- 部分矯正
- 金属
- 金属アレルギー
- 銀歯
- 顎関節症
- 食いしばり