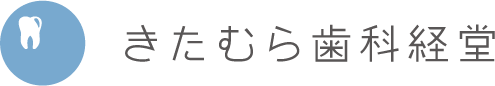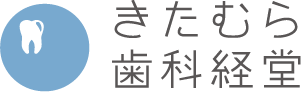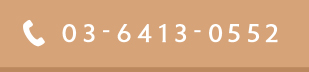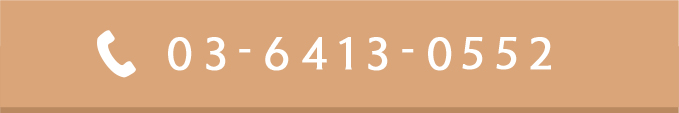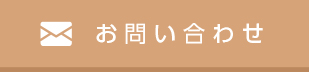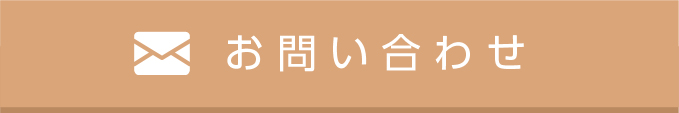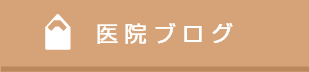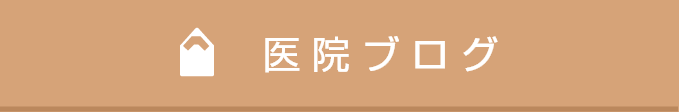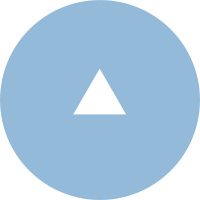2025.03.25更新
マウスピース矯正で抜歯をするケースと、抜歯をするメリット!
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

マウスピース矯正は、装置が目立たず取り外しが可能なことから、近年選ばれる方も多い矯正治療の1つです。抜歯が必要な場合もありますが、できれば抜歯をせずにマウスピース矯正をしたい方も多いのではないでしょうか。
しかし、マウスピース矯正では、抜歯をしたほうが良いケースもあります。
今回は、マウスピース矯正で抜歯をするケースや、抜歯をするメリット・デメリットについて詳しく解説します。
マウスピース矯正で抜歯をするメリット

マウスピース矯正で抜歯をするメリットは、以下の5つです。
- 歯並び噛み合わせを整えられる
- 前歯の突出感を改善できる
- 噛み合わせを改善できる
- 後戻りのリスクを減らせる
- 治療期間を明確にしやすい
それぞれ詳しく解説します。
歯並びや噛み合わせを整えられる
顎のサイズに比べて歯が大きすぎると、歯がキレイに並ばなくなります。このような場合、抜歯をすることで顎に適切なスペースを確保でき、より整った歯並びを目指せます。
前歯の突出感を改善できる
出っ歯や口元の突出が気になる場合、抜歯をして奥に引っ込めるスペースを作ることで、口元をスッキリさせられる場合があります。特に、横顔のEライン(鼻・唇・顎を結んだライン)が整う効果が期待できるため、横顔や笑顔に自信が持てるようになるでしょう。
噛み合わせを改善できる
抜歯によってスペースを作ることで、奥歯の噛み合わせのバランスを整えたり、特定の歯の負担を軽減したりできます。そのため、歯並びだけではなく、上下の歯の噛み合わせも正しく改善できます。正しい噛み合わせは、顎関節の負担軽減や咀嚼の向上につながります。
後戻りのリスクを減らせる
スペースがない場所に無理に歯を並べると、治療後に歯が元の位置に戻ろうとする後戻りのリスクが高まります。抜歯をして十分なスペースを確保すると、歯が安定しやすくなり、矯正治療後の後戻りのリスクを減らせます。
治療期間を明確にしやすい
症例によりますが、抜歯しないで無理に歯を並べる場合、歯の移動に時間がかかることがあります。抜歯することで、歯の動きをシミュレーションしやすく治療計画を立てやすいです。計画通りにスムーズに歯を動かせる可能性も高まるでしょう。
マウスピース矯正で抜歯をするデメリット
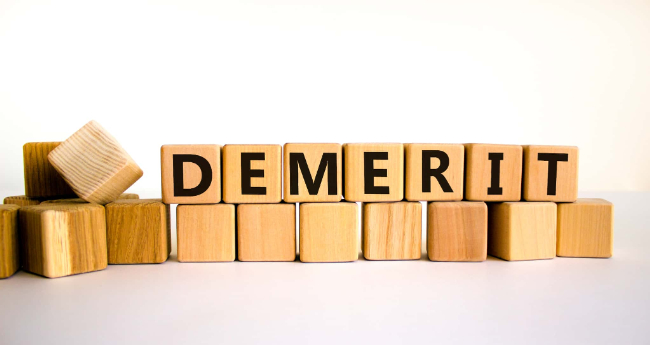
マウスピース矯正で抜歯をするデメリットは、以下の3つです。
- 抜歯後に痛みや腫れが生じる
- 健康な歯を失う場合がある
- 一時的に隙間が生じる
それぞれ詳しく解説します。
抜歯後に痛みや腫れが生じる
抜歯は外科処置のため、処置後は痛みや腫れが生じることがあります。痛みや腫れは一時的なもので徐々に治まるため、心配はいりません。基本的には、処方された痛み止めや腫れ止めの薬を飲んで様子を見れば問題ないでしょう。
しかし、親知らずを抜く場合は、痛みや腫れが数日間続くこともあります。
健康な歯を失う場合がある
マウスピース矯正の抜歯では、健康な歯を抜かなければいけない場合もあります。特に、親知らずではなく小臼歯などを抜く場合は、不安を感じる方も多いです。抜歯する歯が健康な状態であればなおさらでしょう。
健康な歯を失うことに抵抗がある方にとっては、デメリットとなるでしょう。
一時的に隙間が生じる
抜歯をすると、一時的に隙間が生じます。歯並びが整っていく過程で徐々に埋まっていきますが、抜歯箇所が目立つ場所だった場合は、一時的に見た目に影響が出ることもあるでしょう。
マウスピース矯正で抜歯をしたほうがよいケース

マウスピース矯正で抜歯をしたほうがよいケースは、以下の3つです。
- 歯のガタつきが重度のケース
- 上下の歯がズレているケース
- 歯の大きさに対して顎が小さいケース
それぞれ詳しく解説します。
歯のガタつきが重度のケース
叢生(そうせい)と呼ばれる歯並びがガタガタしている状態では、歯を並べるスペースが不足しています。無理に歯を並べようとすると、前歯が外に押し出されたり、噛み合わせが悪くなったりすることがあります。
抜歯をして適切なスペースを確保することで、きれいな歯並びに整えやすくなります。
上下の歯がズレているケース
上の歯が前に出すぎている(上顎前突)または下の歯が前に出ている(反対咬合・受け口)の場合、噛み合わせのバランスが悪いです。抜歯をすることで、前後のバランスを調整ししっかり噛めるようになります。
また、口元がすっきりし、バランスの取れた顔に改善できる可能性が高いです。
歯の大きさに対して顎が小さいケース
歯の大きさに対して顎が小さい場合、無理に歯を並べようとすると、歯列が広がりすぎたり、きれいに歯が並ばなかったりする可能性が高いです。矯正後の後戻りの原因にもなるでしょう。
抜歯して適切なスペースを確保することで、歯並びを安定させられます。
マウスピース矯正で抜歯を必要としないケース

マウスピース矯正で抜歯を必要としないケースは、以下の3つです。
- 軽度の叢生や受け口・出っ歯
- IPRで対応できる
- 顎の成長過程にある子ども
それぞれ詳しく解説します。
軽度の叢生や受け口・出っ歯
軽度のガタつきが気になる程度の叢生や、前歯の傾きを調整するだけで改善できる出っ歯や受け口の場合は、抜歯をせずに治療できる可能性があります。歯を少しずつ動かすだけで歯並びが整う可能性が高いでしょう。
IPRで対応できる
IPRとは、歯のエナメル質を少し削ることでスペースを確保する処置です。ディスキングとも呼ばれるこの処置では、片面0.1~0.25mm程度のごくわずかな量を削るため、歯に悪影響はありません。
IPRの処置で歯を並べるスペースを十分に確保できる場合は、抜歯の必要はありません。
顎の成長過程にある子ども
顎の成長過程にある子どもがマウスピース矯正を行う場合は、抜歯が必要ないケースも多いです。子どもの場合、顎の成長を促しながら顎を拡大させる方法があり、歯を並べるスペースを確保できるためです。
子どもの顎の骨は柔らかく歯も動きやすいため、顎の成長に合わせて柔軟に対応することが可能です。
マウスピース矯正で抜歯をするタイミング

マウスピース矯正で抜歯をするタイミングは、治療計画や歯の動かし方によって異なります。一般的には、マウスピースの作成前、もしくは装着し始めてから行われることが多いです。
マウスピース作成前
マウスピース矯正を始める前に抜歯を終わらせることで、スムーズに歯を移動できるようになります。マウスピースを装着する前にスペースを確保するため、治療計画通りに歯が動きやすくなります。
親知らずの場合も、このタイミングで抜歯することがほとんどで、抜歯後の傷の治癒期間を待ってからマウスピース矯正を開始します。
マウスピースを装着し始めてから
マウスピース矯正を開始してから、矯正治療の進行に合わせて抜歯することもあります。例えば、まず上の歯を抜歯して動かし、その後に下の歯を抜歯するなど、計画的に進めるケースがあります。
一度に複数の歯を抜くと、噛み合わせのバランスが崩れやすいため、歯科医師の判断で段階的に抜歯する場合もあるのです。矯正治療後の抜歯は、歯の動きの経過を見ながら慎重に進められるメリットがあります。
また、ある程度歯並びが整ってきた後に追加でスペースの確保が必要になった場合、治療途中に抜歯を行うケースもあります。
まとめ

マウスピース矯正では、抜歯が必要なケースと必要でないケースがあります。抜歯の必要性は、もともとの歯並びや顎や歯の大きさによっても異なります。
健康な歯の抜歯に抵抗を感じる方も多いですが、抜歯することで理想的な歯並びや適切な噛み合わせに改善できる場合も多いです。抜歯で十分なスペースを確保することで、後戻りのリスクの軽減にもつながります。
マウスピース矯正を検討されている方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2025.03.18更新
虫歯の初期症状とは?見逃しがちなサインと治療法
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

虫歯は、早期に発見すれば進行を防ぐことができますが、初期症状は非常に軽微で見逃されやすいです。どのような症状か現れるのかを知り、早期に受診できるよう努めましょう。
この記事では、虫歯発生のメカニズムや虫歯の初期症状、初期虫歯を治療する方法、虫歯の予防方法について解説します。
虫歯発生のメカニズム

虫歯は、歯の表面にあるエナメル質が酸によって溶かされることで発生します。酸は、食べ物に含まれる糖分が口内の細菌によって分解される過程で作られます。虫歯が発生する具体的なメカニズムは、以下のとおりです。
- 食べ物の摂取
- 細菌の活動
- エナメル質の脱灰
- 再石灰化
- 虫歯の進行
食事を摂って口内に残った糖分を餌に、細菌が酸を作り出します。発生した酸が歯の表面のエナメル質を溶かし、少しずつ歯を侵食していきます。
エナメル質が酸にさらされると、歯の主成分であるカルシウムやリンなどのミネラルが溶け出して歯が弱くなります。この現象を脱灰と呼びます。
通常、唾液中のカルシウムやリンが歯に再度補充されて、歯が修復される再石灰化が起こります。脱灰と再石灰化のバランスが保たれていれば、虫歯が発生することはありません。
しかし、酸の影響が長時間続いて再石灰化が追いつかなった場合、エナメル質が完全に溶けてしまいます。この状態を虫歯と呼びます。
虫歯の初期症状

詳しい初期虫歯の治療法は後述しますが、初期段階で治療できれば大がかりな処置は必要ないケースがほとんどです。そのため、初期症状を理解し、早期に受診することが重要といえます。
ここでは、虫歯になると現れる初期症状をご紹介します。
歯の表面に白い斑点が現れる
エナメル質が酸に溶かされると、歯の表面に白い斑点が現れます。脱灰が進んでいるサインで、虫歯が穴を開ける前の状態といえます。
また、酸によって歯のエナメル質が溶け出した部分に色素が沈着すると、歯に黒い点や線が見られるようになることもあります。白い斑点や黒い点が見られた場合は、早期に歯科医師に相談しましょう。
歯がざらざらし始める
虫歯が進行してエナメル質が少しずつ溶け始めると、歯の表面が滑らかでなくなり、ざらついた質感になります。この状態は歯が弱くなっている証拠で、手で触った時に違和感を覚えることもあるでしょう。
そのまま放置すると、さらに進行して歯に穴が開いていきます。
冷たいものを飲んだときにしみる
虫歯によってエナメル質が薄くなると、冷たいものを摂取したときに歯がしみることがあります。歯の内部にある象牙質が露出してくると、より顕著に現れる症状です。
虫歯が悪化しているサインと言えるので、早めに歯科医院を受診する必要があります。
噛むとわずかに痛みを感じる
虫歯の初期症状として、食べ物を噛んだり歯に圧力がかかったりした際にわずかな痛みが発生することも挙げられます。特に、硬い食べ物を噛んだときや、歯に負担がかかったときに痛みを感じやすいです。
歯茎が少し腫れる
歯の根元に虫歯が発生すると、歯茎が腫れたり赤くなったりすることがあります。腫れが気になる場合は早めに歯科医師に診てもらい、虫歯の進行を食い止めることが大切です。
口臭が気になり始める
虫歯が悪化すると、歯の中で細菌が繁殖し嫌な臭いを発生させることがあります。口臭が強くなったと感じたときは、虫歯が進行している可能性があるでしょう。
虫歯は放置すると進行するので、早期に歯科医院でチェックを受けることが推奨されます。
初期虫歯を治療する方法

お伝えしたとおり、虫歯が進行すればするほど治療が複雑化していきます。大がかりな処置が必要になったり、歯を残せなくなったりすることもあるでしょう。
しかし、初期段階で治療を始められれば、患者さまへの負担を大幅に抑えられます。ここでは、初期虫歯の治療方法を詳しく解説します。
フッ素塗布
初期虫歯の治療方法の一つは、フッ素塗布です。フッ素には、歯のエナメル質を強化し再石灰化を促進する効果があります。ごく初期の虫歯であれば、フッ素塗布とブラッシング方法の見直しで改善できる可能性もあります。
特に、歯科医院で行うフッ素塗布は濃度が高いため効果的です。定期的にフッ素塗布を受ければ、初期虫歯を修復できるでしょう。さらに、虫歯予防にもつながります。
ブラッシング指導
初期虫歯の治療において、正しいブラッシングは非常に重要です。歯科医院でのブラッシング指導では、正しい歯磨きの方法を学びます。歯の表面に残るプラークや食べかすを効果的に除去し、虫歯の原因となる細菌の繁殖を防ぎます。
特に、初期虫歯の場合、適切なブラッシングを行うことで再石灰化を促進し、虫歯の進行を抑えることが期待できます。
PMTC
PMTC(プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング)は、歯科医院で行う専門的なクリーニングです。初期虫歯の治療にも効果的でしょう。
PMTCでは、歯科医師や歯科衛生士が専用の機器を使って、歯の表面に付いたプラークや歯石、着色汚れを丁寧に除去します。専門家による清掃で、歯の表面がきれいになり、細菌の繁殖を防ぐことができます。
また、PMTC後にフッ素塗布を行えば、エナメル質を強化し初期虫歯の進行を防ぐことが期待できます。
虫歯を予防する方法

初期段階で治療すれば、上述した簡単な処置で虫歯の改善が期待できます。
しかし、虫歯は進行性の病気で、歯を削るなどの処置が必要になることも少なくありません。治療すれば進行を止めることはできますが、削った歯質が元の健康な状態に戻ることはありません。
そのため、虫歯は予防することが非常に重要です。ここでは、虫歯を予防する方法について解説します。
適切な歯磨き
毎日の歯磨きは虫歯予防に欠かせません。食後は特に丁寧に磨きましょう。また、歯と歯の間の汚れは歯ブラシだけでは落としきれないため、歯間ブラシやデンタルフロスを使うと、虫歯予防に効果的です。
フッ素入り歯磨き粉の使用
フッ素入り歯磨き粉の使用も、虫歯予防に非常に有効です。フッ素には、歯のエナメル質を強化し再石灰化を促進する作用があります。
特に、虫歯のリスクが高い場合や、歯の再石灰化を助けたい場合に、積極的に取り入れると効果的です。
食後のうがい
飲食後すぐに歯磨きができないときは、うがいが非常に効果的です。うがいは、口内に残った食べかすや酸を洗い流し、虫歯の原因を減らす役割があります。
可能であれば歯磨きをするのが理想ですが、難しい場合はうがいだけでも行いましょう。
こまめに水分を補給する
口内が乾燥していると細菌が繁殖するリスクが高くなるため、こまめに水分を摂ることも重要です。糖分が入っている飲み物の摂取は虫歯の原因となるため、水やお茶などの糖分を含まない飲み物を選択しましょう。
定期的な歯科検診
定期的に歯科医院での検診を受けることで、虫歯の早期発見が可能です。虫歯は進行する前に発見することが大切で、早期に治療すれば大きな問題を避けることができます。
また、歯のクリーニングを受ければ、日々のセルフケアでは落としきれない汚れを取り除くことができます。定期的な歯科検診は、虫歯を効果的に予防するためには欠かせません。
シーラントの使用
シーラントは、歯の溝を樹脂で埋めて食べかすや細菌が溜まりにくくする予防法です。奥歯の噛む面の溝が深い子どもに効果的で、6〜12歳のお子さまであれば保険が適用されることもあります。
飲酒や喫煙を控える
タバコを吸うと血流が悪化するため、口内の免疫力が低下し虫歯や歯周病のリスクが高くなります。また、アルコールも口内の乾燥を引き起こし、虫歯を悪化させる原因になります。
タバコやアルコールの摂取を控えることも、虫歯予防につながります。
まとめ

虫歯の初期症状は、歯の表面に現れる白い斑点や軽い痛みなどが特徴です。これらの兆候を見逃すと、虫歯が進行し歯に穴が開いたり痛みが強くなったりすることがあります。
日々の適切な口腔ケアと定期的な歯科検診を受けることで虫歯の進行を防ぎ、健康な歯を維持しましょう。
虫歯の治療を検討されている方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2025.03.11更新
歯のクリーニングはどれくらいの頻度で受けるべき?メリットと注意点も
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

虫歯や歯周病などを予防するためには、定期的に歯のクリーニングを受けることが重要です。
しかし、どのくらいの頻度で通えばよいか分からないとお悩みの方は少なくありません。歯のクリーニングの頻度は、お口の状態や生活習慣によって異なります。
この記事では、適切な歯のクリーニングの頻度やメリット、注意点について解説します。
歯のクリーニングを受ける頻度

口内環境や生活習慣によって歯垢や歯石が溜まるスピードが異なるため、歯のクリーニングの頻度については個人差があります。ここでは、一般的な歯のクリーニングを受ける頻度について解説します。
セルフケアが適切な方
セルフケアによる磨き残しが少ない方の場合、虫歯や歯周病のリスクは少ないといえます。例えば、フロスや歯間ブラシも使用している方が挙げられるでしょう。他にも、以下の特徴がある方が挙げられます。
- 歯磨きが上手な方
- 歯並びがよい方
- 毎食後に歯磨きしている方
- フロスや歯間ブラシも使用している方
日々の歯磨きだけでも口内の汚れをしっかり落とせているため、歯のクリーニングは約3~6ヵ月に1回の頻度でかまいません。
歯磨きが苦手な方・歯並びが悪い方
歯磨きが上手にできていない方や歯磨きの頻度が低い方の場合、磨き残しができやすいです。また、歯と歯の重なりが多い方、反対に歯と歯の間に隙間が空いている方の場合、きちんと歯磨きをしていても汚れが溜まることがあります。
- 歯磨きが苦手
- 歯磨きの回数が少ない方
- 歯並びが悪い方
上記のような方の場合、虫歯や歯周病のリスクが高くなるため、約1~2ヵ月の頻度で歯のクリーニングを受けましょう。定期的な歯のクリーニングにより、虫歯や歯周病のリスクを下げ、口臭の予防にもつながります。
歯周病の方
歯周病がある方も、より頻繁にクリーニングを受けるべきでしょう。
- 歯茎から出血しやすい方
- 歯周病と診断された方
- 歯周病が進行している方
上記の方の場合は、約1~2ヵ月に1回の通院が必要といえます。歯茎から出血する原因は、磨き残しがあり、歯茎が炎症を起こしているからです。放置すると慢性的な歯肉炎になり、いずれは歯周病を発症します。
虫歯になりやすい方
きちんと歯磨きをしていても、口内環境や食生活によって虫歯のリスクは変動します。特に、食生活が乱れている方や口内が乾燥しやすい方の場合、虫歯リスクが高いので注意が必要です。
また、虫歯治療を受けた回数が多い方も、詰め物や被せ物の隙間から虫歯になることがあります。
- 甘いものを好んでよく食べる方
- 間食が多い方
- 口呼吸の方
- 唾液の量が少ない方
- 虫歯治療を受けた回数が多い方
上記に当てはまる方は、約1~2ヵ月に1回のクリーニングが適切でしょう。定期的に歯科に通院すれば虫歯の有無をチェックしてもらえるため、虫歯を未然に防ぐ効果があります。
歯石が付きやすい方
歯石の付きやすい方の場合、約1~2ヵ月に一度の頻度で歯のクリーニングを受けると良いでしょう。歯石の付きやすさは、食生活や口内環境によって左右されます。
- 甘いものを好んでよく食べる方
- 間食が多い方
- 口呼吸の方
- 唾液の少ない方
上記のような方は、定期的に歯科医院でクリーニングを受けて、口内環境を整える必要があります。
飲食物に含まれる糖分を多く摂取すると、細菌が繁殖し、歯垢の生成が促されます。また、唾液の分泌量が少なければ、汚れが洗い流されません。溜まった歯垢は歯石に変化し、歯ブラシでは取れない汚れへと変化します。
着色が付きやすい方
着色が付きやすい方や着色が気になる方は、約2~3ヵ月に1回のクリーニングが推奨されます。
ただし、審美目的の着色除去の場合、保険が適用されないことがあるため注意が必要です。
喫煙習慣のある方
喫煙習慣のある方は、約1~2ヵ月に一度の頻度で歯のクリーニングを受けると良いでしょう。喫煙習慣がある方は、歯周病の発症リスクが高く、かかった場合は進行しやすいです。また、歯石や着色汚れも付着しやすいので、頻繁にクリーニングを受けるべきです。
歯のクリーニングで行うことと流れ

ここでは、一般的な歯のクリーニングの内容と流れを解説します。
検査
まず、お口の状態を把握するために検査を行います。検査の内容は、レントゲン撮影や歯科医師による視診、歯周病検査などです。歯周病検査では、歯周ポケットの深さ、出血や歯の揺れの有無を確認します。
これらの検査を行うことで、歯周病の進行具合や磨き残しの有無、歯石の付き具合を把握でき、患者様に合った治療内容を定められます。
歯磨き指導
検査で磨き残しをチェックした後は、歯磨き指導を行います。歯ブラシの持ち方や当て方、フロスや歯間ブラシの使用方法について、詳しくアドバイスします。
スケーリング
歯垢はやわらかい汚れのため、歯磨きで取り除くことが可能です。
しかし、歯垢は数日経つと歯石へと変化し、歯ブラシでは取り除けなくなります。そのため、超音波を使用した機械やハンドスケーラーという専用の器具を使用して、除去しなければなりません。
フロッシング
フロッシングとは、フロスや歯間ブラシを使用し、歯と歯の間の汚れを取り除くことです。これらの器具を歯と歯の間に通して、歯石の取り残しがないか確認する目的もあります。
ポリッシング
歯の汚れを取り除いた後は、ポリッシングを行います。ポリッシングとは、専用のペーストを使用し、歯の表面を仕上げ磨きすることです。
歯の表面をツルツルに仕上げることで、着色汚れを除去するだけでなく、新たな歯の汚れを付きにくくする効果があります。
フッ素塗布
歯のクリーニングが終わった後は、全体にフッ素塗布を行います。フッ素には、歯の質を強くし細菌の働きを弱める効果があります。
定期的にフッ素塗布を行うことで、虫歯や歯周病を予防できるのがメリットです。
歯のクリーニングを受けるメリット

歯のクリーニングを受けるメリットは、以下の3点です。
口腔トラブルの予防
口内の汚れをすみずみまで除去することで、虫歯や歯周病を予防できます。また、たとえ虫歯になっていたとしても、早期発見・早期治療に繋げられるでしょう。
着色除去・予防
丁寧に歯磨きをしている方でも、日々の食事により着色が付くことがあります。
しかし、普段の歯磨きでは、なかなか着色汚れは取り除けません。定期的な歯のクリーニングにより、本来持っている歯の白さやツヤを取り戻せます。
口臭改善・予防
歯垢・歯石を除去することで、口臭の改善に効果があります。また、虫歯や歯周病の進行も、口臭の原因の1つです。
歯科治療とクリーニングを併用することで、口内の細菌の繁殖を予防します。虫歯や歯周病だけでなく、口臭の予防に効果があるといえます。
歯のクリーニングを受ける際の注意点

歯のクリーニングを受ける際の注意点は、以下の2点です。
出血や痛み
歯垢や歯石が付いている場合、歯茎の炎症により、クリーニングの際に出血する場合があります。また、歯石が多くついている場合、痛みが出たりクリーニング後に知覚過敏のような症状が出たりする場合があるので注意が必要です。
ただし、歯茎の炎症が治まれば、出血や痛みは自然と治まります。多くの場合、クリーニング当日、長くても2~3日程度で症状は落ち着いてきます。
色の濃い飲食物は避ける
クリーニングを受けた後の歯は、外部からの刺激を受けやすい状態です。着色が付きやすいため、色の濃い飲食物は避けましょう。
具体的には、カレーや赤ワイン、コーヒーなどです。また、熱いもの・冷たいものを摂ると、歯がしみる場合もあります。そのため、クリーニング当日は刺激のあるものも控えてください。
まとめ

セルフケアがきちんとできている方の場合、歯のクリーニングは約3~6ヵ月に1回でかまいません。歯磨きが苦手な方や歯石が付きやすい方の場合、虫歯や歯周病のリスクが高いため、約1~2ヵ月に1回と頻繁に通う必要があります。
歯石を放置すると、虫歯や歯周病を発症し歯の寿命を縮めるかもしれません。また、口臭の発生や着色により、人に不潔な印象を与えることもあります。
お口の健康を維持するためには、ご自身に合った歯のクリーニングの頻度を知っておくことが大切です。
歯のクリーニングの頻度や内容について詳しく知りたい方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2025.03.04更新
奥歯をインプラントにするメリットと費用!治療が難しいといわれる理由も
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

奥歯が抜けてしまうと、噛み合わせが乱れてほかの歯に負担がかかるなど、想像以上に大きな影響を受けることがあります。その抜けた奥歯の代わりに再び噛む力を取り戻せるのがインプラント治療です。
しかし「奥歯をインプラントにするのは難しいの?」「インプラントは奥歯の役割を果たせるの?」など、不安に思っている方もいるのではないでしょうか。
今回は、奥歯の役割やインプラントにするメリット、難しいといわれる理由について詳しく解説します。失った奥歯を補う治療法としてインプラントを検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
奥歯の役割

奥歯とは、糸切り歯(犬歯)よりも奥にある臼歯(きゅうし)のことです。親知らずを除くと上下8本ずつ、合計16本の奥歯があります。犬歯の隣にある歯が小臼歯で、その奥側にある大きな歯を大臼歯と呼びます。
形状が臼に似ていることから臼歯と呼ばれ、日々の食生活や健康の維持に欠かせない存在です。食べ物を噛んで細かくしたり、すりつぶしたりする役割があり、しっかり噛み、食べ物を細かくすることで胃腸での消化を助けます。
咀嚼以外に口腔内のバランスの維持も奥歯の大きな役割といえるでしょう。奥歯が抜けると、噛み合わせが悪くなり、バランスが崩れて顔の輪郭に変化が生じる可能性があるのです。
ただし、奥歯は前歯と比較すると歯磨きがしにくく、むし歯になりやすい傾向があります。また、硬い食べ物を噛んで強い力がかかると、欠けたり折れたりすることがあるので注意しなければなりません。
奥歯をインプラントにするのは難しい?

奥歯のインプラント治療が難しいといわれるのには、以下のような理由があります。
噛み合わせの調整がしにくい
奥歯には噛んだときに強い力が加わります。患者さんの体重以上の力がかかるため、インプラントにすることで破損するリスクがあるのです。また、噛み合わせをしっかり調整できていないと、顎に負担がかかって顎関節の痛みや頭痛につながることもあるでしょう。
下歯槽神経を傷つけるリスクがある
下顎にインプラントを入れる際、下歯槽神経を傷つけないように注意しなければなりません。下歯槽神経は下の歯の歯根近くにあり、レントゲン写真やCTを使用して場所を正しく把握する必要があります。
そのため、下顎の奥歯をインプラントにする場合、ほかの箇所よりも治療の難易度が高くなるケースがあるのです。
手術の際に器具を入れにくい
口の中は奥になればなるほど狭くなります。インプラント体を埋入するときには、口腔内に器具を入れなければなりませんが、スペースが狭いと治療に使用する器具が入らないことがあるのです。これも奥歯の治療が難しい理由の一つです。
患者様に口を大きく開けてもらわないと治療ができないため、開口を補助する器具を使用しますが、顎や筋肉に負担がかかってしまいます。顎関節症の方など、口を大きく開け続けるのが難しいと、インプラント治療を受けるのが難しい場合があるでしょう。
奥歯をインプラントにするメリット

難しいといわれる奥歯のインプラント治療ですが、得られるメリットもたくさんあります。主なメリットは、以下のとおりです。
周囲の歯に負担がかからない
ブリッジの場合は、支えとする健康な歯を削る必要があります。
一方、インプラント治療では、歯槽骨に人工歯根を埋め込むので、周囲の歯に負担がかかりません。健康な歯に負担がかからない点は、インプラント治療のメリットといえるでしょう。
噛む力を取り戻せる
インプラント治療では、人工歯根と顎の骨を結合させるため、入れ歯やブリッジよりもしっかりと食べ物を咀嚼できます。ご自身の歯のように硬い食べ物でもしっかり咀嚼できるようになるため、食事を楽しめるでしょう。
これによって、胃腸への負担を軽減できます。食べ物を十分に咀嚼できれば、消化吸収しやすくなり、全身の健康維持にも大きく貢献します。
噛み合わせを改善できる
奥歯を失ったまま放置すると、噛み合わせが崩れて、ほかの歯に負担がかかることがあります。
しかし、失った奥歯部分にインプラントを埋入することで、噛み合わせが大きく改善します。また、定期的にメンテナンスを受けることで噛み合わせの問題はほぼ避けられるでしょう。
天然歯のような見た目を再現できる
天然歯のような美しい見た目を再現できる点も奥歯をインプラントにするメリットです。保険が適用される部分入れ歯の場合、口をあけたときに歯に引っ掛ける金属のバネが見えることがあります。
一方でインプラントは、人工歯根を顎の骨に埋め込み、その上に人工歯を取り付けることから、金属部分が目立ちにくいです。また、人工歯の部分にはオールセラミックやジルコニアなどの審美性の高い素材を使用するため、天然の歯のような見た目を再現できるのです。
発音に影響が出にくい
入れ歯の場合、ズレたり床部分に厚みがあったりすると、発音しにくいと感じることがあります。
一方でインプラントは、顎の骨にしっかり固定されるためズレることがありません。発音に影響が出ることがないため、人前で話す機会の多い営業や接客業の方に選ばれる傾向があります。
奥歯をインプラントにするデメリット
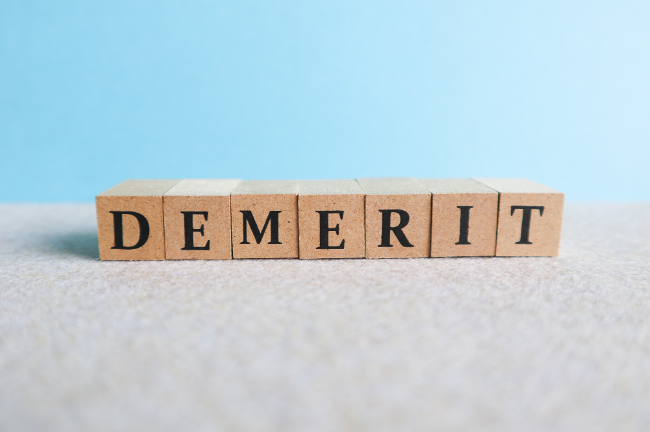
数多くのメリットがあるインプラント治療ですが、デメリットも存在します。インプラント治療を検討している場合は、メリットだけでなくデメリットもしっかり把握しておきましょう。
保険適用外のため治療費が高額になる
インプラント治療は保険適用外です。そのため、高額な費用がかかります。奥歯をインプラントにする場合にかかる費用は、1本あたり30万〜50万円ほどです。1本だけでなく複数の歯をインプラントにすると、さらに高額な治療費がかかります。
骨造成が必要となるケースがある
インプラント治療では、人工歯根と顎の骨をしっかり結合させなければなりません。そのため、顎の骨に高さや厚みが足りない場合、骨造成が必要になるケースがあります。骨造成を行う場合、通常よりも治療期間が長くなり、費用もかかります。
治療期間が長い
治療期間が長いのもインプラント治療のデメリットといえます。インプラントの治療期間は3か月〜1年ほどです。インプラントの治療期間が長い理由は、精密な事前診断が必要であるため、また顎の骨と人工歯根が結合するのを待つ必要があるためです。
なるべく早く治療を終わらせたい方や忙しくて通院する時間がない方にとって、治療期間が長い点はデメリットといえるでしょう。
奥歯をインプラントにする場合にかかる費用

インプラント治療は、自由診療のため費用が高額になりやすいです。インプラント治療を行う部位や骨の状態によって費用は異なりますが、1本あたり30万〜50万円が相場となり、本数が増えると治療費もアップします。
また、自由診療の場合、歯科医院によって費用が異なるため、予算オーバーで後悔しないためにも、事前に歯科医院で確認しましょう。
まとめ

奥歯のインプラント治療は、精密な事前診断と高度な技術を求められることから難易度が高いといわれています。
しかし、周囲の歯に負担をかけずに奥歯の機能を回復させられる、天然歯に近い見た目を再現できるなど、様々なメリットがあります。
奥歯はしっかり噛んで食事をするために欠かせない重要な存在です。奥歯を失ったまま放置すると、噛み合わせが悪くなったり、顔の輪郭に変化が生じたりする可能性があります。そのため、歯を補う治療を受けることが大切なのです。
奥歯をインプラントにすることにはメリットとデメリットがあります。どちらもよく理解し、歯科医師に相談のうえ、ご自身に合った治療法を選択しましょう。
インプラント治療を検討されている方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
ARTICLE
SEARCH
ARCHIVE
CATEGORY
- CAD/CAM冠
- IPR
- MTM
- インビザライン
- インビザライン・エクスプレス
- インビザライン・コンプリヘンシブ
- インビザライン・モデラート
- インビザライン・ライト
- インビザライン矯正
- インプラント治療
- オールセラミック
- カウンセリング
- ジルコニア
- ジルコニアセラミック
- セラミック
- セラミック歯
- セラミック治療
- デメリット
- デンタルローン
- ハイブリッドセラミック
- ブラケット
- ブリッジ
- ホワイトニング
- マウスピース
- マウスピース型
- マウスピース矯正
- メタルタトゥー
- メタルボンド
- メリット
- メンテナンス
- ラミネートベニア
- リスク
- ワイヤー
- ワイヤー矯正
- 予防歯科
- 二酸化ジルコニウム
- 人工ダイヤモンド
- 仮歯
- 保定期間
- 保険適用
- 健康保険
- 入れ歯
- 全体矯正
- 出っ歯
- 前歯
- 医療費控除
- 受け口
- 口腔外科
- 噛み合わせ
- 噛み合わせ治療
- 嚙み合わせ
- 外科治療
- 天然歯
- 失敗
- 奥歯
- 定期検診
- 定期診察
- 審美
- 審美性
- 小児歯科
- 抜歯
- 歯ぎしり
- 歯並び
- 歯列矯正
- 歯周病
- 歯周病菌
- 歯型
- 歯科技工士
- 歯科検診
- 歯科矯正
- 歯茎
- 治療期間
- 症例
- 矯正期間
- 矯正歯科
- 矯正装置
- 精密検査
- 自由診療
- 自費診療
- 虫歯
- 虫歯治療
- 虫歯菌
- 被せ物
- 親知らず
- 詰め物
- 費用
- 通院
- 通院頻度
- 部分入れ歯
- 部分矯正
- 金属
- 金属アレルギー
- 銀歯
- 顎関節症
- 食いしばり