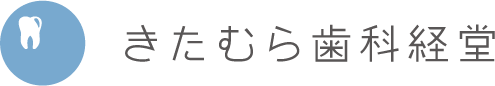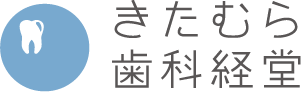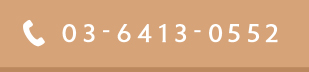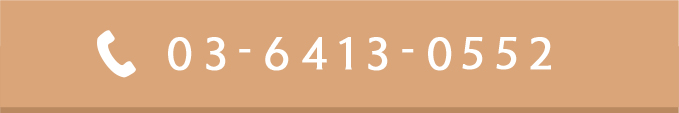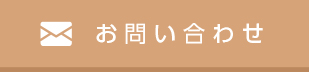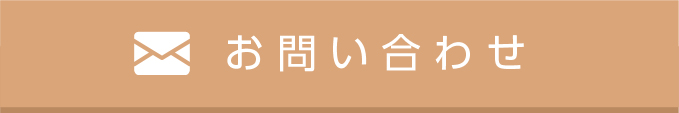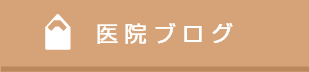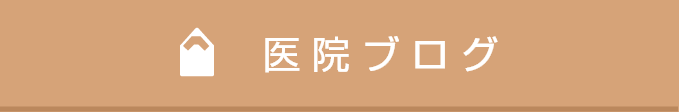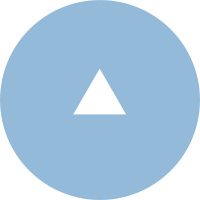2025.08.23更新
治療してもすぐ虫歯になるのはどうして?再発を防ぐためにできることも
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。
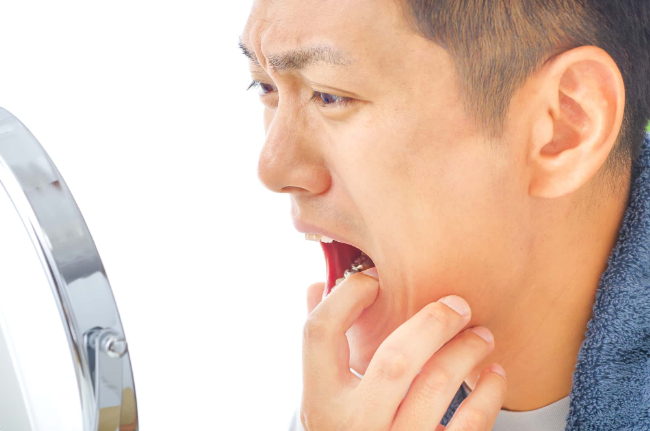
「この前虫歯を治療したばかりなのに、またできてしまった」「毎日歯磨きをしているのになぜか繰り返し虫歯ができる」とお悩みの方がいらっしゃるのではないでしょうか。
一度治療した歯が再び虫歯になることを二次カリエスといいます。実は、一度虫歯を削って治療した箇所は歯質が脆くなるため虫歯になりやすいのです。
とはいえ、何度も治療が必要になれば、通院や費用の負担も増えるため、できるだけ避けたいと考える方も多いでしょう。
そこで今回は、治療してもすぐ虫歯が発生する理由や再発しやすい部位、虫歯を繰り返さないためにできることなどについて解説します。
治療してもすぐ虫歯になるのはどうして?

治療を受けたにもかかわらず、再び虫歯が発生するのはなぜなのでしょうか。ここでは、治療してもすぐ虫歯が発生する理由についてみていきましょう。
治療した歯は脆くなるため
通常、私たちの歯はエナメル質という硬い組織で覆われていますが、虫歯を大きく削ると、内部の象牙質が露出することがあります。象牙質はとても柔らかいため、虫歯が進行しやすいです。虫歯の治療では、露出した象牙質を覆うために詰め物や被せ物を施します。
しかし、詰め物や被せ物を施しても、わずかなすき間や段差が生じて細菌が内部に侵入すれば、再び虫歯が発生するリスクが高まるのです。
適切なブラッシングができていないため
歯をしっかりと磨いているつもりでも、汚れやプラークが除去できていなければ、当然虫歯が発生しやすくなります。虫歯を繰り返す場合には、知らず知らずのうちに歯磨きの癖ができており、磨き残しやすい箇所が発生している可能性があるでしょう。
また、セルフケアの際に歯間ブラシやデンタルフロスなどを使用していない場合、歯間に蓄積したプラークが除去できず、二次カリエスが発生しやすくなります。
甘いものや酸っぱいものを好んで食べているため
せっかく虫歯を治療しても、治療前の食生活を続けていれば、二次カリエスを起こしやすくなります。虫歯菌は、食事に含まれる糖分をエサとして増殖します。そのため、普段から甘いものを頻繁に食べている人は、そうでない人に比べて虫歯のリスクが高くなります。
また、酸っぱいものを頻繁に食べている場合も、口腔内が酸性に傾き、歯が溶かされやすくなります。
ダラダラ食べをしているため
口腔内は、1日のうちに中性になったり酸性になったりを繰り返しています。食事をしたあとは虫歯菌が酸を放出し、口腔内が酸性に傾きますが、歯磨きをすることや唾液が作用することによって中性に保たれるのです。
しかし、ダラダラ食べを続けていると口腔内が中性に戻ることなく、酸性に傾いたままの状態になります。その結果、歯が溶かされて虫歯が発生しやすくなるのです。
口腔内が乾燥しているため
唾液には、口腔内の食べカスや汚れを洗い流し、細菌の活動を抑制する働きがあります。
しかし、加齢やストレス、口呼吸などが原因で唾液の分泌量が減少すると、虫歯が発生しやすく、進行も早くなります。
歯並びが乱れているため
歯並びが悪いと、歯と歯が重なり合ったり凸凹したりして、歯ブラシが行き届きにくくなります。その結果、磨き残しが増えると、虫歯を繰り返すリスクが高くなるでしょう。
虫歯が再発しやすい部位

虫歯が再発しやすい部位は、以下の通りです。
詰め物や被せ物の周辺
虫歯治療の際に装着した詰め物や被せ物には、経年劣化によってすき間や段差ができることがあります。そのようなすき間や段差にはプラークが蓄積しやすくなるため、虫歯が再発するリスクが高まります。
歯と歯の間
歯と歯の間も虫歯が再発しやすい部位のひとつです。歯間に付着した汚れは歯ブラシだけでは取り除くことが難しく、磨き残しが増えると細菌が繁殖して虫歯が再発する可能性があります。
歯の根元
歯の表面はきれいに磨けていても、歯の根元(歯と歯茎との境目)に磨き残しがあるケースも多いです。歯の根元はプラークが蓄積しやすいことに加え、歯根部分はエナメル質で覆われていないため、虫歯菌のダメージを受けやすい状態になります。
奥歯の溝やすき間
奥歯の溝は複雑な形状をしており、磨き残しが多くなりがちです。また、奥歯は噛み合わせることによって強い力がかかるため、詰め物や被せ物が劣化し、すき間やヒビ割れなどが生じやすくなります。その結果、内部に虫歯菌が侵入し、二次カリエスを引き起こすリスクも高くなります。
虫歯を繰り返さないためにできること

毎日の生活を意識的に改善することで虫歯を予防することも可能です。虫歯を繰り返さないためにできることには、以下のようなものがあります。
食生活を改善する
先にも述べた通り、糖分の多いものや酸っぱいものを頻繁に口にすると、虫歯になるリスクが高まります。再発のリスクを軽減するためにも、食生活を見直したほうがよいでしょう。また、ダラダラ食べをやめて、1日3食しっかりと食べることが大切です。
なお、水分補給には甘い飲みものではなく、水や無糖の飲み物を選ぶとよいでしょう。
適切な方法でセルフケアを行う
虫歯の再発を防ぐためには、適切な方法でセルフケアを行うことが重要です。忙しくて毎食後に歯磨きができない方もいらっしゃるかもしれませんが、少なくとも朝晩の2回は丁寧にセルフケアを行うことを心がけましょう。
特に、詰め物や被せ物の周辺、歯と歯の間、歯の根元、奥歯の溝などは、丁寧に磨くことが重要です。歯と歯の間の清掃には、デンタルフロスや歯間ブラシを使用しましょう。
フッ素を活用する
フッ素には、細菌の増殖を抑えたり歯質を強化したりする効果があります。また、エナメル質の表面がわずかに溶かされた状態であれば、フッ素を塗布することで修復が見込めます。
フッ素を含むケア用品は市販でも多く販売されていますので、ご自身が使用しやすいものを取り入れるとよいでしょう。なお、歯科医院であれば、市販のものよりも高濃度のフッ素塗布が受けられますので、より高い予防効果が期待できます。
口の中の乾燥を予防する
先にも述べた通り、唾液の量が少なく口の中が乾燥していると、虫歯のリスクが高まります。二次カリエスを予防するためにも唾液の分泌量を増やし、乾燥を防ぐことが大切です。
唾液の分泌を促進する具体的な方法としては、よく噛んで食べる・キシリトールガムや無糖のガムを噛む・こまめに水を飲むなどが挙げられます。そのほかにも、口呼吸を改善したり口腔保湿剤を使用したりするのも有効な方法といえるでしょう。
ストレスや疲れを溜めない
緊張しているときに口が乾いた経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、ストレスにさらされると唾液がネバついた性状に変化し、口腔内が乾燥しやすくなるといわれています。また、虫歯や歯周病は細菌感染によって引き起こされるものですので、ストレスや疲れが溜まって身体の抵抗力が下がっていると発症しやすくなるのです。
そのため、普段からストレスや疲れを溜め込まないように意識したり栄養バランスのよい食事、十分な休息などを心がけたりすることも大切です。
歯列矯正を受ける
歯並びが乱れていると清掃性が悪くなるため、どうしても虫歯のリスクが高まります。そのため、歯列矯正を受けて歯並びを整えることも虫歯の予防につながります。
定期的に歯科医院を受診する
毎日のセルフケアを丁寧に行っていても磨き残しは発生するものです。そのため、3ヵ月に1回程度は定期的に歯科医院でチェックを受けることが望ましいでしょう。
定期的な歯科検診では、歯のクリーニングやブラッシング指導、詰め物や被せ物のチェックなどが受けられます。定期的に歯科医院を受診することは虫歯の予防はもちろん、トラブルの早期発見・早期治療にもつながるでしょう。
まとめ

一度虫歯を治療した箇所は歯質が弱くなるため、二次カリエスを発症しやすくなります。また、何度も虫歯を繰り返す場合には、食生活や口腔環境、セルフケアの方法などに問題がある可能性もあるでしょう。
普段の生活のなかで虫歯の再発予防に役立つ方法もありますので、ぜひ本記事を参考にしてみてください。「正しいブラッシング方法が知りたい」「歯並びについて相談したい」という方も、歯科医院へご相談ください。
虫歯にお悩みの方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2025.07.22更新
歯を失う原因とリスク!歯を守るために知っておきたいこと
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

いつまでも自分の歯で食事を楽しみたいと願っている方は多いです。
しかし、実際には、年齢を問わず多くの人が何らかの理由で歯を失っています。歯を1本失うだけでも、噛み合わせが悪くなったり発音に支障をきたしたり、見た目の印象が変わったり、さまざまな影響が出ます。
この記事では、歯を失う原因について詳しく解説し、それに伴うリスクや歯を守るために日頃から意識すべきポイントについても紹介します。
歯を失う原因とは

歯を失う原因は一つではなく、複数の要素が絡み合っていることがほとんどです。年齢や生活習慣、セルフケアの状態などによってそのリスクの高さも大きく異なります。
ここでは、代表的な原因を取り上げ、それぞれがどのように歯の喪失につながるのかを詳しく見ていきましょう。
歯周病
歯を失う原因として、最も多いのが歯周病です。日本人の成人の約8割が歯周病にかかっているとも言われており、非常に身近な疾患です。
歯周病は、歯と歯ぐきの間に細菌が侵入し、歯ぐきの炎症や歯槽骨(歯を支える骨)の破壊を引き起こす病気です。進行すると歯がグラグラと動くようになり、最終的には抜け落ちることもあります。
特に、初期段階では自覚症状が少ないため、気づかないうちに進行することが珍しくありません。歯ぐきからの出血や口臭、歯が浮いたような感覚などが現れたときには、すでに中等度以上の状態といえます。
虫歯
虫歯もまた、歯を失う大きな原因の一つです。虫歯が進行すると歯質が大きく失われ、神経が侵されて痛みが出たり根の先に膿がたまったりします。重度になると抜歯が避けられないケースもあります。
特に注意が必要なのは、神経を取った歯です。痛みがなくなるため問題が起こっても気づきにくく、脆くなっているため破折のリスクが高まり、最終的に抜歯に至ることも多いのです。
また、一度治療を受けた歯も再度虫歯になるリスクがあるため、油断は禁物です。治療後も定期的なチェックや予防処置は欠かせません。
歯の破折(割れ・ひび)
歯が割れたりひびが入ったりすることで抜歯が必要になるケースもあります。特に、歯ぎしりや食いしばりの癖がある方や過去に歯の神経を取った方は要注意です。神経を失った歯は内部がもろくなっており、日常的な咀嚼でも破折するリスクがあります。
一見小さな亀裂に見えても、内部で大きなダメージを受けていることがあります。破折の位置が歯根の深い部分にまで及んでいる場合、修復は困難で、抜歯が避けられないことも少なくありません。
外傷
スポーツでの接触や転倒、事故など、強い衝撃によって歯が抜け落ちるケースもあります。特に、前歯は外部からの衝撃を受けやすく、外傷による脱落リスクが高いです。年齢に関係なく起こりうるため、子どもから高齢者まで注意が必要です。
スポーツをする際にはマウスガードの着用を心がけ、転倒リスクの高い環境では周囲への注意も大切です。
噛み合わせの悪さや無意識の癖
噛み合わせのバランスが悪いと、一部の歯に過度な力がかかり、歯や歯周組織に負担をかけます。これが長期にわたって続くと、歯の動揺や歯周病の悪化、さらには歯の破折を招くこともあります。
また、歯ぎしりや頬杖、偏った咀嚼など、無意識の癖も影響します。これらの習慣が積み重なることで、歯へのダメージは徐々に蓄積されていきます。自分では気づきにくいため、歯科医院での定期的なチェックと専門的なアドバイスを受けることが重要です。
歯を失うリスク

歯を失うリスクは、見た目が悪くなることだけではありません。口腔機能を低下させたり、生活の質(QOL)や全身の健康に影響を及ぼしたりするリスクもあります。ここでは、歯を失った場合に起こり得る主なリスクについて解説します。
咀嚼機能の低下
歯を失うと咀嚼機能が低下し、食べ物をしっかり噛むことが難しくなります。そうすると避けるようになる食材が増え、栄養バランスが崩れる原因となります。特に硬めの食材を敬遠するようになりやすく、たんぱく質やビタミン、ミネラルの摂取不足に陥るリスクが高まります。
このような状態が続くと、筋力の低下や免疫力の低下を引き起こしかねません。歯を失うことは、全身の健康を損なう引き金にもなるのです。
発音や表情への影響
前歯を中心に歯を失うと、発音に支障をきたすことがあります。特にサ行やタ行、ラ行などは、歯と舌の接触によって発音が決まるため、歯がないと不明瞭な発音になることがあります。人との会話や仕事に影響を及ぼし、心理的なストレスにもつながりやすくなります。
また、歯は顔全体の骨格を支える役割も担っています。奥歯を失うと、頬がこけて老けた印象になったり口元のシワが目立つようになったりすることもあります。見た目の変化も自信の喪失や社会的な活動の低下につながるため、無視できないリスクです。
噛み合わせの乱れや全身への影響
1本でも歯を失うと、噛み合わせのバランスが崩れます。隣の歯が倒れてきたり、噛み合っていた反対側の歯が伸びてきたりすることで、全体の噛み合わせが不安定になります。歯並びが悪化するだけではなく、顎関節症の原因になることもあります。
認知症・生活機能の低下
近年の研究では、歯を多く失っている高齢者は、そうでない人と比べて認知症のリスクが高まることが報告されています。これは、咀嚼による脳への刺激が減少すると、脳の活動が低下するためだと考えられています。
また、歯の喪失による食事の質の低下や外出機会の減少、人との交流の減少なども生活機能の低下に拍車をかけます。つまり、歯を失うことは口だけの問題ではなく、認知機能や生活の質全体に関わる、重大なリスクであると言えるのです。
歯を失うのを防ぐために大切なこと
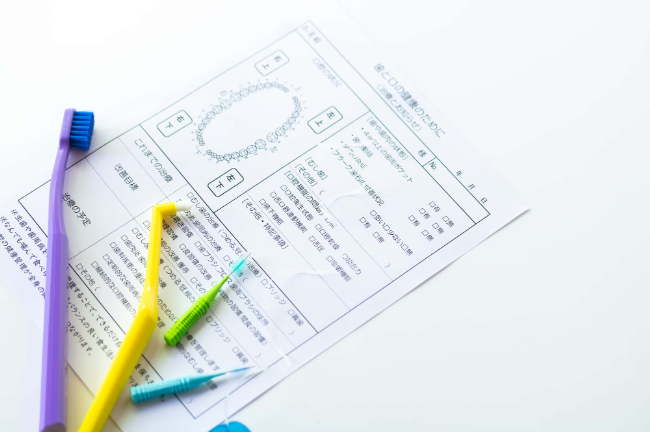
年をとると歯を失うのは避けられないと思う方は少なくありませんが、実際には日々のケアや意識次第で防ぐことが可能です。大切なのは、原因となる疾患や習慣に早く気づき、予防のための行動を継続することです。
ここでは、歯を守るために私たちができる具体的な対策を紹介します。
毎日の丁寧な歯磨き
毎日の丁寧な歯磨きは、歯の喪失を防ぐのに非常に効果的です。歯周病や虫歯の多くは、歯と歯ぐきの間に溜まったプラーク(歯垢)が原因となります。これをしっかり除去するには、1日2〜3回、少なくとも1回は10分程度時間をかけて丁寧に磨くことが大切です。
また、磨き残しが多くなりやすい奥歯の溝や歯間部には、デンタルフロスや歯間ブラシの併用が効果的です。自分の歯並びや口内環境に合ったブラッシング法を知るためにも、歯科衛生士によるブラッシング指導を受けるようにしましょう。
定期的な歯科受診とプロフェッショナルケア
どれだけ丁寧に歯を磨いていても、自宅でのケアだけでは取り切れない汚れが存在します。特に、歯周ポケットの奥深くに入り込んだ歯石やバイオフィルムは専門的な機器と技術でないと除去が困難です。
そのため、3〜6か月に一度を目安に、定期的に歯科検診を受けることが大切です。
定期検診では、虫歯や歯周病などの口腔内の状態チェックだけではなく、歯のクリーニングやフッ素塗布なども行ってもらえます。これらは虫歯などの予防に効果的であり、継続して通院することで、大きなトラブルを未然に防げます。
食生活の見直し
栄養バランスの良い食事は歯や歯ぐきの健康維持に欠かせません。カルシウムやビタミンC、たんぱく質を意識的に摂取し、噛み応えのある食品で咀嚼機能を鍛えることも効果的です。
糖質の多い食品や間食の頻度が多い生活は、虫歯菌の活動を活発にさせ、口内環境の悪化を招きます。特に、寝る前の飲食は唾液の分泌が減る時間帯と重なるため、虫歯のリスクを高めます。食生活の見直しは、口腔と全身の両方を健康に保つ第一歩です。
生活習慣の改善とストレス管理
喫煙や過度の飲酒、睡眠不足などの生活習慣の乱れは、歯周病の進行や免疫力の低下に直結します。喫煙は、歯ぐきの血流を悪化させて炎症を進行させる要因となり、治療の効果を下げるとも言われています。
生活習慣の見直しは、口腔内の健康だけでなく、全身の病気予防にもつながる重要な要素です。
また、現代人に多いストレスも無視できません。ストレスが溜まると歯ぎしりや食いしばりが増え、歯への負担が強まります。適度な運動やリラクゼーション法を取り入れ、心と体のバランスを保つことが、結果的に歯の健康維持にもつながるのです。
まとめ

歯を失うことは、見た目や噛みにくさだけの問題ではありません。咀嚼機能の低下から栄養不足、発音や表情の変化、全身疾患への影響、さらには認知症のリスクまで、私たちの健康や生活の質に深く関わる重要な問題です。
その原因の多くは歯周病や虫歯といった予防可能なものであり、早期の対処と習慣の見直しで多くのリスクは軽減できます。
自分の歯で一生を過ごすためには、正しい知識を持ち、日々のケアと専門的なチェックを怠らないことが大切です。まずは自分の口の中に関心を持ち、小さな変化に気づくことから始めてみましょう。
歯を守りたいとお考えの方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2025.07.08更新
ホワイトニングは虫歯があるとできない?知っておくべき注意点も
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

虫歯があってもホワイトニングはできますが、リスクや注意点があります。虫歯の状態によっては、ホワイトニングを優先することで歯の健康を損なうことがあるので注意が必要です。
この記事では、虫歯治療よりもホワイトニングを優先するリスクや注意点、虫歯の予防法について解説します。
ホワイトニングは虫歯があるとできない?

虫歯があったとしても、ホワイトニングを行うことはできます。
ただし、ホワイトニングの薬剤の影響により、以下のようなリスクを伴う場合があります。
虫歯が悪化することがある
虫歯治療とホワイトニングの施術は、同時には行えません。ホワイトニングの種類にもよりますが、施術には1〜3ヵ月かかることが一般的です。虫歯は自然に治ることはないため、この期間に虫歯が悪化する可能性があることを理解しておきましょう。
特に、歯の内部まで進んだ中等度の虫歯の進行は早いため、ホワイトニング期間に強い痛みが出ることがあります。さらに、虫歯が重症化すると、神経の治療が必要になり、健康な歯の大部分を損なうこともあるので注意が必要です。
また、ホワイトニングで歯が白くなる期間には個人差があります。歯の質によっては理想の白さになるまで長期間かかる場合があり、虫歯治療を後回しにすると歯を失うリスクも高まります。虫歯の大きさによっては、優先的に治療が必要になる可能性があることも理解しておきましょう。
歯がしみる・痛むなどの症状が出ることがある
ホワイトニングでは、効率よく歯を白くするために高濃度の薬剤を使用します。高濃度の薬剤であっても、健康な歯であれば強い痛みが出ることはほとんどありません。
しかし、虫歯になった箇所に薬剤が付着すると、歯がしみたり痛んだりすることがあります。特に、歯に穴が空いている場合や神経まで虫歯が進んでいる場合、歯茎に腫れや出血が見られる場合は症状が出やすいです。
痛みには個人差がありますが、何もしなくてもズキズキと強く痛む場合にはホワイトニングを延期せざるを得ないこともあります。
仮詰めが外れることがある
初期の虫歯であれば、1日で治療が完了することがほとんどです。
しかし、中等度以上の虫歯になると、複数回の治療が必要になり、仮詰めを施すことがあります。この期間にホワイトニングをすると、薬剤の付着により仮詰めが取れ、治療に影響を及ぼすことがあるので注意が必要です。薬剤が歯の内部に浸透し、痛みなどの症状が出るリスクもあります。
虫歯を治療してからホワイトニングをするときの注意点

歯の健康を考えれば、虫歯を治してからホワイトニングをするのが安心です。ここでは、治療を行ってからホワイトニングを受ける際の注意点について解説します。
補綴物には効果がない
ホワイトニングの薬剤は、健康な歯にのみ効果を発揮します。そのため、人工物である補綴物(詰め物や被せ物)を白くすることはできません。前歯や歯の表側に以前受けた治療箇所がある場合、自分の歯の色と補綴物の色に差が生じるリスクがあります。
色が気になる場合には、補綴物のやり替えを行う必要があるでしょう。
また、虫歯治療を受ける場合には、ホワイトニングを受けたい旨を事前に歯科医師に伝えてください。ホワイトニング後の歯の色を想定して、補綴物を作成できるケースもあります。
神経のない歯は白くできない
ホワイトニングの薬剤は健康な歯にしか効果がありません。そのため、虫歯や外傷などで神経を失っている場合、ホワイトニングでは白くできないことがあります。
神経を除去したあとの歯は、全体的にグレーっぽく見えることがあります。このような場合、一般的なホワイトニングではなく、ウォーキングブリーチという方法が選択されることが多いです。
ウォーキングブリーチとは、神経を失った歯の内部に薬剤を詰め、内側から歯を白くする方法です。
このように、お口の状態によって、効果的なホワイトニング方法は異なります。ご自身に合ったホワイトニング方法を知りたい場合には、まずは歯科医師にご相談ください。
知覚過敏の症状が出ることがある
虫歯治療で歯を削ると、一時的に知覚過敏の症状が現れることがあります。この状態でホワイトニングを受けると、薬剤の影響で歯がさらにしみることがあるので注意が必要です。
特に、ホワイトニングを受けた直後は、薬剤の影響により歯の表面が一層剥がれた状態になります。時間の経過とともに元の状態には戻るものの、ホワイトニングを受けた1~2日は刺激の強いもの、色の濃いものを摂るのは控えるのがよいでしょう。
また、歯の表層が剥がれた状態は、虫歯のリスクを高めます。そのため、ホワイトニング施術後は丁寧に歯磨きを行い、虫歯を予防することが大切です。
口内環境を整えてからホワイトニングを受ける
歯の表面に歯垢や歯石が付着しているとホワイトニングの効果が発揮できない場合があります。
なぜなら、歯の表面に汚れが溜まった状態になると、薬剤の成分が歯に吸収されにくくなるためです。また、歯茎に出血や腫れ、炎症がある場合には、強い痛みを伴うことがあります。
そのため、ホワイトニングを受ける際には、事前にお口全体のチェックを受け、口内環境を整えることが大切です。歯や歯茎の炎症を改善し、歯の表面の汚れや着色を取り除いてからホワイトニングを受けることで、より効果的に歯を白くできます。
自覚症状はないから早くホワイトニングを受けたいという方でも、お口の状態によっては歯科治療が優先されることがあります。
全ての治療を終えてからホワイトニングを受けることで、歯の白さを長持ちさせることにもつながるでしょう。
虫歯を予防する方法

お口の状態によっては歯科治療が優先になり、ホワイトニングの施術が延期になることがあります。そのため、できるだけ早く歯を白くしたいという方や、結婚式までに歯のトーンアップを図りたいという方は、日頃から虫歯を予防することが欠かせません。
ここでは、虫歯を予防する方法について解説します。
しっかりとセルフケアを行う
虫歯の原因は歯垢・歯石です。虫歯を予防するためには毎日しっかりと歯磨きをして、歯垢や歯石を除去することが重要です。口内に汚れが溜まると、細菌が繁殖し、虫歯のリスクが高まります。そのため、できれば毎食後に歯磨きを行いましょう。
歯ブラシで全体を磨くことも大切ですが、歯と歯の間には歯ブラシの毛先が届きにくいです。デンタルフロスや歯間ブラシを使用することで、歯ブラシが届きにくい歯と歯の間に付着した汚れも効果的に除去できます。
毎食後の歯磨きが難しい場合には、こまめにうがいをするのもよいでしょう。
ただし、寝る前の歯磨きは特に丁寧に行うことが大切です。そうすることで夜間の細菌繁殖を防ぐことができます。歯磨きの際にフッ素入りの歯磨き粉や洗口液を使用するとより効果的です。
定期的に歯科検診を受ける
虫歯を予防するためには、定期的に歯科医院で検診を受けることが欠かせません。毎日の歯磨きを丁寧に行っていても、歯磨きの仕方に癖があると、磨き残しができるものです。特に、歯ブラシの毛先が入りにくい歯と歯の間や歯と歯茎の境目には汚れが溜まります。
歯垢は歯ブラシでも取れるものですが、放置すると数日で歯石へと変化します。歯石は歯ブラシでは取り除けません。そのため、歯科医院で定期的に除去してもらう必要があるのです。お口の中の汚れを除去することで、虫歯だけでなく歯周病の予防にもつながります。
さらに、ホワイトニング後にも定期的にクリーニングを受けることで、歯の白さを長持ちさせることができるでしょう。
まとめ

ホワイトニングで理想の白さを手に入れるまで1〜3ヵ月かかることが多く、その期間に虫歯を放置すると悪化することがあります。また、虫歯がある状態でホワイトニングをすると、薬剤の影響により歯がしみたり痛んだり、仮詰めが外れたりすることもあるでしょう。
そのため、基本的には虫歯治療を優先的に行ってから、ホワイトニングを受けることが推奨されます。虫歯を治療し、お口の中を清潔にしてからホワイトニングを受けることで、薬剤の効果を高めることができるでしょう。
ホワイトニングを検討されている方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2025.06.10更新
子どもが虫歯になったらどうやって治療する?予防法も
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

子どもの歯は虫歯になりやすく、進行が早いです。乳歯だからといって放置すると、永久歯や噛み合わせに悪影響を与えるおそれもあります。
「子どもの虫歯はどのように治療するの?」「虫歯にさせないためにはどうすればよいの?」と考えている保護者の方もいるでしょう。
この記事では、子どもが虫歯になったときの治療法や虫歯を予防する方法、虫歯治療を受けられる年齢について解説します。お子さまの健康な歯を守るために、ぜひ参考にしてください。
子どもの虫歯の特徴

子どもの虫歯には、以下の特徴があります。
進行が早い
乳歯は石灰化が進んでいないため、永久歯に比べて歯質がやわらかいです。また、乳歯の表面のエナメル質は、永久歯のエナメル質の半分ほどの厚さしかありません。そのため、虫歯の進行が早く、短期間で神経に到達する恐れがあります。
気づきにくい
初期段階の虫歯は白っぽく濁った色をしていることが多く、保護者の方が見ても気づきにくいです。また、虫歯が進行して軽度の痛みが生じても、子どもは痛みをうまく訴えられないことがあります。
痛みが激しくなるまで、保護者の方が気づかず時間が経過することも多いでしょう。乳歯の虫歯は進行が早いため、痛みが激しくなった頃には神経まで到達していることも少なくありません。
永久歯に悪影響を与える
乳歯が虫歯になった場合、永久歯に悪影響を与えかねません。歯の根元まで虫歯菌が感染して膿が溜まると、変色した永久歯が生えてきたり、本来の歯の形ではない状態で生えてきたりする場合があります。
また、虫歯を放置して早期に乳歯を失うと、隣の歯が倒れてきて永久歯が生えてくるスペースがなくなり、歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼす恐れもあります。
子どもが虫歯になったらどうやって治療する?

前述したとおり、子どもの虫歯は気づきにくく進行が早いため、早めに治療することが大切です。ここでは、子どもが虫歯になったときの治療方法について、虫歯の進行段階別に解説します。
初期の虫歯
歯の表面のエナメル質が溶けている虫歯の初期段階であれば、フッ素を塗布して再石灰化を促し、様子を見ることが多いです。再石灰化とは、溶け出したカルシウムやリンが再び歯の表面に取り込まれ、エナメル質が修復されることです。
再石灰化は、唾液によっても行われます。そのため、歯科医院でのフッ素塗布だけでなく、間食を控えて普段のブラッシングをきちんと行うことも大切です。家庭で適切に歯磨きを行えるよう、ブラッシング指導も行います。
エナメル質の虫歯
エナメル質が溶け、穴が空いた段階になると、虫歯の部分を削ってレジン(歯科用プラスチック)や金属で詰め物をします。状態によっては、フッ素を塗布して様子をみる場合もあります。自覚症状は少なく気づきにくいため、歯科検診で発見されることも多いです。
歯の表面のみの治療なので、通院回数は1回程度です。
象牙質の虫歯
エナメル質の内側にある象牙質まで虫歯が進行すると、冷たいものや甘いものがしみることがあります。エナメル質の虫歯と同様に、虫歯の部分を削って詰め物をします。
歯を大きく削った場合は、詰め物をするための型取りが必要です。小さく削って詰めるだけなら1回の通院で治療できますが、型取りをする場合は2回の通院が必要となります。
神経まで達している虫歯
虫歯が神経まで進行すると、何もしていなくても強い痛みを生じることがあります。この段階になると、根管治療が必要です。
根管治療とは、神経や血管が入った根管の内部を取り除き、清掃する治療です。虫歯の部分を削ったあと根管治療を行い、被せ物をして噛む機能を回復させます。早くに歯を失うと、歯並びや噛み合わせに影響する場合があるため、生え変わりまで歯を維持させることが大切です。
根管治療は何度かに分けて行うため、4〜6回程度の通院が必要となります。
歯根まで進行している虫歯
虫歯が進行して歯根まで到達し、ほとんど残っていない場合は抜歯が必要です。乳歯を早期に失うと、隣接する歯が倒れてくる可能性があります。そのため、永久歯が正しい位置に生えるスペースを確保するための治療を行う場合があります。
虫歯の治療は何歳から受けられる?

子どもが虫歯治療を受けられる年齢は3歳頃が目安になります。3歳頃になると、歯科医院の椅子に座り、口を開けてじっとしていられるようになる子どもが多いためです。
治療を受けられるかどうかは、子ども自身が協力して治療が受けられるかどうかがポイントです。4〜5歳頃になると、歯科医師とのコミュニケーションがとりやすくなるため、治療を進めやすくなるでしょう。
治療を行う際は、無理に治療を進めるのではなく、歯科医院の椅子に座ったり、口を開けたりして歯科医院に慣れることから始めます。恐怖心を抱くと治療をスムーズに進められなくなるためです。
また、小さい頃から定期検診を受けておくと、虫歯になったときにスムーズに治療を始められます。乳歯が生え始める生後6ヶ月ごろ、遅くても乳歯が生えそろう1歳半頃には受診するとよいでしょう。
子どもが虫歯になるのを防ぐためには

子どもが虫歯になるのを防ぐためには、保護者がサポートすることが大切です。ここでは、子どもの虫歯を予防する方法を紹介します。
毎日の歯磨きを習慣づける
子どもの虫歯予防の基本は、毎日の歯磨きです。毎食後と寝る前に行うのが理想ですが、最低でも1日1回は歯を磨きましょう。就寝中は唾液が少なくなり虫歯のリスクが高まるため、寝る前の歯磨きは習慣にしてください。
歯磨きは歯が生え始めた頃から開始し、自分で歯ブラシを握れるようになったらストッパーがついた歯ブラシを持たせましょう。歯磨きの絵本を読んだり、子どもが好きなキャラクターの歯ブラシやフルーツ味の歯磨き粉を使用したり、楽しく取り組めるよう工夫しましょう。
保護者の仕上げ磨きを徹底する
永久歯が生える12歳頃までは保護者が毎日仕上げ磨きを行いましょう。子どもは、大人に比べて手先を器用に動かせず、歯のすみずみまで丁寧に磨くことは難しいためです。毎日最低でも1日1回、就寝前に仕上げ磨きを続けると、虫歯予防につながります。
子どもは上顎の真ん中の歯と歯の間や、奥歯と奥歯の間、奥歯の溝に虫歯ができやすいため、特に注意して歯を磨いてあげましょう。
食生活を整える
子どもの虫歯を予防するために、食生活を整えることも大切です。虫歯の原因になる細菌は糖分をエサにして酸を作り出し、歯を溶かします。甘いお菓子やジュースを頻繁に摂っていると、口の中に糖分が長時間留まるため、虫歯のリスクが高まるのです。
おやつは決まった時間に与え、だらだらと時間をかけて食べたり飲んだりしないよう声をかけましょう。焼き芋やおせんべいなど、糖分が少なく歯にくっつきにくい食べ物を選ぶのも虫歯予防に効果的です。
フッ素を塗布する
歯が生え始めた生後6ヶ月頃から、フッ素の塗布を行うのも虫歯予防として有効です。フッ素は、歯の表面のエナメル質を強化し、虫歯になりにくい歯にします。また、歯から溶け出したカルシウムやリンを取り込んで修復させる再石灰化も促す効果もあります。
効果は3ヶ月程度持続するといわれているため、虫歯予防のためには3ヶ月に一度程度フッ素を塗布しましょう。また、普段の歯磨きにも市販のフッ素入りの歯磨き粉を使用すると虫歯予防になります。
定期的に歯科医院を受診する
子どもの虫歯を予防するためには、歯科医院での定期検診を受けることも大切です。虫歯は初期段階では見た目で判断しにくく、痛みや違和感などの症状もほとんどありません。子どもは虫歯の進行が早いため、痛みが生じたときには神経まで達している場合もあります。
定期的に歯科医師がチェックすれば早期に発見でき、負担の少ない治療で済む可能性が高くなります。また、歯科医院ではクリーニングやフッ素塗布、ブラッシング指導などを通じて虫歯を予防することも可能です。
痛みや違和感などの症状がなくても、3〜4ヶ月に一度程度は受診するとよいでしょう。
まとめ

子どもの虫歯は進行が早く気づきにくい特徴があります。虫歯になった場合、初期段階で発見できればフッ素の塗布のみで様子をみることもありますが、虫歯が神経まで進行した場合は、虫歯を大きく削って根管治療が必要です。
虫歯を予防するには、毎日保護者が丁寧に仕上げ磨きをし、できるだけ甘いものを減らしましょう。
定期的に歯科医院を受診すると、虫歯になっても早期に発見でき、治療の負担も少なく済みます。フッ素の塗布やクリーニングによって虫歯予防につながるため、症状がなくても歯科医院を受診しましょう。
子どもの虫歯治療を検討されている方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2025.05.27更新
虫歯治療の費用はいくら?保険が適用されるかも解説
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。
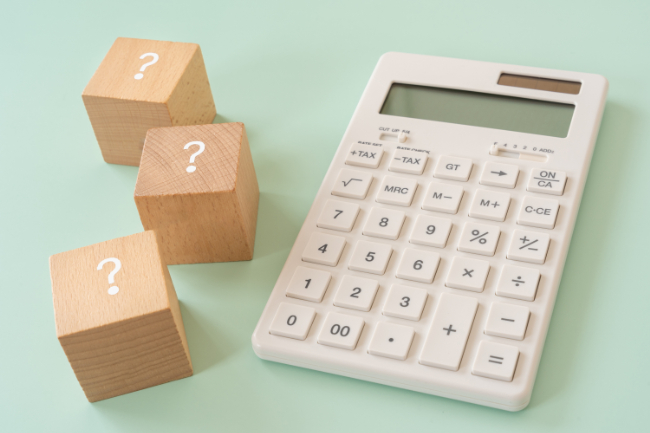
虫歯が進行すると、治療に時間がかかるだけでなく、治療費もかさみます。「虫歯治療にどのくらいの費用がかかる?」「保険は適用できるの?」など不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、虫歯の進行度ごとにかかる治療費の目安について解説します。保険が適用できる範囲や費用を抑える工夫についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
虫歯の治療にかかる費用

治療にかかる費用は、虫歯の進行度によって異なります。ここでは、虫歯の進行度に応じた治療内容と、費用の目安について解説します。
初診の場合
歯科医院を初めて受診した際には、レントゲン撮影や歯の状態の確認が行われます。初診料は3,000〜4,000円程度が目安です。治療を行う場合は、初診料に加えて治療費が発生します。
エナメル質の虫歯
初期の虫歯は、歯の表面のエナメル質が溶けた状態です。
歯の表面に小さな穴が空いた程度であれば、虫歯の部分を削ってレジン(歯科用プラスチック)の詰め物をします。穴が開くほど虫歯が進行していない場合は、フッ素を塗ってエナメル質の修復を目指すこともあります。
保険診療の場合、1本あたりの治療費は1,000〜3,000円程度です。処置時間も短く、1回〜2回程度の通院で治療が完了することが一般的です。
ただし、自費診療で審美性の高い素材(セラミックなど)を選択した場合は、1本あたり1万〜3万円程度かかります。
象牙質まで進行した虫歯
象牙質まで虫歯が進行すると、冷たいものや甘いものを口に入れたときにしみる場合があります。エナメル質の虫歯と同様に、虫歯の部分を削ってレジンで補う治療が行われます。
治療費の目安は3,000円〜1万円程度です。治療が完了するまでに、3〜4回通院が必要となるでしょう。
神経に達した虫歯
虫歯が歯の神経まで進行している場合は、根管治療が必要です。根管治療では、歯の神経や血管が含まれる根管の内部を取り除き、清掃します。
保険適用の場合、4〜5回以上通院し、1本あたり5,000円〜2万円程度の費用が必要です。自由診療の場合は2〜3回程度の通院で治療が完了し、7万〜15万円程度の費用がかかります。
根管治療後は、歯の強度を補うために土台を入れ、その上に被せ物(クラウン)を装着します。被せ物は保険適用の銀歯であれば3,000円〜4,000円程度です。見た目を重視してセラミックなどを選ぶ場合は自費診療となり、5万〜15万円程度かかることもあります。
抜歯が必要な虫歯
虫歯が大きく進行し、歯の保存が難しいと判断された場合は、抜歯が必要になることがあります。抜歯のみの費用は部位によって異なり、保険診療で1,000円〜4,000円程度です。
歯を抜いた後は、歯を補う治療が必要です。入れ歯やブリッジ、インプラントから選択します。
部分入れ歯は保険適用の場合1万〜1万5,000円程度、自由診療の場合15万〜50万円程度です。ブリッジは保険適用で1万〜3万円程度、自費診療でセラミックを使用すると10万〜20万円以上かかる場合があります。
インプラントは基本的に保険適用外となり、1本30万〜50万円が目安です。
虫歯治療に保険は適用される?

ここでは、虫歯の進行度ごとに保険診療が適用される範囲について解説します。
エナメル質から象牙質までの虫歯
エナメル質、もしくは象牙質まで進行している虫歯では、保険診療で対応できる治療が多く、安く治療を受けられます。治療に使われる素材は、保険適用で使用できるレジンが一般的です。審美性にこだわらなければ、奥歯や見えにくい部位でも保険診療で対応できます。
ただし、前歯など審美性が求められる部位で白い詰め物を希望する場合や、見た目に優れた素材セラミックを使用したい場合は、自費診療となります。
神経に達した虫歯
虫歯が神経まで進行した場合は、保険適用内での治療と自由診療での治療を選択できます。基本的には保険適用となり、ルーペ(拡大鏡)を用いて根管内をチェックして細菌を取り除きます。
自由診療で行うメリットは、検査や治療の材料を自由に使用でき、治療の精度を高められる点です。例えば、マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を使用して根管内を鮮明に映し出し、細菌を取り残しにくくできます。
また、ラバーダムという薄いゴムのシートを治療する歯以外に被せることで、根管治療中に細菌が再び感染するのを防ぐのです。
根管治療後の詰め物や被せ物にも、保険適用の素材と自費の素材を選べます。保険適用で使用できる素材は、レジン、銀歯、プラスチックとセラミックを混合したCADCAM冠の3つです。
自由診療では、オールセラミックやジルコニアなど、見た目や耐久性に優れた素材を使用できます。
抜歯が必要な虫歯
虫歯が進行し、歯の保存が難しくなった場合は抜歯が必要です。抜歯自体は保険診療で対応できますが、抜歯後の治療は歯を補う方法によって保険適用できるかどうかが異なります。
ブリッジや部分入れ歯は保険適用のほか、審美性や快適さを重視して自由診療を選択することも可能です。歯の部分がセラミック素材でできたブリッジや、金属製のバネのない入れ歯などが選べます。
虫歯で歯を失った後にインプラント治療をする場合は自由診療となり、保険は適用されません。
自費の治療を選択するメリット

ここからは、自費で虫歯治療を行うメリットについて解説します。
自然で美しい見た目に仕上げられる
自費の治療では、詰め物や被せ物として審美性に優れたセラミックを使用できます。セラミックは陶器素材でできており、天然歯に近い透明感や質感が特徴です。
レジンの場合、周りの歯と色調が異なって目立ちやすく、経年劣化によって変色しやすいデメリットがあります。
セラミックの場合は周りの歯に合わせて色味を調整できるうえ、変色しにくいのです。また、透明感が高く前歯でも目立ちにくいオールセラミックや、強度が高く奥歯にも使用されるジルコニアなど、治療する部位に合わせて選べるのもメリットです。
長持ちしやすい
自費診療で使用されるセラミックは、耐久性が高く、長持ちしやすい素材です。種類にもよりますが、適切にメンテナンスすれば10〜15年以上使用できるとされています。
一方で、保険診療で使用される銀歯の寿命は5〜7年程度、レジンの場合は2年程度です。取れたり、劣化して歯との間に隙間が生じたりすると交換しなければなりません。
セラミックは自費のため初期費用は高額になりますが、長期的に見れば再治療の頻度が減り、結果的にコストを抑えられる可能性があります。
金属アレルギーの心配がない素材を選べる
保険診療で使用される銀歯は、口腔内の炎症や皮膚症状などの金属アレルギーを引き起こすおそれがあります。唾液によって金属の成分が溶け出して体内に入り、体が異物とみなすと、アレルギー反応を引き起こします。
金属アレルギーのない方でも、銀歯を入れた数年後にアレルギー症状が表れるケースもあるのです。
一方、自費診療では金属を一切使わないオールセラミックやジルコニアなど、金属アレルギーの心配がない素材を選べます。
治療の精度を上げられる
自費で治療する場合、保険診療のように治療に使う器材や検査器具に制約がないため、より精度の高い治療が可能です。例えば、虫歯が神経まで進行している場合、再発しないためには根管内を徹底的に清掃し、細菌を取り除く必要があります。
自由診療ではマイクロスコープを用いて細部まで確認できるため、細菌を取り残すリスクが低いのです。
また、被せ物を作製する際は、変形しにくく精密な型取りが可能なシリコンの印象材を使用します。保険診療と比べて、詰め物や被せ物自体の精度も上げられるのです。
虫歯治療の費用負担を軽減するためには

ここでは、虫歯治療にかかる費用を軽減するための方法を紹介します。
保険適用内での治療を希望する
費用を抑えたい場合は、保険適用内での治療を希望しましょう。虫歯治療は保険適用内でも十分に可能です。患者さまの状況によって異なりますが、保険適用内であれば費用の1〜3割負担で治療できます。
ただし、詰め物や被せ物をする際に使用できる素材は限られます。審美性や耐久性におけるデメリットも理解しておきましょう。
医療費控除を活用する
虫歯治療を含め、1年間の医療費が一定額を超えた場合は、医療費控除を申請できます。医療費控除とは、医療費の一部が所得税から控除される制度です。
見た目を改善する審美目的で治療した場合は医療費控除の対象となりませんが、自費診療であっても、医療費控除の対象となるケースがあります。失った歯を補う目的でセラミックを使用した場合は、機能回復が目的であるため対象になる可能性があります。
公共交通機関で通院した場合の交通費も含まれるため、領収書や医療費明細は大切に保管しておきましょう。
デンタルローンを利用する
デンタルローンとは、歯科治療で利用できるローンです。虫歯治療後にセラミック治療やインプラントを行う場合、治療費用が10万円を超えることも珍しくありません。一度に支払うのが難しい場合は、ローンを利用して少しずつ支払うのもひとつの方法です。
デンタルローンは、一般的にクレジットカードの分割払いよりも低金利で借りられるのもメリットです。
ただし、一括で支払うよりも費用がかさむことは理解しておきましょう。
定期的に検診を受ける
虫歯は初期の段階で発見して治療すれば、費用も処置内容も軽く済みます。
しかし、放置すると虫歯が進行し、根管治療や抜歯などの治療が必要となります。治療が複雑になると、費用もかさむのです。
そのため、歯のトラブルが発生しても早めに対処できるよう、定期的に歯科検診を受けましょう。初期段階で虫歯を発見できれば、軽度な治療で済ませられます。定期的に受診すれば歯のクリーニングも受けられるため、虫歯の予防にもつながります。
まとめ

虫歯が進行すると、必要な処置が増えるため、通院回数が増え、費用も高額になりやすいです。基本的な治療には保険が適用されますが、使用できる器材や歯を補うための素材には制限があります。
自費での治療は、保険適用内での治療よりも高額になりますが、詰め物や被せ物に審美性や耐久性の高い素材を使うことが可能です。費用負担を抑えるには、医療費控除を活用し、定期的に検診を受けて再発を予防しましょう。
虫歯治療を検討されている方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2025.03.18更新
虫歯の初期症状とは?見逃しがちなサインと治療法
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

虫歯は、早期に発見すれば進行を防ぐことができますが、初期症状は非常に軽微で見逃されやすいです。どのような症状か現れるのかを知り、早期に受診できるよう努めましょう。
この記事では、虫歯発生のメカニズムや虫歯の初期症状、初期虫歯を治療する方法、虫歯の予防方法について解説します。
虫歯発生のメカニズム

虫歯は、歯の表面にあるエナメル質が酸によって溶かされることで発生します。酸は、食べ物に含まれる糖分が口内の細菌によって分解される過程で作られます。虫歯が発生する具体的なメカニズムは、以下のとおりです。
- 食べ物の摂取
- 細菌の活動
- エナメル質の脱灰
- 再石灰化
- 虫歯の進行
食事を摂って口内に残った糖分を餌に、細菌が酸を作り出します。発生した酸が歯の表面のエナメル質を溶かし、少しずつ歯を侵食していきます。
エナメル質が酸にさらされると、歯の主成分であるカルシウムやリンなどのミネラルが溶け出して歯が弱くなります。この現象を脱灰と呼びます。
通常、唾液中のカルシウムやリンが歯に再度補充されて、歯が修復される再石灰化が起こります。脱灰と再石灰化のバランスが保たれていれば、虫歯が発生することはありません。
しかし、酸の影響が長時間続いて再石灰化が追いつかなった場合、エナメル質が完全に溶けてしまいます。この状態を虫歯と呼びます。
虫歯の初期症状

詳しい初期虫歯の治療法は後述しますが、初期段階で治療できれば大がかりな処置は必要ないケースがほとんどです。そのため、初期症状を理解し、早期に受診することが重要といえます。
ここでは、虫歯になると現れる初期症状をご紹介します。
歯の表面に白い斑点が現れる
エナメル質が酸に溶かされると、歯の表面に白い斑点が現れます。脱灰が進んでいるサインで、虫歯が穴を開ける前の状態といえます。
また、酸によって歯のエナメル質が溶け出した部分に色素が沈着すると、歯に黒い点や線が見られるようになることもあります。白い斑点や黒い点が見られた場合は、早期に歯科医師に相談しましょう。
歯がざらざらし始める
虫歯が進行してエナメル質が少しずつ溶け始めると、歯の表面が滑らかでなくなり、ざらついた質感になります。この状態は歯が弱くなっている証拠で、手で触った時に違和感を覚えることもあるでしょう。
そのまま放置すると、さらに進行して歯に穴が開いていきます。
冷たいものを飲んだときにしみる
虫歯によってエナメル質が薄くなると、冷たいものを摂取したときに歯がしみることがあります。歯の内部にある象牙質が露出してくると、より顕著に現れる症状です。
虫歯が悪化しているサインと言えるので、早めに歯科医院を受診する必要があります。
噛むとわずかに痛みを感じる
虫歯の初期症状として、食べ物を噛んだり歯に圧力がかかったりした際にわずかな痛みが発生することも挙げられます。特に、硬い食べ物を噛んだときや、歯に負担がかかったときに痛みを感じやすいです。
歯茎が少し腫れる
歯の根元に虫歯が発生すると、歯茎が腫れたり赤くなったりすることがあります。腫れが気になる場合は早めに歯科医師に診てもらい、虫歯の進行を食い止めることが大切です。
口臭が気になり始める
虫歯が悪化すると、歯の中で細菌が繁殖し嫌な臭いを発生させることがあります。口臭が強くなったと感じたときは、虫歯が進行している可能性があるでしょう。
虫歯は放置すると進行するので、早期に歯科医院でチェックを受けることが推奨されます。
初期虫歯を治療する方法

お伝えしたとおり、虫歯が進行すればするほど治療が複雑化していきます。大がかりな処置が必要になったり、歯を残せなくなったりすることもあるでしょう。
しかし、初期段階で治療を始められれば、患者さまへの負担を大幅に抑えられます。ここでは、初期虫歯の治療方法を詳しく解説します。
フッ素塗布
初期虫歯の治療方法の一つは、フッ素塗布です。フッ素には、歯のエナメル質を強化し再石灰化を促進する効果があります。ごく初期の虫歯であれば、フッ素塗布とブラッシング方法の見直しで改善できる可能性もあります。
特に、歯科医院で行うフッ素塗布は濃度が高いため効果的です。定期的にフッ素塗布を受ければ、初期虫歯を修復できるでしょう。さらに、虫歯予防にもつながります。
ブラッシング指導
初期虫歯の治療において、正しいブラッシングは非常に重要です。歯科医院でのブラッシング指導では、正しい歯磨きの方法を学びます。歯の表面に残るプラークや食べかすを効果的に除去し、虫歯の原因となる細菌の繁殖を防ぎます。
特に、初期虫歯の場合、適切なブラッシングを行うことで再石灰化を促進し、虫歯の進行を抑えることが期待できます。
PMTC
PMTC(プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング)は、歯科医院で行う専門的なクリーニングです。初期虫歯の治療にも効果的でしょう。
PMTCでは、歯科医師や歯科衛生士が専用の機器を使って、歯の表面に付いたプラークや歯石、着色汚れを丁寧に除去します。専門家による清掃で、歯の表面がきれいになり、細菌の繁殖を防ぐことができます。
また、PMTC後にフッ素塗布を行えば、エナメル質を強化し初期虫歯の進行を防ぐことが期待できます。
虫歯を予防する方法

初期段階で治療すれば、上述した簡単な処置で虫歯の改善が期待できます。
しかし、虫歯は進行性の病気で、歯を削るなどの処置が必要になることも少なくありません。治療すれば進行を止めることはできますが、削った歯質が元の健康な状態に戻ることはありません。
そのため、虫歯は予防することが非常に重要です。ここでは、虫歯を予防する方法について解説します。
適切な歯磨き
毎日の歯磨きは虫歯予防に欠かせません。食後は特に丁寧に磨きましょう。また、歯と歯の間の汚れは歯ブラシだけでは落としきれないため、歯間ブラシやデンタルフロスを使うと、虫歯予防に効果的です。
フッ素入り歯磨き粉の使用
フッ素入り歯磨き粉の使用も、虫歯予防に非常に有効です。フッ素には、歯のエナメル質を強化し再石灰化を促進する作用があります。
特に、虫歯のリスクが高い場合や、歯の再石灰化を助けたい場合に、積極的に取り入れると効果的です。
食後のうがい
飲食後すぐに歯磨きができないときは、うがいが非常に効果的です。うがいは、口内に残った食べかすや酸を洗い流し、虫歯の原因を減らす役割があります。
可能であれば歯磨きをするのが理想ですが、難しい場合はうがいだけでも行いましょう。
こまめに水分を補給する
口内が乾燥していると細菌が繁殖するリスクが高くなるため、こまめに水分を摂ることも重要です。糖分が入っている飲み物の摂取は虫歯の原因となるため、水やお茶などの糖分を含まない飲み物を選択しましょう。
定期的な歯科検診
定期的に歯科医院での検診を受けることで、虫歯の早期発見が可能です。虫歯は進行する前に発見することが大切で、早期に治療すれば大きな問題を避けることができます。
また、歯のクリーニングを受ければ、日々のセルフケアでは落としきれない汚れを取り除くことができます。定期的な歯科検診は、虫歯を効果的に予防するためには欠かせません。
シーラントの使用
シーラントは、歯の溝を樹脂で埋めて食べかすや細菌が溜まりにくくする予防法です。奥歯の噛む面の溝が深い子どもに効果的で、6〜12歳のお子さまであれば保険が適用されることもあります。
飲酒や喫煙を控える
タバコを吸うと血流が悪化するため、口内の免疫力が低下し虫歯や歯周病のリスクが高くなります。また、アルコールも口内の乾燥を引き起こし、虫歯を悪化させる原因になります。
タバコやアルコールの摂取を控えることも、虫歯予防につながります。
まとめ

虫歯の初期症状は、歯の表面に現れる白い斑点や軽い痛みなどが特徴です。これらの兆候を見逃すと、虫歯が進行し歯に穴が開いたり痛みが強くなったりすることがあります。
日々の適切な口腔ケアと定期的な歯科検診を受けることで虫歯の進行を防ぎ、健康な歯を維持しましょう。
虫歯の治療を検討されている方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2024.12.24更新
重度の虫歯の症状は?放置リスクと治療方法、治療費用と期間について
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

虫歯は成人した日本人のおよそ9割が経験しているといわれていますが、なかには治療を受けないまま虫歯を放置している方もいるでしょう。虫歯を放置し、重度の状態にまで進行するとさまざまなリスクがあります。
今回は、重度の虫歯の症状や放置するリスク、治療法などについてくわしく解説します。虫歯にお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
重度の虫歯の症状

軽度の虫歯は、痛みなどの症状がほとんどなく、見た目でもわかりづらいため、発見が遅れやすいです。中等度の状態にまで進行すると冷たいものを口にするとしみたり痛んだりすることもあります。
重度の状態にまで虫歯が進行すると、日常生活に影響を及ぼすことも少なくないでしょう。以下では、重度の虫歯の具体的な症状について解説します。
強い痛みを感じるようになる
虫歯が進行し、歯の内部にある神経にまで達すると強い痛みを感じるようになります。
中等度の虫歯では冷たいものや熱いものを口にしたときに痛みを感じることがありましたが、重度の状態にまで進行すると何もしていなくても痛みを感じるようになるのです。一日中ズキズキと痛むこともあるでしょう。
さらに虫歯が進行し、神経が壊死すると痛みを感じなくなります。痛みがなくなったからといって放置する方がいるかもしれません。
しかし、さらに放置すると顎の骨にまで影響を及ぼす可能性があるため、治療を受ける必要があるのです。
変色する
虫歯が進行すると歯の表面にあるエナメル質に穴が開き、部分的に黒ずんだり茶色く変色したりすることがあります。虫歯が重度の状態にまで進行すると、外側から見ただけでもわかるくらいに大きく黒ずむことがあります。
歯茎や顔が腫れる
虫歯が歯根にまで到達すると、歯茎や顎骨にまで細菌感染が広がることがあります。これによって、歯茎が赤く腫れたり膿が溜まったりする場合もあるでしょう。
さらに進行して体の免疫力が低下すると、顔が腫れることもあり、その部分が熱を持ったり発熱したりする場合もあります。
歯が欠ける・ぐらつく
虫歯が重度の状態にまで進行すると、歯がもろくなって欠けたりぐらついたりすることもあります。この段階では食べ物を噛むことが難しくなったり会話しにくくなったりする可能性もあるでしょう。
重度の虫歯の放置リスク

重度の虫歯を放置するとさまざまな悪影響があります。ここでは、重度の虫歯を放置するリスクについてくわしく解説します。
歯を失う可能性がある
虫歯が重度の状態にまで進行すると、歯の神経や歯根にまで細菌が到達し、最終的には抜歯が必要になる可能性があります。歯を失うと再生することはありません。
歯を失うと噛み合わせに影響が出るだけでなく、空いたスペースに隣接する歯が移動するなどして歯並びが乱れることもあるでしょう。
歯周病になるリスクが高まる
虫歯を放置すると、歯周病を引き起こすリスクも高まります。虫歯によって細菌が増殖し歯茎や顎骨に炎症が広がると、歯周組織が破壊されます。
歯周病にかかると口臭がひどくなったり口の中がねばついたりといった症状が現れます。さらに悪化すると歯が抜け落ちる可能性もあるでしょう。
全身の健康に影響を及ぼす可能性がある
重度の虫歯を放置すると全身の健康に影響を及ぼす可能性もあります。虫歯菌が血液を介して全身をめぐると、頭痛や発熱などの症状が現れる可能性があるだけでなく、心筋梗塞や脳梗塞といった深刻な病気を引き起こすリスクもあります。
特に免疫力が低下している方や、基礎疾患を持っている方は通常よりも合併症を引き起こすリスクが高まるため注意が必要です。また、虫歯による炎症が続くと病気に対する抵抗力が弱くなり、生活習慣病の発症リスクが高まることも考えられます。
重度の虫歯の治療方法

では、重度の虫歯はどのように治療するのでしょうか。ここでは、重度の虫歯の代表的な治療方法について解説します。
根管治療
虫歯が歯の神経にまで達した場合は、根管治療が必要になります。根管治療とは、歯の内部にある感染した神経や血管を取り除き、洗浄・消毒する治療のことです。その後、土台を立て、その上に被せ物を装着して歯の機能を回復させます。
根管治療を受けることで、ご自身の歯を残すことができます。
抜歯
虫歯がさらに進行し、歯の根元や周囲の組織に深刻なダメージを与えている場合や、根管治療をしても歯を残せないと判断される場合には抜歯が必要になるケースが多いです。抜歯後は、以下の方法で歯を補うのが一般的です。
入れ歯
入れ歯とは、失った歯を補う取り外し可能な人工歯のことです。保険が適用される入れ歯を選択することで費用を抑えることができます。また、取り外してお手入れができるため、清潔に保ちやすいです。
一方で、食事の際にズレて噛みにくかったり、慣れるまでは違和感を覚えやすかったりする点はデメリットといえるでしょう。また、保険が適用される部分入れ歯の場合は、口をあけたときに金属のバネが目立つ可能性があります。
ブリッジ
ブリッジとは、欠損した歯の両隣の歯を支えにし、橋を架けるように人工歯を装着する治療法です。
固定式のため、食事の際にズレることがありません。また、取り外してお手入れをする必要がなく、天然の歯と同じように歯磨きができます。セラミックなどの審美性の高い素材を選択することで、天然の歯のような見た目になる点もメリットです。
一方で、支えにする両隣の歯を削らなければならない点はデメリットといえるでしょう。
インプラント
インプラントとは、顎の骨に人工歯根を埋めこみ、その上に人工歯を装着する治療法です。人工歯根と顎の骨が結合されることでズレることなく、しっかり噛めるようになります。天然の歯のような見た目を再現できるのもメリットです。
一方で、顎の骨に人工歯根を埋め込むためには外科的な手術が必要になります。また、自費診療になるため、費用が高額になる点もデメリットといえるでしょう。
重度の虫歯の治療期間

軽度の虫歯であれば短期間で治療が完了することが多いですが、重度の状態にまで虫歯が進行すると複雑な治療が必要になるため、治療期間が長くなる傾向にあります。ここでは、重度の虫歯の治療期間の目安について解説します。
根管治療の場合
根管治療にかかる期間は1〜2ヶ月程度が目安です。
根管治療は基本的に2〜4回の通院が必要になります。1回あたりの治療にかかる時間は30〜60分程度で、感染状態によっては通院回数が増えることもあるでしょう。また、治療後に装着する被せ物の作製と調整のために1〜2回程度の通院が必要になります。
抜歯の場合
抜歯自体は1回の通院で完了します。抜歯後、部分入れ歯やブリッジ、インプラントなどの歯を補う治療を受ける場合にはさらに時間がかかります。
- 部分入れ歯:2週間〜1か月程度(保険診療の場合)
- ブリッジ:1〜2か月程度
- インプラント:半年〜1年程度
インプラントの場合は、埋め込んだ人工歯根と顎の骨が結合するのを待つ必要があるため、入れ歯やブリッジに比べて治療期間が長いです。また、顎の骨を増やす治療が必要になる場合には、さらに治療期間が延びる可能性があるでしょう。
重度の虫歯の治療費用

虫歯の治療には基本的には健康保険が適用されます。
しかし、使用する素材や治療法によっては保険が適用されず、全額自己負担になることもあります。ここでは、重度の虫歯の治療にかかる費用について解説します。
根管治療の場合
根管治療にかかる費用は保険適用の3割負担の場合、3,000円〜5,000円程度が目安です。根管治療後に装着する被せ物の費用は、選択する素材によって異なります。保険が適用される金属製の被せ物は3,000円〜5,000円程度です。
セラミックやジルコニアなどの審美性の高い素材を選ぶと、保険が適用されず高額になる傾向にあります。例えばセラミックで作られた被せ物は1本あたり8万円〜18万円程度が目安になります。
抜歯の場合
抜歯にも保険が適用されることが多く、かかる費用の目安としては1本あたり3,000円〜7,000円程度です。
抜歯後に部分入れ歯やブリッジ、インプラントで歯を補う場合には、それぞれ費用がかかります。部分入れ歯やブリッジの場合、選択するものによっては保険が適用されます。費用の目安は、以下のとおりです。
- 部分入れ歯:5,000円〜1万5,000円程度(保険診療の場合)
- ブリッジ:1本あたり2万円程度(保険診療の場合)
- インプラント:1本あたり30万円〜50万円程度
インプラントは保険が適用されないため、高額な費用がかかります。自費診療の場合は歯科医院によって金額が異なるので、費用が気になる方は事前に見積もりを取って比較検討しましょう。
まとめ

重度の虫歯を放置すると、歯を失うだけでなく全身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。
虫歯が神経にまで達すると強い痛みが現れ、さらに進行すると神経が壊死して痛みを感じなくなることもあります。痛くなくなったからといって放置してはいけません。他の歯を守るためにも治療を受けましょう。
虫歯が神経にまで達している場合には根管治療を行います。歯を残せないほど進行している場合には抜歯を行い、入れ歯やブリッジ、インプラントなどで歯を補います。
虫歯が進行すればするほど複雑な治療が必要になり、その分費用も時間もかかります。そのため、虫歯がある場合は放置せず、違和感があるときは早めに歯科医院を受診してください。
虫歯にお悩みの方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2024.10.15更新
子どもが虫歯になりやすい理由!進行レベル別の治療方法や防ぐ方法
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

子どもの歯である乳歯は、大人と比較して虫歯になりやすいとされています。乳歯のうちから虫歯になると、永久歯の歯並びの悪化や変色といった悪い影響を及ぼす可能性もあります。
子どもの歯を虫歯から守るためにはどのような対策が必要なのか、疑問に思う方もいるでしょう。
今回は、子どもが虫歯になりやすい理由や進行別の治療法、虫歯を防ぐ方法について解説します。
子どもが虫歯になりやすい理由

子どもの歯である乳歯は、永久歯と比較して虫歯になりやすいとされています。主な原因として、歯磨きや間食といった習慣や、歯の構造が挙げられます。
子どもの虫歯の原因を理解して適切に対処を行うこと、がむし歯の予防につながります。
エナメル質が薄い
乳歯は、永久歯とよりもエナメル質が薄いです。エナメル質は、歯の内部を保護したり細菌やウイルスから歯を守ったりする役割を持つ組織です。
そのため、エナメル質が薄い乳歯はむし歯になりやすいのです。
歯磨きに慣れていない
歯磨きがうまくできないことで口の中に食べかすが残ると、虫歯のリスクが高まります。特に、小さい子どもは手先があまり器用ではなく、歯磨きを十分にできません。
虫歯菌は食べかすや磨き残しをエサにして増殖していくため、虫歯を予防するためには正しい歯磨きで汚れを取り除かなければなりません。お子様だけで十分に磨けないことが多いので、10〜12歳頃までは仕上げ磨きが必要とされています。
糖分を好む
甘いお菓子や飲料といった、糖分の多い食品を食べると虫歯のリスクが高まります。クッキーやチョコレート、ジュースなど、甘い飲食物を好むお子様が非常に多いことも、子どもが虫歯になりやすい理由と言えるでしょう。
食事の回数が多い
子どもは体が小さく、1日3回の食事では十分な栄養・エネルギーを摂取できないことが少なくありません。特に子どもは成長が著しいため、3回の食事とは別で1日1〜2回、補食が必要とされています。
しかし、長い時間口の中に糖分が留まると、虫歯のリスクが高まるのです。食後は口内が酸性に傾きますが、唾液の働きによって徐々に中和されていきます。食事の回数が多いと中和が間に合わず、酸性の時間が長く続くため虫歯になりやすくなります。
子どもの虫歯の特徴

子どもの虫歯の特徴を確認しましょう。
進行が速い
子どもの虫歯は、大人よりも進行が早いのが大きな特徴です。また、初期段階の場合には痛みが少ないことも多く、進行するまで虫歯に気づかないケースもあります。
虫歯になっても歯が白い
子どもの乳歯が虫歯になった場合、黒く変色するのではなく白く濁ることが多いです。歯の表面のエナメル質が酸によって溶けることで、白く濁った色になります。
虫歯は黒いというイメージを持っている方が多いため、見過ごされる原因になりやすいです。
神経まで達しやすい
乳歯は、大人の歯に比べて虫歯への抵抗力が弱いという特徴があります。エナメル質が薄いため進行しやすく、悪化すると神経まで達するリスクが高いでしょう。
永久歯に影響を及ぼす
乳歯が虫歯になると、永久歯に悪い影響を及ぼす可能性があります。具体的には、歯並びが悪くなったり、永久歯が変色したりするリスクがあります。永久歯の発育が十分に進まない恐れもあるので、いつか抜ける乳歯の虫歯も予防することが重要です。
子どもの虫歯の治療方法[進行レベル別]

子どもの虫歯は、進行度に応じて治療法が変化していきます。
虫歯が進行すればするほど、治療期間が長くなって通院回数が多くなっていきます。最悪の場合には抜歯が必要になる可能性もあります。
虫歯になってしまった場合には、できる限り早期に治療を始めることが重要です。
C0(虫歯になりかけの状態)
C0の虫歯は、感染している部分が浅く特別な治療を必要としません。正しいブラッシングやフロスによって汚れを落としたり、フッ素を塗布して虫歯の進行を止めたりする治療を中心に行います。
また、歯科医院でのケア・治療だけでなく、唾液の分泌量を増やすことも効果的です。よく噛んで食べる必要がある食材を与えるなど、工夫してみましょう。
C1(エナメル質に虫歯がある状態)
エナメル質に虫歯が進行すると、虫歯がある箇所をドリルで削って詰め物をするという治療を行います。レジンを詰めて治療するのが一般的です。
この段階であれば、1日で治療が終了する場合もあります。
C2(虫歯が象牙質に達している状態)
C2の状態でも、基本的には虫歯部分を削って、削った部分を補うという治療を行います。
ただし、虫歯が象牙質まで達している場合、歯を削る量が多くなります。より広範囲を削って詰め物を行うため、治療の負担が増加する可能性があります。
C3(虫歯が神経に達している状態)
虫歯が神経まで達すると、激しい痛みが生じて日常生活に支障をきたすようになります。この場合、根管治療が必要になるでしょう。神経を抜いた後には、被せ物を装着して歯を補います。
子どもの歯の場合、神経の一部を残して子どもの再生力を利用して治療するケースもあります。
C4(歯冠が崩壊した状態)
虫歯が歯の根元まで達すると、神経が死んで痛みを感じなくなります。このまま放置すると、歯茎が膿み強い痛みを感じたり、口内環境が悪化したりします。
虫歯がこの段階まで進行すると、抜歯を行うことが多いです。
子どもの虫歯を防ぐ方法

子どもの虫歯を防ぐためには、日ごろの食生活に気をつけて適切なケアを続けることが重要です。食事管理や正しい歯磨きは小さな子供だけでは徹底できないので、保護者の方の協力が不可欠でしょう。
食生活に気を付ける
子どものむし歯を防ぐためには、間食の内容やタイミングに気を付ける必要があります。特に、砂糖を含んだおやつや飲み物をだらだらと食べていると、口内に長時間糖分が残るので虫歯になりやすいです。
間食をする時間を決めて、だらだら食べないように気をつけましょう。また、寝る前の間食を控えたり、糖分が残りやすい飴やチューイングキャンディなどのお菓子を避けたりすることも重要です。
適切な歯磨きを行う
正しい歯磨きの習慣を身に付けることが、虫歯のリスクを減らすために重要です。口の大きさに合う歯ブラシを使用して、歯の表面だけでなく歯と歯の間や歯茎など隅々まで丁寧にブラッシングしましょう。
小さい子どもが一人で歯磨きを行うのは難しいため、仕上げ磨きを行うことも虫歯予防につながります。
フッ素を塗布する
フッ素を塗布することで、歯のエナメル質を強化できます。生活習慣や口内の状態に合わせて、3ヶ月に1回を目安にフッ素塗布を受けましょう。
また、フッ素入りの歯磨き粉を日常のケアに取り入れることも虫歯予防に効果的です。
定期検診を受ける
定期的に歯科医院を受診することで、セルフケアでは除去できない汚れを除去したり、虫歯の早期発見に繋げられたりします。定期検診では正しい歯磨き方法の指導も行われるので、普段のケアの質を高めることにもつながるでしょう。
まとめ

子どもの歯である乳歯は、永久歯と比較して虫歯になりやすいとされています。主な原因として、永久歯よりもエナメル質が薄いことや歯磨きを上手に行えないこと、栄養補給のために間食の習慣があることが挙げられます。
子どもの虫歯は白く濁るだけで見た目では分かりづらかったり、進行が早いなどの特徴があります。気づかないうちに神経まで達している可能性もあり、最悪の場合には抜歯が必要になることも考えられます。
日ごろから食生活に気を付け、定期検診を受けて虫歯を早期に発見・治療を行うことが重要です。
子どもの虫歯が気になる方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2024.09.17更新
虫歯になりやすい人の特徴と対処法は?基本的な治療内容と費用
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

「毎日丁寧に歯磨きをしているのに虫歯ができるのはどうして?」といった悩みをもつ方は少なくありません。虫歯のなりやすさは、生まれつきの歯の質や食生活、生活習慣などによって左右されます。
今回は、虫歯になりやすい人の特徴と対処法について解説します。虫歯治療の内容や費用についても言及していますので、虫歯になりやすくてお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
虫歯になるメカニズム

そもそも虫歯とは、虫歯菌が出す酸によって、歯が溶かされることで起こる病気です。虫歯菌は、食べ物に含まれる糖分をエサに繁殖するため、甘いものをよく食べる人は虫歯になるリスクが高いといえます。
ただし、虫歯のなりやすさは食生活だけに左右されるものではありません。そこでここでは、虫歯になるメカニズムについて解説します。
虫歯菌
虫歯の原因は、ミュータンス菌を代表とする虫歯菌です。虫歯菌は磨き残しであるプラークに潜み、糖分を摂取した際に出す酸によって歯を溶かし、虫歯を発症させます。
ただし、虫歯菌は多くの人のお口の中に存在しているため、虫歯菌が潜んでいる=虫歯になりやすいというわけではありません。虫歯菌の動きが活発になれば、虫歯になるリスクが高まります。
つまり、餌となる糖分がお口の中に多く、さらに磨き残しが多ければ、虫歯菌にとって住み心地の良い口内環境となり、虫歯になるリスクが高まるのです。甘いものを控え、しっかり歯磨きをしてお口の中を清潔に保っていれば、虫歯を予防できるでしょう。
糖分
虫歯菌は、食べ物に含まれる糖分をエサに繁殖し、酸を作り出します。また、頻繁に間食を摂っているとお口の中が酸性に傾く時間が長くなるため、歯の再石灰化が促されず、虫歯になるリスクが高まるのです。
そのため、規則正しい食生活を心がけ、間食や甘いものを控えるのがよいでしょう。
歯の質
歯の質は一人ひとり異なり、きちんと歯磨きをしていても虫歯になりやすい人もいます。歯の質は遺伝することがあるため、ご家族のなかに虫歯になりやすい人がいる場合はご自身も虫歯になりやすいかもしれません。
虫歯になりやすい人の特徴

ここでは、虫歯になりやすい人の5つの特徴を解説します。
歯質が弱い人
きちんと歯磨きしていても、生まれつき歯の質が弱ければ虫歯になりやすいといえます。歯質とは、歯の硬さや厚さ、性質などのことです。歯の質が弱いと、虫歯菌の出す酸で歯が溶かされる可能性があるため、虫歯になるリスクが高まります。
歯並びが悪い人
歯並びが悪い人は、きちんと歯磨きをしていても磨き残しが生じやすいため、虫歯になりやすいといえます。磨き残しが増えると、虫歯菌が繁殖しやすくなるため、歯並びがよい人に比べると虫歯になるリスクが高まるのです。
そのため、歯並びが悪い人が虫歯予防をしたいなら、しっかり歯磨きをきちんとすることはもちろん、矯正治療を検討するのも選択肢のひとつです。
磨き残しが多い人
磨き残しが多いと虫歯菌が繫殖しやすくなるため、歯磨きが苦手な人や歯磨きする習慣がない人は虫歯になりやすいでしょう。
毎日歯磨きをしていても、プラークなどの汚れを落とせていなければ意味がありません。虫歯を予防するためには、歯磨きの回数よりも正しい方法で歯磨きをすることが大切です。
食生活が乱れている人
虫歯のなりやすさは、不規則な食生活によっても左右されます。以下に当てはまる場合、虫歯になりやすい人といえますので注意が必要です。
・甘いものをよく食べる
・食事の時間が決まっていない
・間食の回数が多い
・水やお茶の代わりにジュースをよく飲む
・よく噛まない・早食い
・アルコールをよく飲む
虫歯菌は糖分をエサにして繁殖するため、甘いものをよく食べる人は虫歯になりやすいといえます。食事の時間が決まっておらずダラダラと食事をする人や間食の回数が多い人、水やお茶のかわりにジュースやスポーツ飲料を飲む人も要注意です。
規則正しい食生活を送っていないことで、お口の中が酸性に傾くことが長くなると、虫歯になるリスクが高まるのです。
ダラダラと食事する人の反対で、よく噛まずに早食いの人も虫歯になりやすいといわれています。これは、よく噛まないことで唾液の分泌量が減り、お口の中に汚れが溜まりやすくなるからです。
また、アルコールには糖分が多く含まれるうえ、口内を乾燥させる作用があるため、アルコールをよく飲む習慣がある人も虫歯になりやすいでしょう。
口呼吸の人
口呼吸の人は、お口の中が乾燥しやすいため、虫歯になるリスクが高いです。また、口呼吸はお口周りの筋肉の衰えを招くことで、歯並びを悪化させる要因です。口呼吸は虫歯菌の繁殖を促し、口内環境の悪化も招くため、早急に対処する必要があるでしょう。
虫歯になりやすい人ができる対処法

ここでは、虫歯になりやすい人ができる5つの対処法を解説します。
規則正しい食生活を心がける
虫歯を予防するためには、規則正しい食生活を心がけることが大切です。具体的には、以下のことを心がけましょう。
・食事の時間を決める
・甘いものを摂りすぎない
・アルコールを控える
・食後は歯磨きもしくはうがいをする
・水分を摂る
ダラダラと食事を摂っていると、お口の中が酸性に傾く時間が長くなるため、虫歯になるリスクが高まります。特に、糖分を含む甘いものやジュースをよく摂る習慣がある人、アルコールをよく摂る人は要注意です。
間食を完全になくす必要はありませんが、食事や間食の時間は決めましょう。
甘いものやアルコールを口にしても、お口の中の汚れを洗い流せば虫歯のリスクを低減させることができます。できれば毎食後歯磨きすることが理想ですが、難しい場合はうがいをしましょう。
また、口内が乾燥すると虫歯になるリスクが高まるため、こまめに水やお茶で水分補給することも重要です。
歯磨きによるケア
虫歯を予防するためには、正しい方法で歯磨きをして磨き残しをできるだけなくすことが大切です。特に、歯ブラシが届きにくい歯と歯の間や歯と歯茎の境目、歯の重なりが大きい部分は磨き残しが生じやすいといわれています。
全体を歯ブラシで磨いたあとに、フロスや歯間ブラシ、タフトブラシを使用するとよいでしょう。
フッ素によるケア
フッ素には、歯の質を強化し、虫歯菌の働きを弱める効果があります。ふだんからフッ素入りの歯磨き粉やうがい薬、ジェルなどを使用することで、効率的に虫歯を予防できるでしょう。
口呼吸の改善
口呼吸の人は、意識的に口を閉じ、鼻で呼吸するように心がけましょう。口内の乾燥が防げると、虫歯リスクを低減できるはずです。
ただし、口呼吸の原因が鼻詰まりやアレルギーなど鼻疾患である場合は治療が必要になります。これらが原因で口呼吸になっている場合は、まずは耳鼻咽喉科を受診しましょう。
定期的なメンテナンス
虫歯を予防するためには、ご自宅でのケアに加え、定期的に歯科医院でメンテナンスを受けることが大切です。メンテナンスでは、歯のクリーニングを行います。クリーニングを受けることで、お口の中を清潔に保つことができ、虫歯の予防に効果的です。
お口全体の状態も確認してもらえるため、虫歯の早期発見にもつながります。また、患者様に合わせた歯磨き指導も行いますので、正しい歯磨き方法を習得できます。
虫歯初期の基本的な治療内容と費用

初期の虫歯は、歯の表面のエナメル質のみが溶かされた状態です。神経には達していないため、痛みなどはありません。
この段階の虫歯は範囲が狭いため、虫歯の部分を削り、レジンを詰める治療を行います。1回の治療で終わることが多く、費用は保険適用で1,500円〜3,000円程度です。
しかし、象牙質にまで虫歯が達している場合には、冷たいものがしみたり、噛むと痛みが出たりすることがあります。
象牙質にまで虫歯が進行した場合は、虫歯の部分を削り、詰め物で歯を修復する治療が必要になります。詰め物を詰めるまで2〜3回の通院が必要になり、費用は保険適用で3,000円〜1万円程度かかるのが一般的です。
重度の虫歯の基本的な治療内容と費用

重度の虫歯は、虫歯が神経にまで達している状態です。神経が炎症を起こすと、甘いものがしみたり、何もしなくてもズキズキと強い痛みが出たりします。この状態にまで進行すると、歯の神経を抜かなければ痛みはなくなりません。
麻酔をして虫歯部分を削り、炎症を起こした神経を除去してから根管内を洗浄・消毒する根管治療を行います。根管治療で根管内がきれいになったら、薬剤を詰めて土台を立て、その上に被せ物を装着して歯の機能を回復させます。
歯の根の中は複雑な形をしているため、1回の治療では終わらず、複数回の通院が必要です。平均的には3〜5回ほど通院する必要があるといわれていますが、根管治療を行っても症状が改善しない場合、治療が長期化することがあります。
特に、奥歯は歯根の本数が多いため、前歯よりも治療回数がかかるでしょう。根管治療は複数回の治療が必要になることにくわえ、土台を立てる治療も必要になるため、保険適用で1万〜2万円程度かかるのが一般的です。
まとめ

虫歯のなりやすさは、歯の質や生活習慣などによって左右されます。そのため、食生活が乱れている人や歯磨きが苦手な人、歯並びが悪い人などは虫歯になりやすいといえます。まずは、規則正しい食生活を心がけ、毎日の歯磨きで磨き残しをなくすことを心がけましょう。
また、定期的に歯科医院に通い、メンテナンスを受けることも大切です。仮に虫歯になってしまったとしても、早期に発見できれば簡単な治療で済み、費用も抑えられます。何も症状がなくても、約3〜6ヵ月に1回は検診を受けましょう。
虫歯にお悩みの方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2024.02.27更新
インビザライン矯正中に虫歯になったらどうしたらいい?対処法を解説
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

インビザライン矯正中は、何もしていない状態と比較すれば虫歯になるリスクが高いといわれています。インビザライン矯正中に虫歯になった場合、治療が計画通り続けられるのか不安に感じる方もいるかもしれません。
本記事では、インビザライン矯正中に虫歯になってしまった場合にはどうしたらいいのか、その対処法について解説します。
インビザラインとは?

インビザラインとは、透明なマウスピース型の矯正装置を装着して歯並びを整える矯正方法です。2006年に日本に上陸し、治療を受ける方が増加しています。2023年時点では世界で1,600万人以上の実績を誇ります。
インビザライン矯正の対象となる歯並び
インビザライン矯正の対象となる歯並びは、叢生(乱ぐい歯)や交叉咬合、下顎前突(受け口)、空隙歯列(すきっ歯)、過蓋咬合、開咬です。状態によっては該当していてもインビザライン矯正ができないこともありますが、多くの歯並びが対象となる治療法です。
インビザライン矯正の特徴
インビザライン矯正の最大の特徴は、取りはずしができることです。これまで日本で矯正治療の主流となっていたワイヤー矯正は、一度付けたら自分で取りはずしができません。
しかし、インビザライン矯正のマウスピースは簡単に取り外せます。歯のお手入れがしやすく、食事の際のストレスもありません。
また、インビザライン矯正のマウスピースは透明なため目立ちにくく、審美的な観点からも矯正治療の負担を軽くしています。
インビザライン矯正前に虫歯が見つかったら

インビザライン矯正前に虫歯が見つかった場合は、虫歯の治療を先に行ってから矯正治療に移ります。歯並びを放置していても悪化する可能性は低いものの、虫歯を放置していれば悪化していく可能性が高いです。
虫歯が悪化して歯を抜くことになった場合、せっかく作成したマウスピースを装着できなくなるでしょう。作り直しが必要になり、追加の費用もかかるかもしれません。
先に虫歯の治療をしておけば、虫歯の進行を気にすることなく治療を進められます。歯を削る範囲も少なくなるため、計画通りにインビザライン矯正を進められるでしょう。
インビザライン矯正と虫歯治療を同時に行う場合もありますが、矯正前に虫歯が見つかった場合ほとんどの歯科が虫歯治療を優先します。
インビザライン矯正中に虫歯になる原因

前述したように、インビザライン矯正のマウスピースは取りはずしが容易にできることから、食べ物が挟まりにくく歯磨きを丁寧にできます。そのため、ワイヤー矯正よりも虫歯にはなりくいでしょう。
ですが、完全に虫歯にならないわけではありません。インビザライン矯正中に虫歯ができる原因は、次の通りです。
マウスピースによって唾液が行き届かなくなる
インビザライン矯正では、1日20~22時間程度マウスピースを装着しなければなりません。マウスピースは歯をしっかりと動かすために、歯に密着するように作られています。
そのため、マウスピースの装着中は歯に唾液が届かなくなります。そもそも、歯は唾液の自浄作用によって汚れを洗い流しています。唾液が届かないと、自浄作用が低下するのです。
唾液には殺菌作用もあるので、唾液がうまく歯に届かないことで虫歯のリスクが高まります。
ケアが不十分
インビザライン矯正中には、主に2つのケアが重要となります。
1つは口腔内のケアです。マウスピースを長時間装着するため、唾液による自浄作用・殺菌作用を受けられなくなります。
虫歯を予防するためには、歯磨きが非常に重要です。インビザライン矯正によって徐々に歯並びが整ってきているとはいえ、まだ、歯に隙間があったり重なっていたりする部分があるでしょう。うまく歯磨きができないケースもあります。
もう1つはマウスピースのケアです。マウスピースが汚い状態のまま歯に装着し続けると、マウスピースないで細菌が繁殖して虫歯の原因になる可能性があります。
インビザライン矯正中に虫歯になったときは

インビザライン矯正中に虫歯になったときは、インビザライン矯正前と異なり、対処法にさまざまな選択肢があります。インビザライン矯正中に虫歯になったときの対処法は、次の通りです。
インビザライン矯正を中断して虫歯治療をする
インビザライン矯正を中断して虫歯の治療を優先するという選択肢です。もしも虫歯が悪化して歯を抜くことになった場合、せっかくインビザライン矯正で歯並びが整ったとしても、審美性が低下するでしょう。
治療を中断するためマウスピースは作り直しになる可能性が高いですが、治療後はインビザライン矯正がスムーズに進むでしょう。
インビザライン矯正と並行して虫歯治療をする
インビザライン矯正の場合、マウスピースを着脱できるので虫歯治療を一緒におこなえます。歯を抜くなど、歯並びが変わるような大きな治療はできませんが、少し削って詰め物をする程度の治療であれば可能です。
歯並びに大きな影響を及ぼすほど虫歯が進行している場合、この選択はできません。
応急処置のみをする
応急処置のみをして、インビザライン矯正を継続する方法もあります。虫歯の進行リスクが低く、インビザライン矯正が終わりに差しかかっている方限定の選択肢です。
インビザライン矯正が終了したら、すぐに虫歯治療をする必要があります。
インビザライン矯正中は虫歯予防が重要!
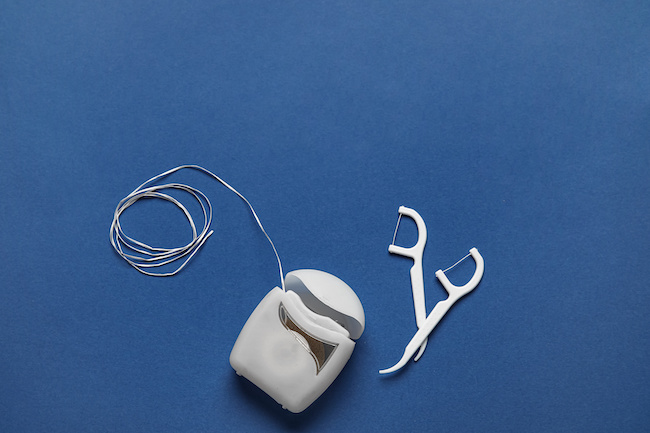
インビザライン矯正を予定通りに遂行するためには、虫歯予防が重要といえます。インビザライン矯正中に、とくに意識しておこなってほしい虫歯の予防方法は、次の通りです。
歯磨きをしっかりとおこなう
虫歯予防として最も効果があるのが歯磨きです。矯正前よりも意識して丁寧に歯磨きを行いましょう。
とくに、インビザライン矯正のときにアタッチメントを装着している場合は注意してください。アタッチメントの周りは汚れが溜まりやすいので、念入りに磨きましょう。
ブラッシングだけでなく、フロスや歯間ブラシ、洗口液も使用するとしっかりと汚れを落とせます。
歯磨きをするタイミングは、マウスピースを装着する前がベストです。きれいな歯でマウスピースをつければ、汚れのなかで繁殖した菌がマウスピース内で増殖することはありません。虫歯のリスクを低減できるでしょう。
マウスピースを清潔にする
歯だけでなくマウスピースも清潔にしておきましょう。マウスピースに汚れが溜まっている状態だと、汚れに付着した菌がマウスピースのなかで繁殖してしまいます。
マウスピースは水やぬるま湯で汚れを落としてから、ブラッシングをして丁寧にすすぎ、よく乾燥させましょう。週に2〜3回、マウスピース専用の洗浄剤を使用するとより清潔に保てます。
マウスピースをつけたまま飲食しない
食事や飲水の際にはマウスピースを外さなければなりません。飲み物を飲むだけの場合や、食べ歩きしている場合、外食する場合など、マウスピースを外さずに飲食したいこともあるかもしれません。
マウスピースをつけたまま飲食をすると、マウスピースと歯の間に食べ物や飲み物の糖分が入り込み、虫歯のリスクを高めます。虫歯予防のためにも、マウスピースをつけたままの飲食は控えましょう。
水分を摂取する
インビザライン矯正中は、口のなかが乾燥しやすいといわれています。唾液の分泌量が低下している状態のため、虫歯菌が繁殖しやすいでしょう。そのため、こまめに水分を摂って口の中の乾燥を予防することが重要です。
ただし、糖が含まれている飲み物は避けてください。
まとめ

インビザライン矯正中は、ワイヤー矯正ほどではないものの虫歯になるリスクがあります。そのため、インビザライン矯正中は虫歯予防をしっかりとおこないましょう。
インビザライン矯正中に虫歯になった場合は治療を中断しなければならない可能性があります。軽度な虫歯であれば少し処置をしてインビザライン矯正を継続できることもありますが、重度の虫歯の場合は矯正を中断することが多いです。
虫歯の治療で歯を抜いたり削ったりすると、最初に作っていたマウスピースを装着できなくなるでしょう。作り直しが必要になり、費用や時間がかかってしまいます。
インビザライン矯正を検討されている方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
投稿者:
- 1
- 2

ARTICLE
SEARCH
ARCHIVE
CATEGORY
- CAD/CAM冠
- IPR
- MTM
- インビザライン
- インビザライン・エクスプレス
- インビザライン・コンプリヘンシブ
- インビザライン・モデラート
- インビザライン・ライト
- インビザライン矯正
- インプラント治療
- オールセラミック
- カウンセリング
- ジルコニア
- ジルコニアセラミック
- セラミック
- セラミック歯
- セラミック治療
- デメリット
- デンタルローン
- ハイブリッドセラミック
- ブラケット
- ブリッジ
- ホワイトニング
- マウスピース
- マウスピース型
- マウスピース矯正
- メタルタトゥー
- メタルボンド
- メリット
- メンテナンス
- ラミネートベニア
- リスク
- ワイヤー
- ワイヤー矯正
- 予防歯科
- 二酸化ジルコニウム
- 人工ダイヤモンド
- 仮歯
- 保定期間
- 保険適用
- 健康保険
- 入れ歯
- 全体矯正
- 出っ歯
- 前歯
- 医療費控除
- 受け口
- 口腔外科
- 噛み合わせ
- 噛み合わせ治療
- 嚙み合わせ
- 外科治療
- 天然歯
- 失敗
- 奥歯
- 定期検診
- 定期診察
- 審美
- 審美性
- 小児歯科
- 抜歯
- 歯ぎしり
- 歯並び
- 歯列矯正
- 歯周病
- 歯周病菌
- 歯型
- 歯科技工士
- 歯科検診
- 歯科矯正
- 歯茎
- 治療期間
- 症例
- 矯正期間
- 矯正歯科
- 矯正装置
- 精密検査
- 自由診療
- 自費診療
- 虫歯
- 虫歯治療
- 虫歯菌
- 被せ物
- 親知らず
- 詰め物
- 費用
- 通院
- 通院頻度
- 部分入れ歯
- 部分矯正
- 金属
- 金属アレルギー
- 銀歯
- 顎関節症
- 食いしばり