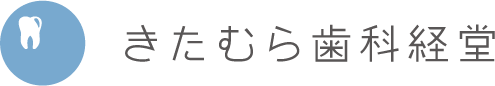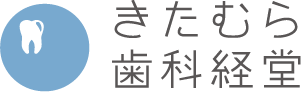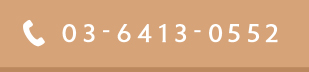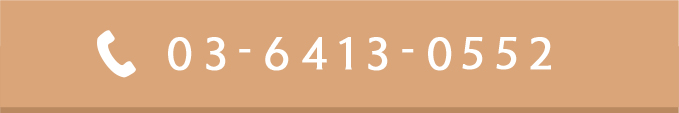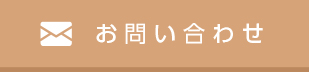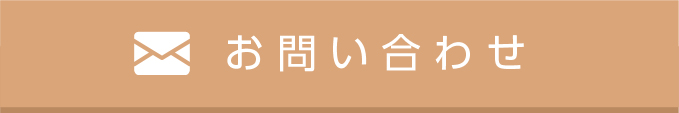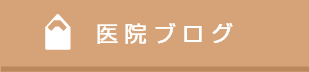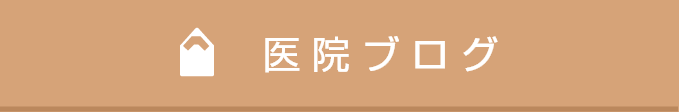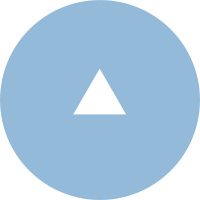2025.09.16更新
歯の噛み合わせに違和感を感じる!その原因とセルフチェック・治療法
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

食事のときや、ふと口を閉じたときに「なんだか噛み合わせがしっくりこない」と感じたことはありませんか。
その小さな違和感は、お口のバランスが崩れているサインかもしれません。噛み合わせのずれは、放置すると歯や顎に負担をかけ、虫歯や歯周病のリスクを高めるだけでなく、頭痛や肩こりといった全身の不調につながることもあります。
この記事では、歯の噛み合わせに違和感が生じる主な原因と、ご自身でできる対策、そして歯科医院での治療法について詳しく解説します。我慢せずに不快感を解消したい方は、ぜひ参考にしてください。
歯の噛み合わせに違和感を感じる

まず歯の噛み合わせに違和感を感じるとは、どのような状態や症状を指すのかについて詳しく解説します。
噛み合わせとは
噛み合わせとは、上下の歯が口を閉じたときにどのように接触するかを示す言葉です。健康な噛み合わせでは、上下の歯がバランスよく接触し、食べ物を効率よく噛むことができます。
また、噛み合わせは顎の関節や筋肉とも密接に関係しており、全体のバランスが取れていることが重要です。
日常生活の中で無意識に行われる動作ですが、歯並びや顎の位置、歯の高さなどが少しでも乱れると、噛み合わせに違和感を感じることがあります。
違和感を感じる主な症状と例
噛み合わせに違和感を感じる場合、具体的には以下のような症状がみられます。
- 上下の歯がうまく合わない
- 食事中に片側だけで噛んでしまう
- 歯が浮いたような感覚がある
- 顎が疲れやすい
- 口を開け閉めすると音がする
また、歯科治療後に詰め物や被せ物が高く感じる、歯がしみる、顎や頭に痛みを感じるといったケースもあります。
歯の噛み合わせに違和感が生じる主な原因

歯の噛み合わせに違和感を感じる場合、その背景にはさまざまな原因が考えられます。
虫歯や歯周病による噛み合わせの変化
虫歯や歯周病が進行すると、歯が移動したり、歯ぐきが下がったりして噛み合わせが変化することがあります。
特に歯周病による歯の揺れや歯の位置の変化は、違和感の大きな要因となります。
詰め物・被せ物・インプラントの不適合
治療後の詰め物や被せ物、インプラントが歯列や噛み合わせに合っていない場合、違和感や痛みが生じることがあります。
歯ぎしり・食いしばり・ストレスの影響
無意識のうちに歯ぎしりや食いしばりをしていると、歯や顎に負担がかかり、噛み合わせに不快感を覚えることがあります。
ストレスが原因となることも少なくありません。
歯の摩耗や損傷
加齢や強い力が加わることで歯がすり減ったり、欠けたりすると、噛み合わせのバランスが崩れ違和感を感じることがあります。
抜歯や歯列の変化
抜歯後に隣接する歯が動いたり、歯並びが変化したりすることでも噛み合わせに違和感を感じることがあります。特に放置するとさらに悪化する場合もあるため注意が必要です。
顎関節症や生活習慣の変化
顎関節症や姿勢の変化、食生活の変化なども噛み合わせに影響を与えることがあります。
噛み合わせの違和感を自分でチェックする方法

噛み合わせの違和感を感じたとき、自分でできるセルフチェックの方法について解説します。
日常生活で気をつけたいチェックポイント
日常生活の中で噛み合わせの違和感を見逃さないためには、歯を閉じたときに上下の歯が均等に当たっているか、特定の歯だけが強く当たっていないかを意識してみましょう。
また、食事の際に片側だけで噛む癖がないか、発音や会話中に違和感がないかも確認することが大切です。これらを日常的に意識することで、違和感の早期発見につながります。
朝起きた時や食事中の違和感の確認
朝起きたときに顎や歯に疲れを感じたり、食事中に噛みにくさや痛みを覚える場合は、噛み合わせに問題がある可能性があります。
特に、朝の顎のこわばりや、食事の際に特定の部位だけが痛む場合は注意が必要です。
痛みや不快感の記録方法
噛み合わせの違和感や痛み、不快感を感じたタイミングや状況を、日記やスマートフォンのメモなどに記録しておくと、歯科受診時に症状を正確に伝えやすくなります。
記録する際は、痛みの強さや発生した時間帯、どの歯や部位に感じたかなどを具体的に記載すると、診断や治療の参考になります。
噛み合わせの違和感を放置するリスク

噛み合わせの違和感をそのままにしておくと、口腔内だけでなく全身の健康にもさまざまな影響を及ぼす可能性があります。
虫歯・歯周病の悪化リスク
噛み合わせに違和感があると、特定の歯に過剰な力がかかりやすくなります。
その結果、歯と歯の間に隙間ができたり、歯磨きがしにくくなったりすることで、プラークや歯石が着きやすくなります
これにより、虫歯や歯周病が進行しやすくなるため、早めの対応が大切です。
顎関節症や肩こり・頭痛など全身への影響
噛み合わせの不調和は、顎の関節や筋肉に負担をかけることがあります。
これが続くと、顎関節症を引き起こしたり、首や肩の筋肉が緊張しやすくなり、肩こりや頭痛などの全身症状につながることも考えられます。
歯の破損や見た目の変化
噛み合わせの違和感を放置すると、一部の歯に過度な力が集中し、歯が欠けたり摩耗したりすることがあります。
また、歯並びが徐々に崩れることで、見た目にも変化が現れる場合があります。
こうした変化は、機能面だけでなく審美面にも影響を与えるため、早期の相談が望ましいでしょう。
自宅でできる噛み合わせの違和感への対策

歯の噛み合わせに違和感を感じたとき、自宅でできる対策にはどのようなものがあるのか、具体的に解説します。
セルフケアや生活習慣の見直し
噛み合わせの違和感を感じた場合、まずは日常生活の中で無意識に歯を食いしばっていないか、片側だけで噛む癖がないかを意識してみましょう。
また、硬い食べ物を避けて顎への負担を減らすことや、歯磨きの際に優しく丁寧にケアすることも大切です。
寝る前にリラックスした状態で顎の筋肉を軽くマッサージするのも、筋肉の緊張を和らげる一助となります。
ストレスマネジメントの方法
ストレスは無意識の歯ぎしりや食いしばりの原因となることがあります。
深呼吸や軽いストレッチ、趣味の時間を持つなど、日常的にストレスを溜め込まない工夫を意識してみましょう。
また、十分な睡眠を確保することも顎や全身の緊張緩和につながります。
応急処置のポイント
突然、噛み合わせに違和感が生じた場合は無理に噛み合わせを調整しようとせず、安静を心がけましょう。
痛みや腫れがある場合は、冷たいタオルで軽く冷やすことが一時的な対策となります。
歯科医院で受けられる噛み合わせの治療法

歯の噛み合わせに違和感がある場合、歯科医院ではさまざまな治療法を提供しています。
歯列矯正や詰め物・被せ物の調整
歯並びや噛み合わせのずれが原因の場合、歯列矯正によって歯を理想的な位置に動かす方法や、詰め物・被せ物の高さや形を調整することで噛み合わせを改善する治療が行われます。
矯正治療はワイヤーやマウスピースを用いることが多く、詰め物や被せ物の調整は比較的短時間で終わることもあります。
咬合調整やスプリント療法
歯の噛み合わせ面を少しずつ削る咬合調整や、マウスピース型の装置(スプリント)を装着し、顎や筋肉への負担を軽減する治療も選択肢です。
これらは主に顎関節症や慢性的な違和感に対して用いられ、症状や原因に応じて適切な治療方法が変わります。
虫歯・歯周病治療とインプラント治療
虫歯や歯周病が噛み合わせの違和感の原因となっている場合は、まずそれらの治療が優先されます。
また、歯を失った場合にはインプラントやブリッジ、入れ歯による補綴治療で噛み合わせを回復することも可能です。
治療費や期間の目安
治療法によって費用や期間は大きく異なります。
矯正治療は約60万円から150万円程度、期間も2〜3年かかることが多いですが、詰め物や被せ物の調整、咬合調整は比較的短期間・低コストで済む場合もあります。
噛み合わせの違和感があるときに歯科医院を受診するタイミング

噛み合わせに違和感を覚えた際、どのようなタイミングで歯科医院を受診すべきかについて解説します。
受診を判断する具体的な基準
噛み合わせの違和感が一時的なものか、数日から1週間以上続くかどうかが受診の目安となります。例えば、食事や会話の際に歯が当たる感覚が続いたり、顎やこめかみに軽い痛みや疲労感を感じたりする場合は、早めの受診が推奨されます。
また、歯が浮いた感じや、噛むたびに歯がずれるような感覚がある場合も注意が必要です。違和感が軽度であっても、日常生活に支障をきたす場合や、症状が徐々に強くなっている場合は、自己判断せずに歯科医師に相談することが大切です。
治療後に気をつけたい噛み合わせの管理と再発予防

歯の噛み合わせ治療後は、違和感の改善だけでなく、再発を防ぐためのセルフケアがとても重要です。
治療後のセルフケアと定期的なチェック
例えば、歯磨きやデンタルフロスを使った丁寧な口腔ケアは、歯や歯ぐきの健康維持に役立ちます。
また、噛み合わせの変化がある場合は、早めに歯科医院で相談しましょう。
定期的な歯科検診を受けることで、噛み合わせの微妙なズレやトラブルを早期に発見し、必要に応じた調整を受けることができます。
これにより、再発リスクを抑えやすくなります。
再発を防ぐための生活習慣のポイント
噛み合わせのトラブルを再発させないためには、日常生活での注意も欠かせません。
無意識の歯ぎしりや食いしばりは、噛み合わせに負担をかける要因となるため、就寝時のマウスピースを装着することも一つの方法です。
また、硬い食べ物や片側だけで噛む癖を避け、バランス良く食事を摂ることも大切です。
ストレスを溜め込まないことや、正しい姿勢を意識することも、噛み合わせの安定に役立つと考えられています。
まとめ

歯の噛み合わせに違和感を覚える場合、虫歯や歯周病、歯ぎしり、詰め物の不具合などさまざまな原因が考えられます。
自分で鏡を使ったチェックや、指で軽く押してみる方法もありますが、違和感を放置すると顎関節や全身の健康に影響することもあるとされています。
自宅でのケアや生活習慣の見直しも大切ですが、症状が続く場合は早めに歯科医院で相談することが勧められています。
噛み合わせの治療を検討されている方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2025.06.24更新
噛み合わせの治療にはいくらかかる?治療法ごとの費用を解説
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

「噛み合わせが悪い」と感じていても、具体的にどんな治療が必要なのか、また費用がどのくらいかかるのかが分からず、不安に思う方も多いでしょう。噛み合わせの悪さは、顎や肩の痛み、頭痛、食事のしづらさといったさまざまな不調の原因になることがあります。
症状の程度や原因によって治療法は異なり、治療法によって費用も大きく変わります。
この記事では、噛み合わせ治療の主な方法と、それぞれの費用の目安について分かりやすく解説します。
噛み合わせを治療する方法とそれぞれの費用

噛み合わせの乱れは、虫歯や歯周病だけでなく、顎関節症や肩こり、頭痛などの全身症状にも関係するといわれています。こうしたトラブルを未然に防ぐためには、原因に合わせた適切な治療が欠かせません。
ここでは、主に行われている噛み合わせ治療の方法と、それぞれにかかる費用の目安について解説します。
スプリント治療
スプリント治療は、透明なマウスピースのような装置を就寝時に装着することで、顎の位置を安定させたり、歯ぎしりや食いしばりによる負担を軽減したりする方法です。軽度の噛み合わせのズレに用いられることが多く、体への負担も少ない点が特徴です。
費用は保険適用であれば約5,000円前後、自費診療では3万円から5万円程度が相場とされています。顎関節症の治療を目的とする場合は、保険が適用されるケースがあります。
矯正治療
歯並びの乱れや顎の骨格に起因する噛み合わせの問題には、矯正治療が選択されます。ワイヤーを使った一般的な矯正のほか、近年では透明なマウスピース矯正も普及しています。歯列全体を整えることで、自然な噛み合わせへと導きます。
費用は自費診療となるため高額になりやすく、全体矯正であれば70万円〜120万円程度、部分的な矯正でも20万円〜40万円程度が目安です。マウスピース型矯正は装置の枚数や治療期間に応じて変動しますが、一般的には80万円前後になることが多いです。
補綴治療(被せ物・詰め物による調整)
噛み合わせの不具合が、詰め物や被せ物の高さや形状によるものであれば、補綴治療によって調整することが可能です。過去の治療で作られた人工物が原因となっている場合、その部分を作り直すことで改善が期待できます。
費用は使用する素材によって大きく異なり、保険適用の銀歯であれば数千円程度、自費のセラミックなどを選択すると1本あたり5万円〜15万円程度になることもあります。審美性や耐久性を重視する場合は、自費治療を選ぶ方が多いです。
咬合調整
歯の表面をわずかに削り、高さの微調整を行うことで噛み合わせを整える方法が咬合調整です。特に、治療した歯が他の歯よりも高くなっている場合などに有効とされています。施術は短時間の場合が多く、即効性があるのも特長です。
費用については、保険適用で数百円〜数千円程度、自費診療の場合は5,000円〜1万円程度が一般的です。
ただし、繰り返し調整が必要になるケースもあります。歯科医師の指示に従って継続的に受診することが大切です。
インプラント治療を併用する
歯を失ったことで噛み合わせのバランスが崩れている場合には、インプラントを用いた治療が選ばれるケースもあります。人工歯根を顎の骨に埋め込み、上部構造を装着することで、自然な噛み合わせを回復します。
インプラント治療は自費診療となり、1本あたり30万円〜50万円程度が一般的です。また、補綴物の素材や骨造成の有無によっては、さらに費用がかかる場合があります。
噛み合わせの治療に保険は適用される?

噛み合わせの治療は、目的や治療内容によって保険が適用されるかどうかが異なります。たとえば、スプリント治療や咬合調整など、顎関節症や痛みの改善を目的とした治療であれば、医師の診断のもとで保険が適用されることがあります。
一方で、見た目を整えるための矯正治療は、原則として自費診療になります。重度の噛み合わせ異常や先天的な顎の変形と診断された場合には、厚生労働省が定める施設での治療に限り、保険が適用されるケースもあります。
適用条件は厳密に決められているため、事前に歯科医師とよく相談することが大切です。
噛み合わせの治療にかかった費用は医療費控除の対象?
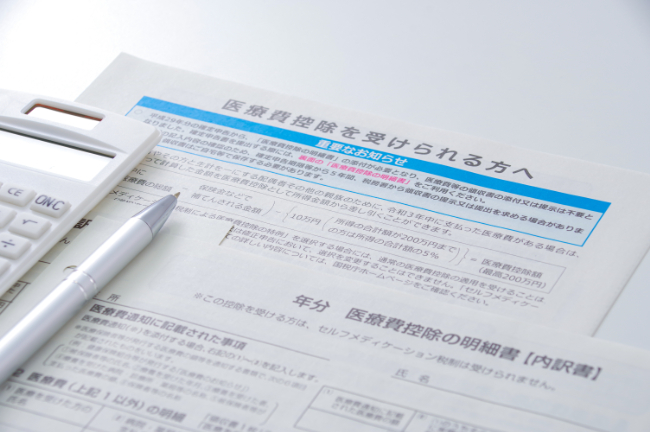
噛み合わせの治療費が医療費控除の対象になるかどうかは、治療の目的によって判断されます。噛み合わせの異常によって食事や発音に支障が出ているなど、機能改善を目的とした治療であれば、医療費控除の対象として認められる可能性があります。
たとえば、顎関節症の治療や成長期の子どもに対する矯正などが該当します。
一方で、審美目的の矯正や見た目を良くするためだけの治療は、医療費控除の対象外とされます。判断に迷う場合は、治療前に歯科医師に確認してみましょう。
噛み合わせが悪いまま放置するリスク

噛み合わせの乱れは、見た目や食べにくさといった表面的な問題だけにとどまらず、全身のさまざまな不調を引き起こす原因となることがあります。ここでは、噛み合わせが悪いままの状態を放置することで生じるリスクについて詳しく解説します。
虫歯や歯周病のリスクが高まる
噛み合わせが乱れていると、食べ物のかすがたまりやすく、歯ブラシが届きにくい部分が生じます。その結果、清掃が不十分となり、プラークや歯石が蓄積しやすくなります。これが原因となって虫歯や歯周病が発症・悪化しやすくなるのです。
また、噛む力が一部の歯に集中して加わることで、歯の摩耗が進み、詰め物や被せ物が壊れやすくなるケースも見られます。日常的なケアをしっかり行っていたとしても、噛み合わせに問題がある限り、トラブルを繰り返す可能性があるため注意が必要です。
顎関節や筋肉への負担が蓄積する
噛み合わせのズレは、顎の動きや筋肉のバランスにも影響します。上下の歯が正しくかみ合わない状態では、咀嚼運動のたびに顎の関節に余計な負担がかかり、長期間にわたって続くと顎関節症へとつながるおそれがあります。
具体的には、口を開けるときに音が鳴る、顎が痛む、スムーズに開閉できないなどの症状が現れることがあります。加えて、噛む筋肉が常に緊張状態になることで、慢性的な肩こりや首のこり、頭痛を引き起こすケースも少なくありません。
見た目や発音に影響を及ぼすこともある
噛み合わせの状態は、顔の印象や輪郭にも影響を与えることがあります。歯並びが乱れていると口元が出て見えたり、顎が左右非対称になったりすることがあり、これがコンプレックスの原因になるのです。
また、前歯がかみ合っていない開咬と呼ばれる状態では、発音が不明瞭になる場合があり、会話の際に支障が出ることもあります。仕事や接客などで人と話す機会が多い方にとっては、社会的なストレスの一因となりかねません。
消化機能にも影響を及ぼすおそれがある
通常、しっかりと噛んで食べ物を細かくすることで、消化器官への負担を軽減しています。
しかし、噛み合わせが悪いと噛む力が不十分になり、十分に咀嚼されないまま飲み込んでしまうことが増えます。その結果、胃腸にかかる負担が大きくなり、消化不良や胃もたれなどを引き起こすかもしれません。
特に高齢の方や持病を抱える方にとっては、こうした影響が体全体の健康に直結する可能性があります。
心理的なストレスや生活の質の低下
噛み合わせの問題は、見た目や発音、痛みや違和感などを通して、心理的なストレスを生み出すことがあります。食事が楽しめなかったり、人前で話すのが億劫になったりすることで、日常生活の質が下がる可能性もあるでしょう。
また、慢性的な痛みや不調を抱えながら生活を続けることは、精神的な疲労にもつながりやすいです。気づかないうちに心身に負担をかけていることもあるのです。
長期的には全身の健康状態にも影響する
噛み合わせの不調が引き起こす影響は、局所的なものにとどまりません。顎関節や筋肉への負担が全身の姿勢バランスに影響し、結果として背骨や骨盤の歪みにつながることもあります。
これが足腰の痛みやしびれを引き起こすこともあり、単なる口腔内の問題では済まされない状況に陥る可能性もあります。
まとめ

噛み合わせの治療には、スプリント療法や咬合調整といった負担の少ない方法から、矯正治療やインプラントのように費用が高額になるケースまで幅広い選択肢があります。治療の目的や歯の状態によって方法は異なり、費用も大きく変わってきます。
保険が適用される治療もあるため、自己判断で放置せず、まずは歯科医師に相談することが大切です。
噛み合わせの乱れを放置すると、口腔内のトラブルや全身の不調にもつながるおそれがあります。違和感を抱えている方は早めに専門の診察を受け、将来の健康へのリスクを減らす一歩を踏み出しましょう。
噛み合わせの治療を検討されている方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2024.11.26更新
噛み合わせが悪い原因とは?症状や治療法も併せて解説
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

噛み合わせや歯並びが悪いと、見た目が気になるという方が多いのではないでしょうか。悪い噛み合わせは見た目だけでなく、口腔内や全身に悪い影響を与える可能性があります。では、どうして噛み合わせが悪くなるのでしょうか。
今回は、噛み合わせが悪くなる原因や症状、治療法などについて解説します。噛み合わせや歯並びが気になっている方は、ぜひ参考にしてください。
噛み合わせが悪い状態(不正咬合)とは

噛み合わせが悪い状態のことを不正咬合といいます。不正咬合にはいくつかの種類があり、それぞれ原因や起こり得る影響が異なります。ここでは、不正咬合の6つの種類とそれぞれの特徴について解説します。
叢生(そうせい)
叢生とは、歯が一定の向きに生えずに歯列の一部に凹凸がみられたり、重なり合ったりしている状態のことを指します。
叢生は、おもに顎の大きさと歯の大きさのバランスが悪いことや、骨格的な問題により歯が十分に生え揃うためのスペースが確保できないことが原因で引き起こされます。叢生は日本人の不正咬合のなかで最も高い割合を占めるといわれており、八重歯も叢生の一種です。
空隙歯列(くうげきしれつ)
空隙歯列とは、歯と歯の間にすき間が空いている状態のことで、すきっ歯とも呼ばれます。
空隙歯列は、顎の大きさに比べて歯のサイズが小さいことや先天的な歯の本数の不足などが原因で生じます。すきっ歯の状態になると、タ行やサ行の発音がしにくくなったり歯のすき間に汚れが蓄積しやすくなったりするでしょう。
上顎前突(じょうがくぜんとつ)
上顎前突とは、上の前歯や上顎全体が前方に突き出した状態のことをいいます。いわゆる出っ歯のことです。
上顎前突では口が閉じにくくなるため口呼吸やドライマウスが引き起こされ、虫歯や歯周病のリスクが高まります。また、口元が出っ張っていると人目に触れやすいため、見た目にコンプレックスを抱きやすいです。
上顎前突は遺伝的な要因によって引き起こされることもありますが、指しゃぶりや舌癖などの後天的な要因によって生じることも考えられるでしょう。
下顎前突(かがくぜんとつ)
下顎前突は、下の前歯や下顎全体が前方に突き出している状態のことで、受け口や反対咬合とも呼ばれます。
下顎前突では、咀嚼機能が低下したりサ行の発音に影響が出たりすることが考えられるでしょう。下顎前突の原因としては、遺伝的な要因のほかに、舌癖や口呼吸などの後天的な要因が挙げられます。
開咬(かいこう)
開咬とは、奥歯を噛み合わせたときに前歯が噛み合わずに、常に開いた状態になることを指し、オープンバイトとも呼ばれます。
オープンバイトでは前歯が噛み合わないため、前歯で食べ物を噛み切ることが難しくなります。そのため、奥歯に過度な負担がかかりやすいです。また、口が常に開いた状態になるため、口の中が乾燥しやすくなったり滑舌に影響が出たりすることも考えられるでしょう。
開咬の原因としては、哺乳瓶やおしゃぶりの長時間使用、指しゃぶりなどが挙げられます。
過蓋咬合(かがいこうごう)
過蓋咬合とは、上下の歯の噛み合わせが深い状態のことで、ディープバイトとも呼ばれます。
過蓋咬合では、歯を噛み合わせたときに上の歯列が下の歯列を覆い隠すような状態になります。このような状態では、前歯で食べ物を噛み切りにくくなります。また、虫歯や歯周病、顎関節症のリスクも高まるでしょう。
過蓋咬合の原因はさまざまですが、上顎と下顎の大きさのバランスが悪いことなどが挙げられます。
噛み合わせが悪くなる原因

では、なぜ噛み合わせが悪くなるのでしょうか。以下では、噛み合わせが悪くなるおもな原因についてみていきましょう。
骨格などの遺伝によるもの
不正咬合は顎の大きさや歯の大きさのバランスの悪さによって引き起こされることが多いといわれています。例えば、両親のどちらかまたは、両方が受け口の場合には、子どもも受け口になる可能性が高くなります。
骨格や歯並びは親から子へ必ず遺伝するというわけではありませんが、両親どちらかまたは両方に不正咬合がある場合には、早い段階から経過観察をすることが望ましいでしょう。
生活習慣によるもの
不正咬合は顎や口に継続的に力が加わるような生活習慣が原因で引き起こされることもあります。具体的には、頬杖・舌癖・口呼吸・片方だけで噛む癖・うつぶせ寝・歯ぎしり・食いしばりなどです。普段からこのような癖がある方は不正咬合を引き起こしやすくなります。
また、たとえ矯正治療で歯並びが改善しても生活習慣自体が改善されなければ、再び不正咬合が引き起こされるリスクがあります。
永久歯が抜けたことによるもの
ケガや虫歯など何らかの原因によって歯が抜け、そのまま放置すると次第に歯並びが乱れることがあります。その結果、不正咬合が引き起こされることも考えられますので、永久歯を失った場合には早めに歯を補う治療を受けることが大切です。
歯周病による影響
歯周病も噛み合わせが悪くなる原因のひとつです。歯周病を放置していると歯を支える歯ぐきの力が弱くなり、舌の圧力などで噛み合わせに影響が及ぶことが考えられます。
噛み合わせが悪いと出る症状

悪い噛み合わせは、口腔内だけでなく、全身にも影響を与えることがあります。ここからは、噛み合わせが悪いことで現れる症状について解説します。
虫歯や歯周病
噛み合わせが悪いと歯磨きがしにくくなるため、汚れや歯垢が溜まりやすくなります。その結果、虫歯や歯周病になるリスクが高まるでしょう。
顎関節症
不正咬合の状態では、噛んだときに顎にかかる力が偏りやすくなります。その結果、顎関節に過度な負担がかかり、顎関節症を発症するリスクも高くなります。
頭痛・肩こり・腰痛
噛み合わせが悪く、口周りの筋肉に負担がかかると、頭痛や肩こり、腰痛を引き起こすことも考えられるでしょう。
顔のゆがみ
噛み合わせが悪いと左右の顎のバランスや顎周りの筋肉のバランスが悪くなることがあります。その結果、顔がゆがんだり左右非対称になったりすることがあるでしょう。
胃腸への負担
不正咬合の状態では食べ物をうまく噛み切ることができず、咀嚼不十分な状態で胃に運ばれることが考えられます。それにより、胃腸への負担がかかることもあるでしょう。
歯ぎしりや食いしばり
歯ぎしりや食いしばりが不正咬合を引き起こすこともありますが、不正咬合によって歯ぎしりや食いしばりが引き起こされることもあります。また、歯ぎしりや食いしばりをすることで、歯の擦り減りやひび割れ、歯や顎の痛みなどが生じることもあるでしょう。
噛み合わせを良くする治療法

噛み合わせを改善するための治療法としては、矯正治療と生活習慣の改善が挙げられます。ここでは、それぞれの治療法について解説します。
矯正治療
矯正治療の方法には、おもに以下の3つがあります。
ワイヤー矯正
ワイヤー矯正とは歯に直接装置を装着し、ワイヤーを通して歯並びを整える方法のことです。
ワイヤー矯正には歯の表側に装置を装着する表側矯正と歯の裏側に装置を装着する裏側矯正があります。裏側矯正であれば、装置が目立ちにくいため見た目が気になる方でも受け入れやすいでしょう。
ワイヤー矯正は、歯に強い力をかけられるため重度の症例にも対応できます。
マウスピース矯正
マウスピース矯正とは、透明なマウスピースを装着し、1週間~2週間に1回の頻度で交換しながら、少しずつ歯列を整えていく方法のことです。食事や口腔ケアの際には取り外しができるという特徴があります。
ただし、マウスピース矯正はすべての症例に対応できるわけではありません。歯を大きく移動させる必要がある場合には適応とならない可能性があります。
外科的矯正
骨格的な問題により一般的な矯正治療のみでは対応できない場合には、顎の骨を整えるための手術と矯正治療を組み合わせて行います。外科的矯正は、おもに顎変形症と診断された場合に適応されます。
生活習慣の改善
不正咬合を改善するためには、噛み合わせに悪い影響を及ぼすような生活習慣を改善することも重要です。舌癖や頬杖をつく癖など顎に負担がかかる習慣がある方は、できるだけ早い段階で改善しましょう。
まとめ

噛み合わせが悪いと、見た目にコンプレックスを抱きやすいだけでなく、虫歯や歯周病などのリスクも高まります。場合によっては、頭痛や肩こりなど口腔内以外にも症状が及ぶこともあるでしょう。
噛み合わせに違和感がある方や顎に不調を感じている方は、放置せずに歯科医院へご相談ください。
噛み合わせが悪いことにお悩みの方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
ARTICLE
SEARCH
ARCHIVE
CATEGORY
- CAD/CAM冠
- IPR
- MTM
- インビザライン
- インビザライン・エクスプレス
- インビザライン・コンプリヘンシブ
- インビザライン・モデラート
- インビザライン・ライト
- インビザライン矯正
- インプラント治療
- オールセラミック
- カウンセリング
- ジルコニア
- ジルコニアセラミック
- セラミック
- セラミック歯
- セラミック治療
- デメリット
- デンタルローン
- ハイブリッドセラミック
- ブラケット
- ブリッジ
- ホワイトニング
- マウスピース
- マウスピース型
- マウスピース矯正
- メタルタトゥー
- メタルボンド
- メリット
- メンテナンス
- ラミネートベニア
- リスク
- ワイヤー
- ワイヤー矯正
- 予防歯科
- 二酸化ジルコニウム
- 人工ダイヤモンド
- 仮歯
- 保定期間
- 保険適用
- 健康保険
- 入れ歯
- 全体矯正
- 出っ歯
- 前歯
- 医療費控除
- 受け口
- 口腔外科
- 噛み合わせ
- 噛み合わせ治療
- 嚙み合わせ
- 外科治療
- 天然歯
- 失敗
- 奥歯
- 定期検診
- 定期診察
- 審美
- 審美性
- 小児歯科
- 抜歯
- 歯ぎしり
- 歯並び
- 歯列矯正
- 歯周病
- 歯周病菌
- 歯型
- 歯科技工士
- 歯科検診
- 歯科矯正
- 歯茎
- 治療期間
- 症例
- 矯正期間
- 矯正歯科
- 矯正装置
- 精密検査
- 自由診療
- 自費診療
- 虫歯
- 虫歯治療
- 虫歯菌
- 被せ物
- 親知らず
- 詰め物
- 費用
- 通院
- 通院頻度
- 部分入れ歯
- 部分矯正
- 金属
- 金属アレルギー
- 銀歯
- 顎関節症
- 食いしばり