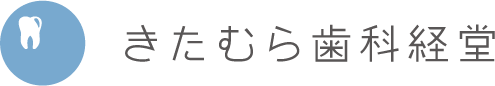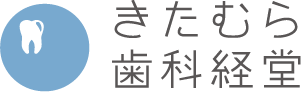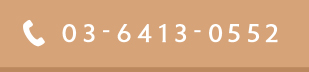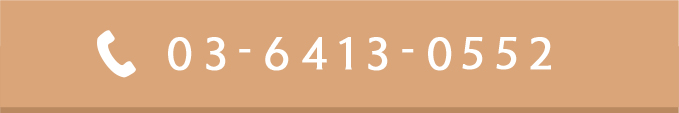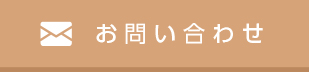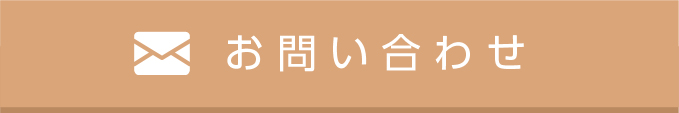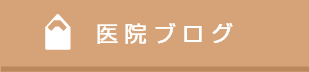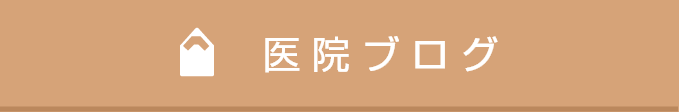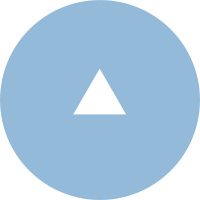2025.09.30更新
子どもとフッ素:メリット・注意点や安全な使い方を解説
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

子どもの歯の健康を守りたいと考える保護者の方は多いでしょう。虫歯は進行すると痛みだけでなく、治療に時間や費用がかかるため、予防することが非常に重要です。
そのようななかで、注目されているのがフッ素の活用です。特に子どもの虫歯を予防するためには、日常生活のなかでフッ素を上手に取り入れることが効果的だとされています。
しかし「フッ素は安全なの?」「どのように使えばいいの?」といった疑問を持つ保護者の方も多いのではないでしょうか。
今回は、フッ素の基礎知識から子どもへの具体的な活用方法、注意点、そして歯科医院でのフッ素塗布の費用について解説します。子どもの将来の歯の健康を守るために、ぜひ参考にしてください。
フッ素とは

フッ素とは、自然界に広く分布する元素の一つで、私たちの体の中にも存在しています。歯や骨の構成にも関わる重要なミネラルであり、歯科分野ではフッ化物として虫歯予防に活用されています。
特に歯の表面を強化する効果があるため、お子さんの成長期の口腔ケアに欠かせない存在となっています。
フッ素の効果
フッ素には主に以下の3つの効果があります。
1つ目は、再石灰化の促進です。日常の飲食により歯の表面が酸で溶かされても、フッ素の働きによって唾液中のミネラルが歯に再吸収され、表面が再び硬くなります。
2つ目は、歯質の強化です。フッ素が歯に取り込まれることで、エナメル質が強化され、酸に溶けにくい強い歯になります。
3つ目は、虫歯菌の抑制です。フッ素には虫歯菌が活動を抑える働きがあるため、虫歯の進行を防ぐ効果も期待できます。
これらの作用により、フッ素は予防歯科の分野で高く評価されており、子どもから大人まで広く利用されています。
子どもにフッ素を活用するメリット

ここでは、子どもにフッ素を活用するメリットについて解説します。
虫歯予防に高い効果を発揮する
子どもの歯は大人に比べてエナメル質が薄く、虫歯になりやすい傾向があります。
フッ素はその弱い歯を強化し、酸による脱灰を抑える効果があります。また、歯にダメージが加わっても、唾液とともにフッ素が作用することで再石灰化が促進され、初期の虫歯であれば自然修復されることもあります。
フッ素は虫歯の進行を防ぐだけでなく、初期の虫歯を治す可能性もあるのです。
歯質を強くして虫歯になりにくい歯を育てる
フッ素は歯の表面に取り込まれると、エナメル質の構造をより硬く、酸に強い性質へと変化させます。これにより、フッ素を継続的に取り入れている子どもは、虫歯に対する抵抗力の高い歯を持つことができます。
特に、生えたばかりの永久歯は非常に虫歯になりやすいため、この時期にフッ素を活用することは将来的な口腔の健康にも大きな影響を与えます。
虫歯菌の活動を抑える効果がある
フッ素には、虫歯の原因菌が酸をつくる働きを抑える作用もあります。これにより、歯の表面に酸が長時間とどまるのを防ぎ、歯が溶け出すリスクを下げることができます。特に、歯みがきが十分にできない年齢の子どもにとっては、フッ素の力が大きな助けとなります。
保護者の方のケアの補助として活用できる
小さな子どもは自分で丁寧に歯を磨くことが難しいため、どうしても磨き残しが多くなりがちです。特に奥歯の溝や歯と歯の間などは、虫歯のリスクが高い部分です。そういった部分にもフッ素が行き渡ることで、磨き残しによる虫歯の発生を予防する効果が期待できます。
ご家庭でのケアとフッ素の活用を組み合わせることで、より安心して子どもの口腔管理を行うことができます。
子どもにフッ素を使うときの注意点

ここでは、子どもにフッ素を使うときの注意点について解説します。
フッ素の過剰摂取に注意する
フッ素は虫歯予防に効果的な成分ですが、過剰に摂取するとフッ素症と呼ばれる状態を引き起こす可能性があります。特に子どもは身体が小さいため、少量でも過剰になるリスクがあります。フッ素症は歯の表面に白い斑点が現れる症状で、美観に影響する場合もあります。
フッ素入りの歯みがき粉を使う際には、年齢に応じた適量を守ることが大切です。たとえば、6歳未満の子どもには、米粒大の量を目安とし、うがいができない年齢の子には無理にフッ素入りの歯みがき粉を使わないようにしましょう。
飲み込まないように注意を促す
子どもは歯みがき粉をおいしいと感じて飲み込んでしまうことがありますが、これもフッ素の過剰摂取につながる原因の一つです。
特にフレーバー付きの歯みがき粉は子どもにとってお菓子のような存在になってしまうこともあるため、保護者の方が使用量を管理し、飲み込まないように指導することが重要です。また、歯みがきのあとにしっかりうがいをする習慣も身につけさせましょう。
フッ素塗布の頻度やタイミングに注意する
歯科医院で行われるフッ素塗布は効果が高い一方で、やみくもに頻繁に行えば良いというわけではありません。一般的には3ヶ月から6ヶ月に1回が適切とされています。
また、永久歯が生え始めるタイミングや、虫歯のリスクが高い子どもに対しては、歯科医師の判断に基づいて塗布の回数を調整することが望ましいです。個々のリスクに応じて、歯科医師と相談しながら活用していくことが大切です。
市販のフッ素製品との併用は慎重に
家庭でのフッ素ケア製品と、歯科医院でのフッ素塗布を併用する場合は、トータルのフッ素摂取量を意識する必要があります。
市販のフッ素入りマウスウォッシュやジェル、タブレットなどを過剰に使用すると、知らず知らずのうちにフッ素の摂取量が上限を超えてしまうことも考えられます。フッ素製品を複数併用する際には、歯科医師や歯科衛生士に相談し、適切な使用方法を確認しておくと安心です。
子どものフッ素の取り入れ方

ここでは、子どものフッ素の取り入れ方について解説します。
フッ素入りの歯みがき粉を活用する
もっとも手軽にフッ素を取り入れる方法が、フッ素入りの歯みがき粉を使うことです。市販の子ども向け歯みがき粉は、年齢に応じてフッ素濃度が調整されています。
例えば、6歳未満の子どもには500ppm程度、6歳以上では1000ppm〜1450ppmまでの濃度が推奨されています。歯みがき粉の使用量も年齢によって異なり、3歳未満なら米粒大、3〜6歳ならグリーンピース大を目安にすると良いでしょう。
毎日の歯みがきのなかで、自然にフッ素を取り入れる習慣を作ることが大切です。
フッ素入りの洗口液を取り入れる
フッ素入りの洗口液を取り入れる方法もあります。1日1回、フッ素入りの洗口液でうがいをするだけで、歯全体にフッ素を行き渡らせることができます。
ただし、うがいがしっかりできる年齢(おおむね4〜5歳以上)になってから使用を開始するのが望ましいです。
フッ素配合ジェルを活用する
歯みがきのあとに塗るタイプのフッ素ジェルなどの製品もあります。これらは歯全体にフッ素を直接塗布できるため、歯みがき粉とは異なる角度からの予防が期待できます。
特に、虫歯リスクの高いお子さまには、寝る前などに使用することで、フッ素が歯にとどまる時間を長く保てるという利点があります。
ただし、こちらも使用量や頻度に注意し、歯科医院でのアドバイスを受けながら行うことが重要です。
歯科医院での定期的なフッ素塗布
ご家庭でのケアとあわせて、定期的に歯科医院でフッ素塗布を受けることが効果的です。専門の器具と高濃度のフッ素を使用するため、自宅では届きにくい奥歯や歯と歯の間までしっかりケアすることができます。
3ヶ月〜6ヶ月に1回を目安に通院することで、虫歯の早期発見・予防にもつながります。子ども自身に歯医者さんに通う習慣を身につけさせることも、将来の歯の健康を守るうえで大切なポイントです。
歯科医院で受けられるフッ素塗布の費用

歯科医院で行われるフッ素塗布の費用は、保険適用の有無や自治体の支援制度によって異なります。多くの地域では、乳幼児や小児に対して子ども医療費助成制度が適用されるため、自己負担がない場合もあります。
一方、助成がない場合や自由診療でのフッ素塗布の場合、1回あたりの費用はおおよそ1,000円〜3,000円程度が一般的です。歯科医院によって料金設定が異なるため、事前に確認しておくと安心です。
また、定期検診の一環としてフッ素塗布を行う場合は、検診費用とあわせて請求されることがあります。自治体によっては1歳半健診や3歳児健診の場で無料でフッ素塗布を受けられるところもありますので、お住まいの地域の情報も確認しておきましょう。
まとめ

子どもの歯を虫歯から守るためには、日々のケアに加えてフッ素を上手に活用することが非常に有効です。フッ素には歯を強くし、虫歯菌の活動を抑える効果があり、家庭での歯みがきや洗口液、さらには歯科医院でのフッ素塗布など、さまざまな取り入れ方が存在します。
ただし、過剰摂取や誤った使用法には注意が必要であり、年齢や状況に応じた適切な方法を選ぶことが大切です。歯科医師や歯科衛生士のアドバイスを受けながら、子どもの成長に合わせたケアを続けていくことで、将来の健康な歯並びや口腔環境にもつながります。
フッ素はあくまで補助的なサポートであり、基本は毎日の丁寧な歯みがきと保護者の方の見守りです。正しい知識をもとに、安心してフッ素を取り入れていきましょう。
お子さんのお口の健康を守りたいとお考えの方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2025.08.23更新
治療してもすぐ虫歯になるのはどうして?再発を防ぐためにできることも
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。
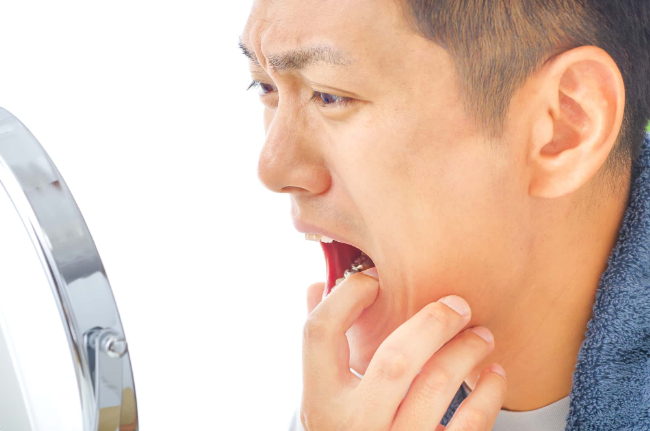
「この前虫歯を治療したばかりなのに、またできてしまった」「毎日歯磨きをしているのになぜか繰り返し虫歯ができる」とお悩みの方がいらっしゃるのではないでしょうか。
一度治療した歯が再び虫歯になることを二次カリエスといいます。実は、一度虫歯を削って治療した箇所は歯質が脆くなるため虫歯になりやすいのです。
とはいえ、何度も治療が必要になれば、通院や費用の負担も増えるため、できるだけ避けたいと考える方も多いでしょう。
そこで今回は、治療してもすぐ虫歯が発生する理由や再発しやすい部位、虫歯を繰り返さないためにできることなどについて解説します。
治療してもすぐ虫歯になるのはどうして?

治療を受けたにもかかわらず、再び虫歯が発生するのはなぜなのでしょうか。ここでは、治療してもすぐ虫歯が発生する理由についてみていきましょう。
治療した歯は脆くなるため
通常、私たちの歯はエナメル質という硬い組織で覆われていますが、虫歯を大きく削ると、内部の象牙質が露出することがあります。象牙質はとても柔らかいため、虫歯が進行しやすいです。虫歯の治療では、露出した象牙質を覆うために詰め物や被せ物を施します。
しかし、詰め物や被せ物を施しても、わずかなすき間や段差が生じて細菌が内部に侵入すれば、再び虫歯が発生するリスクが高まるのです。
適切なブラッシングができていないため
歯をしっかりと磨いているつもりでも、汚れやプラークが除去できていなければ、当然虫歯が発生しやすくなります。虫歯を繰り返す場合には、知らず知らずのうちに歯磨きの癖ができており、磨き残しやすい箇所が発生している可能性があるでしょう。
また、セルフケアの際に歯間ブラシやデンタルフロスなどを使用していない場合、歯間に蓄積したプラークが除去できず、二次カリエスが発生しやすくなります。
甘いものや酸っぱいものを好んで食べているため
せっかく虫歯を治療しても、治療前の食生活を続けていれば、二次カリエスを起こしやすくなります。虫歯菌は、食事に含まれる糖分をエサとして増殖します。そのため、普段から甘いものを頻繁に食べている人は、そうでない人に比べて虫歯のリスクが高くなります。
また、酸っぱいものを頻繁に食べている場合も、口腔内が酸性に傾き、歯が溶かされやすくなります。
ダラダラ食べをしているため
口腔内は、1日のうちに中性になったり酸性になったりを繰り返しています。食事をしたあとは虫歯菌が酸を放出し、口腔内が酸性に傾きますが、歯磨きをすることや唾液が作用することによって中性に保たれるのです。
しかし、ダラダラ食べを続けていると口腔内が中性に戻ることなく、酸性に傾いたままの状態になります。その結果、歯が溶かされて虫歯が発生しやすくなるのです。
口腔内が乾燥しているため
唾液には、口腔内の食べカスや汚れを洗い流し、細菌の活動を抑制する働きがあります。
しかし、加齢やストレス、口呼吸などが原因で唾液の分泌量が減少すると、虫歯が発生しやすく、進行も早くなります。
歯並びが乱れているため
歯並びが悪いと、歯と歯が重なり合ったり凸凹したりして、歯ブラシが行き届きにくくなります。その結果、磨き残しが増えると、虫歯を繰り返すリスクが高くなるでしょう。
虫歯が再発しやすい部位

虫歯が再発しやすい部位は、以下の通りです。
詰め物や被せ物の周辺
虫歯治療の際に装着した詰め物や被せ物には、経年劣化によってすき間や段差ができることがあります。そのようなすき間や段差にはプラークが蓄積しやすくなるため、虫歯が再発するリスクが高まります。
歯と歯の間
歯と歯の間も虫歯が再発しやすい部位のひとつです。歯間に付着した汚れは歯ブラシだけでは取り除くことが難しく、磨き残しが増えると細菌が繁殖して虫歯が再発する可能性があります。
歯の根元
歯の表面はきれいに磨けていても、歯の根元(歯と歯茎との境目)に磨き残しがあるケースも多いです。歯の根元はプラークが蓄積しやすいことに加え、歯根部分はエナメル質で覆われていないため、虫歯菌のダメージを受けやすい状態になります。
奥歯の溝やすき間
奥歯の溝は複雑な形状をしており、磨き残しが多くなりがちです。また、奥歯は噛み合わせることによって強い力がかかるため、詰め物や被せ物が劣化し、すき間やヒビ割れなどが生じやすくなります。その結果、内部に虫歯菌が侵入し、二次カリエスを引き起こすリスクも高くなります。
虫歯を繰り返さないためにできること

毎日の生活を意識的に改善することで虫歯を予防することも可能です。虫歯を繰り返さないためにできることには、以下のようなものがあります。
食生活を改善する
先にも述べた通り、糖分の多いものや酸っぱいものを頻繁に口にすると、虫歯になるリスクが高まります。再発のリスクを軽減するためにも、食生活を見直したほうがよいでしょう。また、ダラダラ食べをやめて、1日3食しっかりと食べることが大切です。
なお、水分補給には甘い飲みものではなく、水や無糖の飲み物を選ぶとよいでしょう。
適切な方法でセルフケアを行う
虫歯の再発を防ぐためには、適切な方法でセルフケアを行うことが重要です。忙しくて毎食後に歯磨きができない方もいらっしゃるかもしれませんが、少なくとも朝晩の2回は丁寧にセルフケアを行うことを心がけましょう。
特に、詰め物や被せ物の周辺、歯と歯の間、歯の根元、奥歯の溝などは、丁寧に磨くことが重要です。歯と歯の間の清掃には、デンタルフロスや歯間ブラシを使用しましょう。
フッ素を活用する
フッ素には、細菌の増殖を抑えたり歯質を強化したりする効果があります。また、エナメル質の表面がわずかに溶かされた状態であれば、フッ素を塗布することで修復が見込めます。
フッ素を含むケア用品は市販でも多く販売されていますので、ご自身が使用しやすいものを取り入れるとよいでしょう。なお、歯科医院であれば、市販のものよりも高濃度のフッ素塗布が受けられますので、より高い予防効果が期待できます。
口の中の乾燥を予防する
先にも述べた通り、唾液の量が少なく口の中が乾燥していると、虫歯のリスクが高まります。二次カリエスを予防するためにも唾液の分泌量を増やし、乾燥を防ぐことが大切です。
唾液の分泌を促進する具体的な方法としては、よく噛んで食べる・キシリトールガムや無糖のガムを噛む・こまめに水を飲むなどが挙げられます。そのほかにも、口呼吸を改善したり口腔保湿剤を使用したりするのも有効な方法といえるでしょう。
ストレスや疲れを溜めない
緊張しているときに口が乾いた経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、ストレスにさらされると唾液がネバついた性状に変化し、口腔内が乾燥しやすくなるといわれています。また、虫歯や歯周病は細菌感染によって引き起こされるものですので、ストレスや疲れが溜まって身体の抵抗力が下がっていると発症しやすくなるのです。
そのため、普段からストレスや疲れを溜め込まないように意識したり栄養バランスのよい食事、十分な休息などを心がけたりすることも大切です。
歯列矯正を受ける
歯並びが乱れていると清掃性が悪くなるため、どうしても虫歯のリスクが高まります。そのため、歯列矯正を受けて歯並びを整えることも虫歯の予防につながります。
定期的に歯科医院を受診する
毎日のセルフケアを丁寧に行っていても磨き残しは発生するものです。そのため、3ヵ月に1回程度は定期的に歯科医院でチェックを受けることが望ましいでしょう。
定期的な歯科検診では、歯のクリーニングやブラッシング指導、詰め物や被せ物のチェックなどが受けられます。定期的に歯科医院を受診することは虫歯の予防はもちろん、トラブルの早期発見・早期治療にもつながるでしょう。
まとめ

一度虫歯を治療した箇所は歯質が弱くなるため、二次カリエスを発症しやすくなります。また、何度も虫歯を繰り返す場合には、食生活や口腔環境、セルフケアの方法などに問題がある可能性もあるでしょう。
普段の生活のなかで虫歯の再発予防に役立つ方法もありますので、ぜひ本記事を参考にしてみてください。「正しいブラッシング方法が知りたい」「歯並びについて相談したい」という方も、歯科医院へご相談ください。
虫歯にお悩みの方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2025.04.22更新
今日から実践!歯周病を予防するためにできること
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

「歯磨きの時に歯茎から出血する」「歯周病は治療できるの?」「歯周病って予防できるの?」など、歯周病に関して悩んでいる人は多いのではないでしょうか。歯周病はプラークによる細菌感染が主な原因となり、歯茎に炎症を起こす病気です。
将来的に歯を失うこともある歯周病には、正しい予防と適切な治療が必要です。
今回は、歯周病の原因や歯周病の予防と早期発見が大切な理由、歯周病を予防する方法について詳しく解説します。
歯周病の原因

歯周病は炎症性疾患で、主な原因は歯と歯茎の間に蓄積するプラーク(歯垢)です。プラークは細菌の塊で、適切に除去されないと歯石へと変化し歯周組織を破壊します。
また、生活習慣なども歯周病のリスクを高める要因となります。ここでは、歯周病の主な原因について詳しく解説します。
喫煙
ニコチンやタールなど、たばこに含まれる有害物質が口腔内の粘膜や歯肉から体内に吸収されると、免役力が低下します。十分な血液が歯茎に届かなくなることから、細菌に対する抵抗力が低くなり歯周病のリスクがアップします。
タバコは歯周病を悪化させるだけでなく、治りにくくする特徴もあります。また、受動喫煙も歯周病に影響を及ぼすとされています。
よく噛まずに食べる
食事の際に食べ物をよく噛まないと、唾液が十分に分泌されないことから、口内の自浄作用が低下して細菌が繁殖しやすくなります。食べ物をよく噛むことで顎の筋肉が鍛えられ、血液の循環が良くなり免疫力がアップし、歯周病の予防につながります。
食事の際は、よく噛んで食べることを心がけましょう。
不適切な口腔ケア
毎日のケアで、適切にブラッシングが行われないとプラークが蓄積しやすくなります。また、歯ブラシだけのお手入れでは、歯と歯の間に汚れが残りやすいです。
歯間に残った汚れが歯周病の原因となることがあるため、歯周病を予防するためにはデンタルフロスや歯間ブラシの使用が欠かせません。
歯周病の予防と早期発見が大切な理由

歯周病は、初期段階での治療が非常に重要な病気です。放置して進行すると、歯を支える骨や歯茎が破壊され、最終的には歯を失うリスクが高まります。
ここでは、歯周病の予防と早期発見が大切な理由についてまとめます。
歯の喪失を防げる
歯周病が進行すると、歯を支える歯槽骨や歯茎が徐々に破壊されます。歯がぐらつき、最終的には抜け落ちることもあります。歯周病の進行を食い止め、歯を支える組織を回復させるためには早期に治療することが望ましいです。
しかし、治療が遅れると外科的な治療が必要になるケースが多く、治療の負担が増加します。また、回復までの時間も長くなる傾向があります。
治療費を節約できる
歯周病が悪化すると、歯周外科治療や歯周再生療法など、高度で費用のかかる治療が必要になるケースがあります。必然的に通院回数も増え、時間的な負担も大きくなります。
早期に発見すると、スケーリングや日常的なケアの指導が主な治療内容となるので、治療にかかる時間はもちろん費用も抑えられます。歯周病を早期に発見すると、治療も早い段階で開始できるため、経済的負担を軽減し時間を効率的に活用できます。
口腔内の快適さが向上する
歯周病が進行すると、歯茎の腫れや出血、口臭、歯のぐらつきや痛みなどの不快な症状を引き起こします。これらの症状は、食事や会話を楽しめないなど、日常生活に大きな支障をきたします。
早期に発見し治療を開始すれば、口腔内の快適さを取り戻せるでしょう。
全身の健康を守れる
歯周病は、口腔内だけでなく、全身の健康にも影響を及ぼします。進行した歯周病は、糖尿病の悪化、心筋梗塞や脳梗塞、妊娠中の早産や低体重児出産などのリスクを高めることが分かっています。
早期に発見し治療すれば、これらの全身疾患のリスクを減らすことが可能です。歯科治療を通じて全身の健康が守られるのは、早期発見・早期治療の大きなメリットといえるでしょう。
再発予防が容易になる
慢性的な疾患の歯周病は、治療後も再発の可能性があります。早期に治療を受けることで、健康な状態を維持しやすくなり、再発のリスクを最小限に抑えられるでしょう。
歯周病を予防するためには

ここでは、歯科医院で行う予防法と、自宅でできる予防法について詳しく解説します。
歯科医院で行われる予防法
歯周病は、適切な予防策をとることで発症を抑えられます。まずは、歯科医院で実施される予防策をご紹介します。
定期的な歯科検診
歯周病の予防では、定期的な歯科検診が欠かせません。歯科検診では、歯茎の出血の有無、歯周ポケットの深さなどをチェックします。初期段階では自覚症状が乏しいため、定期検診で歯周病の有無を確認することが重要なのです。
定期検診の目安は3~6か月に一度ですが、個々の口腔状態やリスクに応じて歯科医師と相談して適切な頻度を決めるようにしましょう。万が一、歯周病に罹患していても、初期のうちに治療を開始できるメリットがあります。
クリーニング
国家資格を保有する歯科医師や歯科衛生士が行うクリーニングでは、専用の機械や薬剤を使用して歯の隅々まで汚れを除去できます。毎日丁寧に歯を磨いても、歯と歯の間や歯と歯茎の境目などには磨き残しが生じます。
特に、奥歯の裏側や小臼歯などは歯ブラシの毛先が届きにくく、歯の形が丸いので磨き残しが多い箇所です。
汚れをそのまま放置していると徐々に歯石に変化し、歯周病の原因になります。プラークを歯石化しないためにも、定期的なクリーニングが重要です。
定期的にクリーニングを行うことで健康な歯茎を維持しやすくなるため、歯周病の予防につながります。
ブラッシング指導
歯磨きが得意でないと感じている場合は、必要に応じてブラッシング指導を受けるようにしましょう。利き手の違いや歯の形、歯並びなど、さまざまな要素が重なり、磨き方には一人一人癖があります。
そのため、同じ個所を磨き残す人は少なくありません。また、患者様の口腔内や歯並び、歯の形状、サイズに合わせた歯ブラシの選び方や当て方、動かし方を意識するだけで、きれいに磨けるようになる人も珍しくありません。
歯周病の予防には、デンタルフロスや歯間ブラシなどのツールを併用することも不可欠です。ブラッシング指導の際に、歯ブラシの動かし方だけでなくツールの使い方も教われば、毎日のセルフケアのクオリティを高められるでしょう。
自宅でできる予防法
歯周病の予防には、歯科医院で行う定期検診のほかに、生活習慣の改善など、自宅でできる予防法があります。
正しく歯磨きを行う
自己流の磨き方では、歯に付着した汚れをしっかり落とせない可能性があります。プラークを除去することを意識して、しっかり歯磨きしましょう。
歯を磨くというよりも、歯と歯茎の間や歯間のプラークを除去するイメージでブラッシングすると良いかもしれません。デンタルフロスや歯間ブラシを使用することも忘れないようにしましょう。
歯ブラシが届きにくい部分は、デンタルフロスや歯間ブラシも併用しながら、隅々まできれいにブラッシングしてください。歯磨きだけでは届かない部分の清掃が可能になり、より効果的にプラークを除去できます。
生活習慣を見直す
バランスの取れた食事や、抗酸化作用のあるビタミンCやカルシウムを含む食品を積極的に摂取することで、歯周病を予防できます。栄養の偏った食事は、身体の抵抗力を弱める恐れがあります。
食事を取ったり取らなかったりするような生活や、ダラダラといつまでも食事を続けることのないようにしましょう。いつまでも口内に食べ物が入っている状態が続くと、虫歯のリスクが上がるため、1日3食できるだけ決まった時間に食事を取るようにしてください。
また、十分な睡眠をとりストレスを適切に管理することで、免疫力を高められます。良い睡眠をとるためのポイントは、以下のとおりです。
- 起床時間と就寝時間を決める
- 朝日をしっかり浴びる
- 就寝前にスマホを見ない
- 就寝前の飲食を控える
- 入浴は寝る2~3時間前に終わらせる
毎日、7~8時間の睡眠時間を確保することが望ましいでしょう。健康的な生活習慣は、歯周病の予防だけでなく全身の健康維持にも重要です。
禁煙
喫煙は歯周病のリスクを高めるため、歯周病の予防として禁煙が推奨されます。喫煙者は非喫煙者に比べ、歯周病に罹患するリスクが高いです。そのため、禁煙することで歯周病の発症リスクを大幅に減少させられるでしょう。
患者様自身で禁煙が難しい場合は、禁煙をサポートするプログラムやカウンセリングを活用し、禁煙を成功させましょう。
まとめ

歯周病は自覚症状に乏しく軽視されがちですが、口腔内だけでなく全身疾患にも関連する怖い病気です。歯周病の予防と悪化防止には、歯科医院での定期検診はもちろん、患者様自身でのセルフケアが欠かせません。
歯周病は罹患する前に予防することが大切なので、まず歯科医院で定期検診を受け、現状の歯や歯茎をチェックして適切な治療を受けるようにしましょう。
歯周病予防に興味がある方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2025.03.11更新
歯のクリーニングはどれくらいの頻度で受けるべき?メリットと注意点も
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

虫歯や歯周病などを予防するためには、定期的に歯のクリーニングを受けることが重要です。
しかし、どのくらいの頻度で通えばよいか分からないとお悩みの方は少なくありません。歯のクリーニングの頻度は、お口の状態や生活習慣によって異なります。
この記事では、適切な歯のクリーニングの頻度やメリット、注意点について解説します。
歯のクリーニングを受ける頻度

口内環境や生活習慣によって歯垢や歯石が溜まるスピードが異なるため、歯のクリーニングの頻度については個人差があります。ここでは、一般的な歯のクリーニングを受ける頻度について解説します。
セルフケアが適切な方
セルフケアによる磨き残しが少ない方の場合、虫歯や歯周病のリスクは少ないといえます。例えば、フロスや歯間ブラシも使用している方が挙げられるでしょう。他にも、以下の特徴がある方が挙げられます。
- 歯磨きが上手な方
- 歯並びがよい方
- 毎食後に歯磨きしている方
- フロスや歯間ブラシも使用している方
日々の歯磨きだけでも口内の汚れをしっかり落とせているため、歯のクリーニングは約3~6ヵ月に1回の頻度でかまいません。
歯磨きが苦手な方・歯並びが悪い方
歯磨きが上手にできていない方や歯磨きの頻度が低い方の場合、磨き残しができやすいです。また、歯と歯の重なりが多い方、反対に歯と歯の間に隙間が空いている方の場合、きちんと歯磨きをしていても汚れが溜まることがあります。
- 歯磨きが苦手
- 歯磨きの回数が少ない方
- 歯並びが悪い方
上記のような方の場合、虫歯や歯周病のリスクが高くなるため、約1~2ヵ月の頻度で歯のクリーニングを受けましょう。定期的な歯のクリーニングにより、虫歯や歯周病のリスクを下げ、口臭の予防にもつながります。
歯周病の方
歯周病がある方も、より頻繁にクリーニングを受けるべきでしょう。
- 歯茎から出血しやすい方
- 歯周病と診断された方
- 歯周病が進行している方
上記の方の場合は、約1~2ヵ月に1回の通院が必要といえます。歯茎から出血する原因は、磨き残しがあり、歯茎が炎症を起こしているからです。放置すると慢性的な歯肉炎になり、いずれは歯周病を発症します。
虫歯になりやすい方
きちんと歯磨きをしていても、口内環境や食生活によって虫歯のリスクは変動します。特に、食生活が乱れている方や口内が乾燥しやすい方の場合、虫歯リスクが高いので注意が必要です。
また、虫歯治療を受けた回数が多い方も、詰め物や被せ物の隙間から虫歯になることがあります。
- 甘いものを好んでよく食べる方
- 間食が多い方
- 口呼吸の方
- 唾液の量が少ない方
- 虫歯治療を受けた回数が多い方
上記に当てはまる方は、約1~2ヵ月に1回のクリーニングが適切でしょう。定期的に歯科に通院すれば虫歯の有無をチェックしてもらえるため、虫歯を未然に防ぐ効果があります。
歯石が付きやすい方
歯石の付きやすい方の場合、約1~2ヵ月に一度の頻度で歯のクリーニングを受けると良いでしょう。歯石の付きやすさは、食生活や口内環境によって左右されます。
- 甘いものを好んでよく食べる方
- 間食が多い方
- 口呼吸の方
- 唾液の少ない方
上記のような方は、定期的に歯科医院でクリーニングを受けて、口内環境を整える必要があります。
飲食物に含まれる糖分を多く摂取すると、細菌が繁殖し、歯垢の生成が促されます。また、唾液の分泌量が少なければ、汚れが洗い流されません。溜まった歯垢は歯石に変化し、歯ブラシでは取れない汚れへと変化します。
着色が付きやすい方
着色が付きやすい方や着色が気になる方は、約2~3ヵ月に1回のクリーニングが推奨されます。
ただし、審美目的の着色除去の場合、保険が適用されないことがあるため注意が必要です。
喫煙習慣のある方
喫煙習慣のある方は、約1~2ヵ月に一度の頻度で歯のクリーニングを受けると良いでしょう。喫煙習慣がある方は、歯周病の発症リスクが高く、かかった場合は進行しやすいです。また、歯石や着色汚れも付着しやすいので、頻繁にクリーニングを受けるべきです。
歯のクリーニングで行うことと流れ

ここでは、一般的な歯のクリーニングの内容と流れを解説します。
検査
まず、お口の状態を把握するために検査を行います。検査の内容は、レントゲン撮影や歯科医師による視診、歯周病検査などです。歯周病検査では、歯周ポケットの深さ、出血や歯の揺れの有無を確認します。
これらの検査を行うことで、歯周病の進行具合や磨き残しの有無、歯石の付き具合を把握でき、患者様に合った治療内容を定められます。
歯磨き指導
検査で磨き残しをチェックした後は、歯磨き指導を行います。歯ブラシの持ち方や当て方、フロスや歯間ブラシの使用方法について、詳しくアドバイスします。
スケーリング
歯垢はやわらかい汚れのため、歯磨きで取り除くことが可能です。
しかし、歯垢は数日経つと歯石へと変化し、歯ブラシでは取り除けなくなります。そのため、超音波を使用した機械やハンドスケーラーという専用の器具を使用して、除去しなければなりません。
フロッシング
フロッシングとは、フロスや歯間ブラシを使用し、歯と歯の間の汚れを取り除くことです。これらの器具を歯と歯の間に通して、歯石の取り残しがないか確認する目的もあります。
ポリッシング
歯の汚れを取り除いた後は、ポリッシングを行います。ポリッシングとは、専用のペーストを使用し、歯の表面を仕上げ磨きすることです。
歯の表面をツルツルに仕上げることで、着色汚れを除去するだけでなく、新たな歯の汚れを付きにくくする効果があります。
フッ素塗布
歯のクリーニングが終わった後は、全体にフッ素塗布を行います。フッ素には、歯の質を強くし細菌の働きを弱める効果があります。
定期的にフッ素塗布を行うことで、虫歯や歯周病を予防できるのがメリットです。
歯のクリーニングを受けるメリット

歯のクリーニングを受けるメリットは、以下の3点です。
口腔トラブルの予防
口内の汚れをすみずみまで除去することで、虫歯や歯周病を予防できます。また、たとえ虫歯になっていたとしても、早期発見・早期治療に繋げられるでしょう。
着色除去・予防
丁寧に歯磨きをしている方でも、日々の食事により着色が付くことがあります。
しかし、普段の歯磨きでは、なかなか着色汚れは取り除けません。定期的な歯のクリーニングにより、本来持っている歯の白さやツヤを取り戻せます。
口臭改善・予防
歯垢・歯石を除去することで、口臭の改善に効果があります。また、虫歯や歯周病の進行も、口臭の原因の1つです。
歯科治療とクリーニングを併用することで、口内の細菌の繁殖を予防します。虫歯や歯周病だけでなく、口臭の予防に効果があるといえます。
歯のクリーニングを受ける際の注意点

歯のクリーニングを受ける際の注意点は、以下の2点です。
出血や痛み
歯垢や歯石が付いている場合、歯茎の炎症により、クリーニングの際に出血する場合があります。また、歯石が多くついている場合、痛みが出たりクリーニング後に知覚過敏のような症状が出たりする場合があるので注意が必要です。
ただし、歯茎の炎症が治まれば、出血や痛みは自然と治まります。多くの場合、クリーニング当日、長くても2~3日程度で症状は落ち着いてきます。
色の濃い飲食物は避ける
クリーニングを受けた後の歯は、外部からの刺激を受けやすい状態です。着色が付きやすいため、色の濃い飲食物は避けましょう。
具体的には、カレーや赤ワイン、コーヒーなどです。また、熱いもの・冷たいものを摂ると、歯がしみる場合もあります。そのため、クリーニング当日は刺激のあるものも控えてください。
まとめ

セルフケアがきちんとできている方の場合、歯のクリーニングは約3~6ヵ月に1回でかまいません。歯磨きが苦手な方や歯石が付きやすい方の場合、虫歯や歯周病のリスクが高いため、約1~2ヵ月に1回と頻繁に通う必要があります。
歯石を放置すると、虫歯や歯周病を発症し歯の寿命を縮めるかもしれません。また、口臭の発生や着色により、人に不潔な印象を与えることもあります。
お口の健康を維持するためには、ご自身に合った歯のクリーニングの頻度を知っておくことが大切です。
歯のクリーニングの頻度や内容について詳しく知りたい方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2024.10.22更新
予防歯科とは?何をするの?費用と保険適用についても解説
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

「歯の治療は痛いしお金がかかる」と、通院するのをためらう方もいるのではないでしょうか。
しかし、歯の問題が重症化すると、治療にかかる費用や期間が増えることになります。また、見た目に自信がなくなったり、好きなものが食べにくくなったり、日常生活に支障をきたす場合もあるでしょう。
予防歯科は、虫歯や歯周病の発生を抑え、歯の健康維持のために有効な手段です。
この記事では、予防歯科の内容や費用、保険適用の可否について解説します。メリットやデメリットもご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
予防歯科とは

予防歯科とは、虫歯や歯周病などのトラブルを未然に防ぎ、歯の健康寿命を長くするための取り組みです。従来の治療は症状が出てから行うのが主流でしたが、予防歯科は普段から歯の健康を保つために積極的に歯科医院を受診します。
海外では予防歯科の考え方が一般的になっており、近年では、日本でも予防歯科に力をいれる歯科医院が増えてきました。
予防歯科では何をするの?

予防歯科では、プロフェッショナルケアとセルフケアの2つを組み合わせることで、虫歯や歯周病を予防します。ここからは、プロフェッショナルケアとセルフケアの内容をご紹介します。
プロフェッショナルケア
以下で、歯科医院で行うプロフェッショナルケアの内容について詳しく解説します。
検査
まず、予防歯科ではお口の中の検査を行います。歯科医師がお口の中を見て、虫歯・歯周病の有無や歯周ポケットの深さ、歯茎や噛み合わせの状態などを確認します。他にも、歯の動揺や割れ・欠けがないかなどの確認も行われるでしょう。
必要に応じて、レントゲン撮影をする場合もあります。健康なときのお口の中の状態を知っておくことで、問題が起こった際にすぐに気づいて対処できるのです。
スケーリング
予防歯科では、歯の表面や歯周ポケットにたまった歯石を専用器機で取り除く、スケーリングと呼ばれる処置が行われます。歯垢を放置すると石灰化して歯石になりますが、セルフケアでは除去できません。
歯石は口内トラブルの原因になるため、歯科医院でしっかり除去してもらうことが重要なのです。スケーリングを定期的に受けることで口腔内の健康を維持し、虫歯や歯周病を防げるでしょう。
PMTC
PMTC(Professional Mechanical Tooth Cleaning)とは、専門的なクリーニングのことです。専用の機器や研磨剤を使用して、セルフケアでは取り除けない汚れや細菌の塊(バイオフィルム)を除去します。
PMTCでは、歯の表面を滑らかにして汚れや細菌が再び付着しにくい状態を保ちます。また、飲食物やタバコによる着色汚れも取り除けるため、審美性の向上も期待できるでしょう。
歯磨き指導
虫歯や歯周病を防ぐためには、歯科衛生士による歯磨き指導も重要です。予防歯科では、歯科衛生士が患者様の歯の状態に合わせて、適切な歯ブラシの選び方や歯磨きのやり方、歯間ブラシやフロスの使い方などを丁寧に指導します。
歯磨き指導を受けるとセルフケアの質が向上し、口腔内の健康を長期にわたって保つことにつながるでしょう。
フッ素塗布
フッ素は、歯質を強化して虫歯になりにくくする作用があります。特に、歯が柔らかい乳歯や生えて間もない永久歯には、フッ素による予防は有効です。
汚れや歯石をしっかり取り除いた歯にフッ素を塗布することで、フッ素の効果を最大限に発揮できます。フッ素の効果は約3~4ヶ月程度持続するため、その期間内に再度歯科医院を受診して塗布してもらうと良いでしょう。
シーラント
シーラントは、歯の溝を歯科用プラスチックで埋めて虫歯を予防する処置です。歯の溝には歯ブラシの毛先が届きにくく、食べかすやプラークが溜まりやすいです。シーラントで溝を埋めれば、歯垢や食べカスがたまりにくくなるのです。
また、歯を強くするフッ化物が含まれている場合が多く、歯の再石灰化を促進するため虫歯予防に高い効果が期待できるでしょう。
特に、生えたばかりの6歳臼歯や乳歯の奥歯は、歯の溝が深く虫歯になりやすいです。シーラントが予防に非常に有効です。
通常は予防のために行う処置は保険適用外ですが、6〜12歳のお子様であれば保険適用でシーラントを受けられます。
セルフケア
予防歯科では、歯科医院でのプロフェッショナルケアに加えて、自宅でのセルフケアもしっかり行うことが大切です。
毎日のケアを疎かにして磨き残しが生じると、汚れや歯垢が蓄積して細菌が繁殖します。虫歯や歯周病の原因になるため、歯の汚れを毎日しっかり落として口腔内を清潔に保つことが重要です。
特に、就寝中は唾液の分泌量が減るので、お口の中が乾き細菌が増えやすい状態になります。寝る前の歯磨きをしっかり行い、細菌の量をできるだけ抑えましょう。
また、食生活の改善も予防歯科には欠かせません。糖分の摂取を控えたり、栄養バランスの取れた食事をしたり、口腔内の健康を保ちましょう。
食生活の改善は、口腔内だけでなく全身の健康にもつながります。バランスの取れた食事を心がけ、適切な食習慣を続けることで長く健康な歯を保てるでしょう。
予防歯科の費用と保険適用について

以前は、予防歯科は基本的には保険適用外の自由診療でした。健康保険の制度は病気の最低限の治療をカバーするもので、予防歯科は病気になる前の診療なので治療ではないと考えられていたからです。
しかし、2020年4月の診療報酬改定によって、虫歯予防も治療の一環という考えに変わり、保険が適用されるケースも出てきました。予防歯科の保険適用の条件は、大きくわけて以下の2つです。
- すでに虫歯や歯周病がある
- 口腔管理体制強化加算の基準を満たしている
虫歯や歯周病は、進行を抑えることが重要です。重症化すると治療の難易度が高くなるため、予防処置が必要と判断された場合は保険が適用されます。
また、治療を行う歯科医院が、口腔管理体制強化加算という基準を満たしていることも予防歯科に保険が適用される条件です。
予防歯科にかかる費用は、保険診療の3割負担の場合、1回3,500円程度が目安とされています。自由診療の場合の目安は、1回5,000円〜2万円程度です。
自由診療は治療費を歯科医院で自由に決めることができ、歯科医院によって費用が異なるため、事前に確認しましょう。
予防歯科のメリット・デメリット
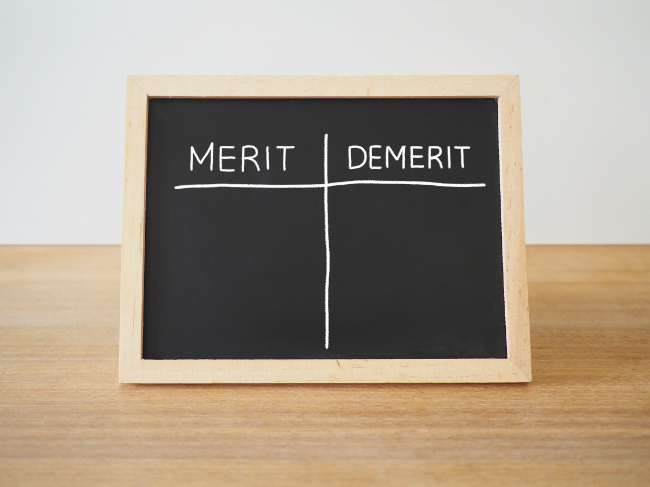
ここからは、予防歯科のメリットとデメリットを解説します。両方をしっかり理解しておきましょう。
メリット
予防歯科のメリットは、以下のとおりです。
虫歯や歯周病を未然に防げる
予防歯科に定期的に通うことで、虫歯や歯周病を未然に防げます。初期の虫歯や歯周病は自覚症状がほとんどなく、気づいた時には進行しているケースも少なくありません。
予防歯科では、虫歯や歯周病になりにくい口内環境を作れます。また、定期的に歯科医院を受診していれば、虫歯や歯周病になった場合でも早期に発見して治療できるのです。
将来の治療費を抑えられる
予防歯科は、将来かかるかもしれない高額な治療費の抑制が期待できるでしょう。虫歯や歯周病は、症状が進行するほど治療が複雑になって通院回数が増え、治療費も高くなります。
しかし、予防歯科で定期的に歯科医院を受診していれば、万が一トラブルが発生しても症状が軽いうちに発見・対処できます。予防歯科で口内の健康を維持することで、将来かかる治療費用の負担を減らせる可能性があるのです。
全身疾患のリスクを軽減できる
予防歯科で虫歯・歯周病予防を行えば、さまざまな病気のリスクを軽減できます。
虫歯や歯周病の細菌が歯茎から血管に入り全身を巡ると、心臓や脳の疾患などを引き起こす可能性があります。そのため、虫歯や歯周病の予防をすることで、全身疾患のリスクの低減につながるのです。
また、近年では歯が残っている本数が多いほど、健康寿命が長くなるということが明らかになってきました。健康な歯があることで食べ物をしっかり噛めて脳の血流が増え、全身の健康につながるのです。
デメリット
予防歯科のデメリットは、定期的に通院する必要があることでしょう。患者さまによって多少異なりますが、一般的に約3ヶ月に1回、年に3〜4回程度の通院が必要とされています。
虫歯や歯周病の予防に不可欠なことを理解していても、通院時間の確保が必要だったり費用の負担が増加したり、通い続けるのが難しいと感じる方もいるかもしれません。
しかし、虫歯や歯周病になると治療費がかかり、重症化している場合は費用や通院の負担が大幅に増加します。予防歯科を続けることで、結果的に将来的な治療の負担を減らせる可能性が高くなるため、受けたほうが良いでしょう。
まとめ

予防歯科では、虫歯や歯周病にかからないためのケアを行い、健康な歯を維持するためのサポートが行われます。定期的な通院で将来かかるかもしれない治療費を軽減でき、病気のリスクも抑えられるのがメリットです。
ただし、保険適用外になる場合もあるので、事前に歯科医院に相談しましょう。歯の健康を長く保つためにも、予防歯科を検討してみてはいかがでしょうか。
予防歯科を検討されている方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2024.08.27更新
MTMとは?歯科で予約する流れ・検査や治療内容・費用・重要性を解説!
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

皆さんはMTM(メディカルトリートメントモデル)という言葉をご存じでしょうか。MTMとは患者さんの口腔内の状態を詳しく確認したうえで将来的なリスクを評価し、予防をおこなうプログラムのことです。
従来の「歯が痛くなったから歯医者に行く」という考えではなく「歯の健康を維持するために歯医者に行く」ことを目的としています。
歯が痛い・歯茎から出血した・歯が欠けたなど何かきっかけがないと歯科医院を受診しないという方がいるかもしれませんが、MTMについて知り、今一度自分の歯の健康について考えてみてはいかがでしょうか。
今回は、MTMの流れや内容、費用、重要性などについて解説します。
MTM(メディカルトリートメントモデル)とは?

MTM(メディカルトリートメントモデル)とは、患者さんの口腔内の状態を確認して初期のリスク評価から予防プログラムの立案、最小限の治療、メンテナンスまでの一連の流れのことをいいます。
従来の歯科医療では、虫歯や歯周病の早期発見や症状のある部分の修復・補綴などを目的としていましたが、近年では「できるだけ欠損しないように」「健康な歯をより長く保てるように」という予防的なアプローチへと変化しています。現在では多くの歯科医院がMTMによるプログラムを作成し、患者さんへの予防的なマネジメントをおこなっているのです。
歯科でMTMを予約する流れ

歯科でMTMを予約するには、まず受診したい歯科医院がMTMに対応しているかを確認する必要があるでしょう。MTMを取り入れているどうかは歯科医院のホームページで確認することもできますし、電話で問い合わせることもできます。
突然来院されてもお時間が確保できない可能性があるため、必ず予約を入れてから受診するようにしてください。また、予約の際に「MTMを希望します」「MTMについて詳しい内容が知りたいです」と伝えていただけるとスムーズにご案内ができるでしょう。
MTMの検査や治療内容

では、MTMではどのような検査や治療がおこなわれるのでしょうか。ここでは、MTMの検査や治療の内容について解説します。
初診
初診では、まず問診票を記入していただきます。年齢や生活習慣、既往歴などを確認し、治療と予防の計画に役立てます。気になる症状などがあれば、初診時にお伝えください。初診の日に検査をおこなうことが一般的です。
初診時は検査時間も含めて60分ほどかかりますので、お時間に余裕のある日に予約を取るとよいでしょう。
検査
問診が終了したあとは、患者さんの口腔内の状態を詳しくチェックするために検査をおこないます。検査では、レントゲン撮影や口腔内写真撮影、唾液検査、歯周検査などがおこなわれることが一般的です。
しかし、具体的な検査の項目については歯科医院によっても異なります。
治療計画の説明
検査のあとには、検査結果をもとに現在の口腔内の状態や将来的なリスクなどについて説明があります。その後、患者さん一人ひとりに合った予防計画を説明し、実際に治療開始となるでしょう。
検査や治療計画の説明終了後には、歯科衛生士から歯磨き指導や歯石除去、PMTC(専用機械を使ったクリーニング)、フッ素塗布などを受けて初診日は終了です。
初期治療
初期治療では、初診日のブラッシング指導のとおりに丁寧にセルフケアができているかを確認し、再度ブラッシング指導がおこなわれます。丁寧に磨いているつもりでも、歯垢や歯石が蓄積している可能性はありますので、歯垢や歯石の除去もおこないます。
その後、専用の機械を用いたクリーニング(PMTC)をおこない、フッ素を塗布して終了です。
評価
初期治療が終了したら、再度虫歯や歯周病の検査をおこない、口腔内の環境が改善されているかどうか評価をおこないます。このとき、再度口腔内写真を撮影し、治療前後の状態をチェックします。これまでの経過を踏まえて、今後のための予防プランを説明します。
治療
初期虫歯であれば適切な歯磨きやメンテナンスで進行を止めることが可能です。
しかし、虫歯治療の必要があると判断した場合には、治療をおこないます。
治療後の再評価
虫歯の治療が完了したら、これまでの治療により口腔内の状態がどの程度改善されたかを再評価します。治療開始前との口腔内の状態を比較するために、レントゲン撮影や口腔内写真撮影、唾液検査をおこなうことが一般的です。
一連の治療が終了したら、これまでの経過を患者さん自身がいつでも確認できるようにデータをお渡しします。
メンテナンス
その後は3か月~6か月に1回の頻度でメンテナンスを受けます。口腔内の状態を確認することはもちろんですが、普段のケアでは落としきれない汚れを歯科医院で定期的に除去してもらうことが重要です。
定期的なメンテナンスではしっかりと歯磨きができているかを確認したり、フッ素の塗布を受けたりすることもできます。普段のケアで気になることや気になる症状などがあれば、定期検診で確認しましょう。
歯科でMTMをするときの費用

MTM(メディカルトリートメントモデル)にかかる費用ですが、検査から評価、予防プログラムの立案、ケアなどを含めて1万5,000円ほどが一般的です。
なお、口腔内の常在菌の状態を検査し、虫歯や歯周病のリスクを確認するための唾液検査(サリバテスト)には別途3,000円程度かかります。それ以外にも、CT検査が必要と判断された場合には、5,000円〜1万5,000円ほどかかるでしょう。
MTMでの検査の項目については歯科医院によって異なるため、事前に確認してください。
MTMの重要性

歯科を受診する目的として、虫歯の予防を挙げる方は少ないかもしれません。多くの場合は「虫歯の治療のため」「早期発見のため」「失った歯を補うため」などではないでしょうか。
しかし、そのように何らかの症状を改善することを目的とした歯科医療では、再発を繰り返すケースが非常に多いのです。そして結果的に健康な歯を失う方が多いのも現状です。
MTMは「悪くなったら治せばいい」という考えではなく「健康な歯を維持していく」という目的から生まれたプログラムです。患者さん自身が自分の口腔内の状態やリスクを理解したうえで自分自身に合った予防をおこなうため、歯の寿命を延ばすことに繋がります。
また、歯科医師や歯科衛生士のサポートのもと、患者さん自身が変化を実感できることにより、セルフケアのモチベーション維持にも役立つでしょう。
歯の定期検診とMTMの違い

虫歯を予防するために定期検診を受けている方もいるかもしれません。もちろん、定期検診も虫歯・歯周病の予防や早期発見・早期治療に役立つものではありますが、個々の将来的なリスクを予防するという観点からいうと物足りない内容であることはいうまでもありません。
生活習慣や口腔内の状態、歯磨きのクセなどは一人ひとり異なるものです。MTMは口腔内の状態やリスクをしっかりと確認したうえで、土台からしっかりと口腔内の健康状態を改善していくことを目的としています。
また、患者さんそれぞれの生活習慣や口腔内の状態に合わせたオーダーメイドのプランを立案できることもMTMの強みといえるでしょう。
定期検診のように、ただ歯垢や歯石を除去し、歯磨き指導を受けるだけでなく、患者さん自身が「自分の歯の健康を維持していこう」と改めて実感できる機会にもなります。
まとめ

MTM(メディカルトリートメントモデル)とは、患者さん一人ひとりに合わせた予防プログラムのことです。MTMでは事前に検査をおこない、現在の口腔内の状態や将来的なリスクを確認したうえで自分に合ったセルフケアを身につけることができます。
虫歯や歯周病を繰り返す方などは、MTMを活用してまずは自分の口腔内の状態をしっかりと確認するとよいでしょう。
歯科医院に対するイメージが「悪い箇所を治す場所」という考えから「お口の健康を維持するために通う場所」という考えに変わるよう、歯科医師や歯科衛生士がサポートいたしますので、ぜひMTMをご活用ください。
予防歯科を検討されている方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
ARTICLE
SEARCH
ARCHIVE
CATEGORY
- CAD/CAM冠
- IPR
- MTM
- インビザライン
- インビザライン・エクスプレス
- インビザライン・コンプリヘンシブ
- インビザライン・モデラート
- インビザライン・ライト
- インビザライン矯正
- インプラント治療
- オールセラミック
- カウンセリング
- ジルコニア
- ジルコニアセラミック
- セラミック
- セラミック歯
- セラミック治療
- デメリット
- デンタルローン
- ハイブリッドセラミック
- ブラケット
- ブリッジ
- ホワイトニング
- マウスピース
- マウスピース型
- マウスピース矯正
- メタルタトゥー
- メタルボンド
- メリット
- メンテナンス
- ラミネートベニア
- リスク
- ワイヤー
- ワイヤー矯正
- 予防歯科
- 二酸化ジルコニウム
- 人工ダイヤモンド
- 仮歯
- 保定期間
- 保険適用
- 健康保険
- 入れ歯
- 全体矯正
- 出っ歯
- 前歯
- 医療費控除
- 受け口
- 口腔外科
- 噛み合わせ
- 噛み合わせ治療
- 嚙み合わせ
- 外科治療
- 天然歯
- 失敗
- 奥歯
- 定期検診
- 定期診察
- 審美
- 審美性
- 小児歯科
- 抜歯
- 歯ぎしり
- 歯並び
- 歯列矯正
- 歯周病
- 歯周病菌
- 歯型
- 歯科技工士
- 歯科検診
- 歯科矯正
- 歯茎
- 治療期間
- 症例
- 矯正期間
- 矯正歯科
- 矯正装置
- 精密検査
- 自由診療
- 自費診療
- 虫歯
- 虫歯治療
- 虫歯菌
- 被せ物
- 親知らず
- 詰め物
- 費用
- 通院
- 通院頻度
- 部分入れ歯
- 部分矯正
- 金属
- 金属アレルギー
- 銀歯
- 顎関節症
- 食いしばり