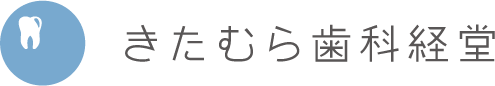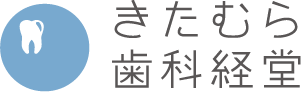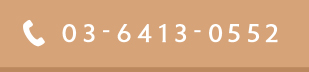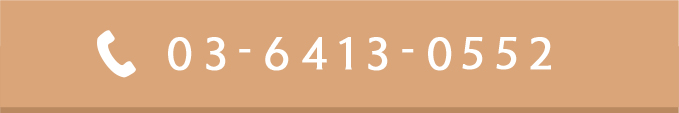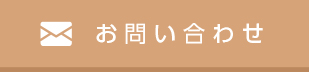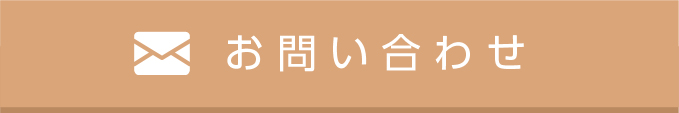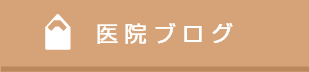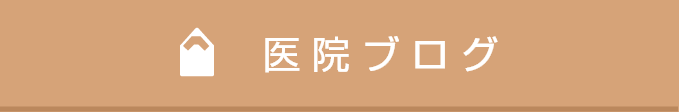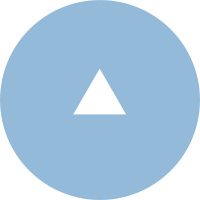2025.09.30更新
子どもとフッ素:メリット・注意点や安全な使い方を解説
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

子どもの歯の健康を守りたいと考える保護者の方は多いでしょう。虫歯は進行すると痛みだけでなく、治療に時間や費用がかかるため、予防することが非常に重要です。
そのようななかで、注目されているのがフッ素の活用です。特に子どもの虫歯を予防するためには、日常生活のなかでフッ素を上手に取り入れることが効果的だとされています。
しかし「フッ素は安全なの?」「どのように使えばいいの?」といった疑問を持つ保護者の方も多いのではないでしょうか。
今回は、フッ素の基礎知識から子どもへの具体的な活用方法、注意点、そして歯科医院でのフッ素塗布の費用について解説します。子どもの将来の歯の健康を守るために、ぜひ参考にしてください。
フッ素とは

フッ素とは、自然界に広く分布する元素の一つで、私たちの体の中にも存在しています。歯や骨の構成にも関わる重要なミネラルであり、歯科分野ではフッ化物として虫歯予防に活用されています。
特に歯の表面を強化する効果があるため、お子さんの成長期の口腔ケアに欠かせない存在となっています。
フッ素の効果
フッ素には主に以下の3つの効果があります。
1つ目は、再石灰化の促進です。日常の飲食により歯の表面が酸で溶かされても、フッ素の働きによって唾液中のミネラルが歯に再吸収され、表面が再び硬くなります。
2つ目は、歯質の強化です。フッ素が歯に取り込まれることで、エナメル質が強化され、酸に溶けにくい強い歯になります。
3つ目は、虫歯菌の抑制です。フッ素には虫歯菌が活動を抑える働きがあるため、虫歯の進行を防ぐ効果も期待できます。
これらの作用により、フッ素は予防歯科の分野で高く評価されており、子どもから大人まで広く利用されています。
子どもにフッ素を活用するメリット

ここでは、子どもにフッ素を活用するメリットについて解説します。
虫歯予防に高い効果を発揮する
子どもの歯は大人に比べてエナメル質が薄く、虫歯になりやすい傾向があります。
フッ素はその弱い歯を強化し、酸による脱灰を抑える効果があります。また、歯にダメージが加わっても、唾液とともにフッ素が作用することで再石灰化が促進され、初期の虫歯であれば自然修復されることもあります。
フッ素は虫歯の進行を防ぐだけでなく、初期の虫歯を治す可能性もあるのです。
歯質を強くして虫歯になりにくい歯を育てる
フッ素は歯の表面に取り込まれると、エナメル質の構造をより硬く、酸に強い性質へと変化させます。これにより、フッ素を継続的に取り入れている子どもは、虫歯に対する抵抗力の高い歯を持つことができます。
特に、生えたばかりの永久歯は非常に虫歯になりやすいため、この時期にフッ素を活用することは将来的な口腔の健康にも大きな影響を与えます。
虫歯菌の活動を抑える効果がある
フッ素には、虫歯の原因菌が酸をつくる働きを抑える作用もあります。これにより、歯の表面に酸が長時間とどまるのを防ぎ、歯が溶け出すリスクを下げることができます。特に、歯みがきが十分にできない年齢の子どもにとっては、フッ素の力が大きな助けとなります。
保護者の方のケアの補助として活用できる
小さな子どもは自分で丁寧に歯を磨くことが難しいため、どうしても磨き残しが多くなりがちです。特に奥歯の溝や歯と歯の間などは、虫歯のリスクが高い部分です。そういった部分にもフッ素が行き渡ることで、磨き残しによる虫歯の発生を予防する効果が期待できます。
ご家庭でのケアとフッ素の活用を組み合わせることで、より安心して子どもの口腔管理を行うことができます。
子どもにフッ素を使うときの注意点

ここでは、子どもにフッ素を使うときの注意点について解説します。
フッ素の過剰摂取に注意する
フッ素は虫歯予防に効果的な成分ですが、過剰に摂取するとフッ素症と呼ばれる状態を引き起こす可能性があります。特に子どもは身体が小さいため、少量でも過剰になるリスクがあります。フッ素症は歯の表面に白い斑点が現れる症状で、美観に影響する場合もあります。
フッ素入りの歯みがき粉を使う際には、年齢に応じた適量を守ることが大切です。たとえば、6歳未満の子どもには、米粒大の量を目安とし、うがいができない年齢の子には無理にフッ素入りの歯みがき粉を使わないようにしましょう。
飲み込まないように注意を促す
子どもは歯みがき粉をおいしいと感じて飲み込んでしまうことがありますが、これもフッ素の過剰摂取につながる原因の一つです。
特にフレーバー付きの歯みがき粉は子どもにとってお菓子のような存在になってしまうこともあるため、保護者の方が使用量を管理し、飲み込まないように指導することが重要です。また、歯みがきのあとにしっかりうがいをする習慣も身につけさせましょう。
フッ素塗布の頻度やタイミングに注意する
歯科医院で行われるフッ素塗布は効果が高い一方で、やみくもに頻繁に行えば良いというわけではありません。一般的には3ヶ月から6ヶ月に1回が適切とされています。
また、永久歯が生え始めるタイミングや、虫歯のリスクが高い子どもに対しては、歯科医師の判断に基づいて塗布の回数を調整することが望ましいです。個々のリスクに応じて、歯科医師と相談しながら活用していくことが大切です。
市販のフッ素製品との併用は慎重に
家庭でのフッ素ケア製品と、歯科医院でのフッ素塗布を併用する場合は、トータルのフッ素摂取量を意識する必要があります。
市販のフッ素入りマウスウォッシュやジェル、タブレットなどを過剰に使用すると、知らず知らずのうちにフッ素の摂取量が上限を超えてしまうことも考えられます。フッ素製品を複数併用する際には、歯科医師や歯科衛生士に相談し、適切な使用方法を確認しておくと安心です。
子どものフッ素の取り入れ方

ここでは、子どものフッ素の取り入れ方について解説します。
フッ素入りの歯みがき粉を活用する
もっとも手軽にフッ素を取り入れる方法が、フッ素入りの歯みがき粉を使うことです。市販の子ども向け歯みがき粉は、年齢に応じてフッ素濃度が調整されています。
例えば、6歳未満の子どもには500ppm程度、6歳以上では1000ppm〜1450ppmまでの濃度が推奨されています。歯みがき粉の使用量も年齢によって異なり、3歳未満なら米粒大、3〜6歳ならグリーンピース大を目安にすると良いでしょう。
毎日の歯みがきのなかで、自然にフッ素を取り入れる習慣を作ることが大切です。
フッ素入りの洗口液を取り入れる
フッ素入りの洗口液を取り入れる方法もあります。1日1回、フッ素入りの洗口液でうがいをするだけで、歯全体にフッ素を行き渡らせることができます。
ただし、うがいがしっかりできる年齢(おおむね4〜5歳以上)になってから使用を開始するのが望ましいです。
フッ素配合ジェルを活用する
歯みがきのあとに塗るタイプのフッ素ジェルなどの製品もあります。これらは歯全体にフッ素を直接塗布できるため、歯みがき粉とは異なる角度からの予防が期待できます。
特に、虫歯リスクの高いお子さまには、寝る前などに使用することで、フッ素が歯にとどまる時間を長く保てるという利点があります。
ただし、こちらも使用量や頻度に注意し、歯科医院でのアドバイスを受けながら行うことが重要です。
歯科医院での定期的なフッ素塗布
ご家庭でのケアとあわせて、定期的に歯科医院でフッ素塗布を受けることが効果的です。専門の器具と高濃度のフッ素を使用するため、自宅では届きにくい奥歯や歯と歯の間までしっかりケアすることができます。
3ヶ月〜6ヶ月に1回を目安に通院することで、虫歯の早期発見・予防にもつながります。子ども自身に歯医者さんに通う習慣を身につけさせることも、将来の歯の健康を守るうえで大切なポイントです。
歯科医院で受けられるフッ素塗布の費用

歯科医院で行われるフッ素塗布の費用は、保険適用の有無や自治体の支援制度によって異なります。多くの地域では、乳幼児や小児に対して子ども医療費助成制度が適用されるため、自己負担がない場合もあります。
一方、助成がない場合や自由診療でのフッ素塗布の場合、1回あたりの費用はおおよそ1,000円〜3,000円程度が一般的です。歯科医院によって料金設定が異なるため、事前に確認しておくと安心です。
また、定期検診の一環としてフッ素塗布を行う場合は、検診費用とあわせて請求されることがあります。自治体によっては1歳半健診や3歳児健診の場で無料でフッ素塗布を受けられるところもありますので、お住まいの地域の情報も確認しておきましょう。
まとめ

子どもの歯を虫歯から守るためには、日々のケアに加えてフッ素を上手に活用することが非常に有効です。フッ素には歯を強くし、虫歯菌の活動を抑える効果があり、家庭での歯みがきや洗口液、さらには歯科医院でのフッ素塗布など、さまざまな取り入れ方が存在します。
ただし、過剰摂取や誤った使用法には注意が必要であり、年齢や状況に応じた適切な方法を選ぶことが大切です。歯科医師や歯科衛生士のアドバイスを受けながら、子どもの成長に合わせたケアを続けていくことで、将来の健康な歯並びや口腔環境にもつながります。
フッ素はあくまで補助的なサポートであり、基本は毎日の丁寧な歯みがきと保護者の方の見守りです。正しい知識をもとに、安心してフッ素を取り入れていきましょう。
お子さんのお口の健康を守りたいとお考えの方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2025.06.10更新
子どもが虫歯になったらどうやって治療する?予防法も
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

子どもの歯は虫歯になりやすく、進行が早いです。乳歯だからといって放置すると、永久歯や噛み合わせに悪影響を与えるおそれもあります。
「子どもの虫歯はどのように治療するの?」「虫歯にさせないためにはどうすればよいの?」と考えている保護者の方もいるでしょう。
この記事では、子どもが虫歯になったときの治療法や虫歯を予防する方法、虫歯治療を受けられる年齢について解説します。お子さまの健康な歯を守るために、ぜひ参考にしてください。
子どもの虫歯の特徴

子どもの虫歯には、以下の特徴があります。
進行が早い
乳歯は石灰化が進んでいないため、永久歯に比べて歯質がやわらかいです。また、乳歯の表面のエナメル質は、永久歯のエナメル質の半分ほどの厚さしかありません。そのため、虫歯の進行が早く、短期間で神経に到達する恐れがあります。
気づきにくい
初期段階の虫歯は白っぽく濁った色をしていることが多く、保護者の方が見ても気づきにくいです。また、虫歯が進行して軽度の痛みが生じても、子どもは痛みをうまく訴えられないことがあります。
痛みが激しくなるまで、保護者の方が気づかず時間が経過することも多いでしょう。乳歯の虫歯は進行が早いため、痛みが激しくなった頃には神経まで到達していることも少なくありません。
永久歯に悪影響を与える
乳歯が虫歯になった場合、永久歯に悪影響を与えかねません。歯の根元まで虫歯菌が感染して膿が溜まると、変色した永久歯が生えてきたり、本来の歯の形ではない状態で生えてきたりする場合があります。
また、虫歯を放置して早期に乳歯を失うと、隣の歯が倒れてきて永久歯が生えてくるスペースがなくなり、歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼす恐れもあります。
子どもが虫歯になったらどうやって治療する?

前述したとおり、子どもの虫歯は気づきにくく進行が早いため、早めに治療することが大切です。ここでは、子どもが虫歯になったときの治療方法について、虫歯の進行段階別に解説します。
初期の虫歯
歯の表面のエナメル質が溶けている虫歯の初期段階であれば、フッ素を塗布して再石灰化を促し、様子を見ることが多いです。再石灰化とは、溶け出したカルシウムやリンが再び歯の表面に取り込まれ、エナメル質が修復されることです。
再石灰化は、唾液によっても行われます。そのため、歯科医院でのフッ素塗布だけでなく、間食を控えて普段のブラッシングをきちんと行うことも大切です。家庭で適切に歯磨きを行えるよう、ブラッシング指導も行います。
エナメル質の虫歯
エナメル質が溶け、穴が空いた段階になると、虫歯の部分を削ってレジン(歯科用プラスチック)や金属で詰め物をします。状態によっては、フッ素を塗布して様子をみる場合もあります。自覚症状は少なく気づきにくいため、歯科検診で発見されることも多いです。
歯の表面のみの治療なので、通院回数は1回程度です。
象牙質の虫歯
エナメル質の内側にある象牙質まで虫歯が進行すると、冷たいものや甘いものがしみることがあります。エナメル質の虫歯と同様に、虫歯の部分を削って詰め物をします。
歯を大きく削った場合は、詰め物をするための型取りが必要です。小さく削って詰めるだけなら1回の通院で治療できますが、型取りをする場合は2回の通院が必要となります。
神経まで達している虫歯
虫歯が神経まで進行すると、何もしていなくても強い痛みを生じることがあります。この段階になると、根管治療が必要です。
根管治療とは、神経や血管が入った根管の内部を取り除き、清掃する治療です。虫歯の部分を削ったあと根管治療を行い、被せ物をして噛む機能を回復させます。早くに歯を失うと、歯並びや噛み合わせに影響する場合があるため、生え変わりまで歯を維持させることが大切です。
根管治療は何度かに分けて行うため、4〜6回程度の通院が必要となります。
歯根まで進行している虫歯
虫歯が進行して歯根まで到達し、ほとんど残っていない場合は抜歯が必要です。乳歯を早期に失うと、隣接する歯が倒れてくる可能性があります。そのため、永久歯が正しい位置に生えるスペースを確保するための治療を行う場合があります。
虫歯の治療は何歳から受けられる?

子どもが虫歯治療を受けられる年齢は3歳頃が目安になります。3歳頃になると、歯科医院の椅子に座り、口を開けてじっとしていられるようになる子どもが多いためです。
治療を受けられるかどうかは、子ども自身が協力して治療が受けられるかどうかがポイントです。4〜5歳頃になると、歯科医師とのコミュニケーションがとりやすくなるため、治療を進めやすくなるでしょう。
治療を行う際は、無理に治療を進めるのではなく、歯科医院の椅子に座ったり、口を開けたりして歯科医院に慣れることから始めます。恐怖心を抱くと治療をスムーズに進められなくなるためです。
また、小さい頃から定期検診を受けておくと、虫歯になったときにスムーズに治療を始められます。乳歯が生え始める生後6ヶ月ごろ、遅くても乳歯が生えそろう1歳半頃には受診するとよいでしょう。
子どもが虫歯になるのを防ぐためには

子どもが虫歯になるのを防ぐためには、保護者がサポートすることが大切です。ここでは、子どもの虫歯を予防する方法を紹介します。
毎日の歯磨きを習慣づける
子どもの虫歯予防の基本は、毎日の歯磨きです。毎食後と寝る前に行うのが理想ですが、最低でも1日1回は歯を磨きましょう。就寝中は唾液が少なくなり虫歯のリスクが高まるため、寝る前の歯磨きは習慣にしてください。
歯磨きは歯が生え始めた頃から開始し、自分で歯ブラシを握れるようになったらストッパーがついた歯ブラシを持たせましょう。歯磨きの絵本を読んだり、子どもが好きなキャラクターの歯ブラシやフルーツ味の歯磨き粉を使用したり、楽しく取り組めるよう工夫しましょう。
保護者の仕上げ磨きを徹底する
永久歯が生える12歳頃までは保護者が毎日仕上げ磨きを行いましょう。子どもは、大人に比べて手先を器用に動かせず、歯のすみずみまで丁寧に磨くことは難しいためです。毎日最低でも1日1回、就寝前に仕上げ磨きを続けると、虫歯予防につながります。
子どもは上顎の真ん中の歯と歯の間や、奥歯と奥歯の間、奥歯の溝に虫歯ができやすいため、特に注意して歯を磨いてあげましょう。
食生活を整える
子どもの虫歯を予防するために、食生活を整えることも大切です。虫歯の原因になる細菌は糖分をエサにして酸を作り出し、歯を溶かします。甘いお菓子やジュースを頻繁に摂っていると、口の中に糖分が長時間留まるため、虫歯のリスクが高まるのです。
おやつは決まった時間に与え、だらだらと時間をかけて食べたり飲んだりしないよう声をかけましょう。焼き芋やおせんべいなど、糖分が少なく歯にくっつきにくい食べ物を選ぶのも虫歯予防に効果的です。
フッ素を塗布する
歯が生え始めた生後6ヶ月頃から、フッ素の塗布を行うのも虫歯予防として有効です。フッ素は、歯の表面のエナメル質を強化し、虫歯になりにくい歯にします。また、歯から溶け出したカルシウムやリンを取り込んで修復させる再石灰化も促す効果もあります。
効果は3ヶ月程度持続するといわれているため、虫歯予防のためには3ヶ月に一度程度フッ素を塗布しましょう。また、普段の歯磨きにも市販のフッ素入りの歯磨き粉を使用すると虫歯予防になります。
定期的に歯科医院を受診する
子どもの虫歯を予防するためには、歯科医院での定期検診を受けることも大切です。虫歯は初期段階では見た目で判断しにくく、痛みや違和感などの症状もほとんどありません。子どもは虫歯の進行が早いため、痛みが生じたときには神経まで達している場合もあります。
定期的に歯科医師がチェックすれば早期に発見でき、負担の少ない治療で済む可能性が高くなります。また、歯科医院ではクリーニングやフッ素塗布、ブラッシング指導などを通じて虫歯を予防することも可能です。
痛みや違和感などの症状がなくても、3〜4ヶ月に一度程度は受診するとよいでしょう。
まとめ

子どもの虫歯は進行が早く気づきにくい特徴があります。虫歯になった場合、初期段階で発見できればフッ素の塗布のみで様子をみることもありますが、虫歯が神経まで進行した場合は、虫歯を大きく削って根管治療が必要です。
虫歯を予防するには、毎日保護者が丁寧に仕上げ磨きをし、できるだけ甘いものを減らしましょう。
定期的に歯科医院を受診すると、虫歯になっても早期に発見でき、治療の負担も少なく済みます。フッ素の塗布やクリーニングによって虫歯予防につながるため、症状がなくても歯科医院を受診しましょう。
子どもの虫歯治療を検討されている方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2025.04.08更新
子どもの歯磨きは何歳からはじめる?歯磨きの仕方と仕上げ磨きのコツも
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

「子どもはいつから歯磨きするの?」「歯磨きの方法は?」「歯ブラシの選び方が知りたい」など、子どもの歯磨きについて悩む保護者の方は多いです。子どもは虫歯になりやすいため、適切に歯磨きする必要があるでしょう。
この記事では、子どもの歯磨きを始める年齢や歯磨きの仕方、仕上げ磨きのコツなどを解説します。
子どもの歯磨きは何歳からはじめる?
子どもの歯磨きは、歯が生え始めたら開始しましょう。個人差はありますが、生後6ヵ月頃に下の前歯2本が生え始めます。
初めは、ガーゼを指に巻きつけ、歯を拭くことから始めます。子ども用の小さなブラシで軽く撫でる程度でもかまいません。この時期に意識すべきなのは、汚れを取り切ることではなく、まずは歯磨きに慣れることです。
1歳半頃には上の前歯2本と上下の切歯、1歳半~2歳頃に奥歯が生え始めます。2歳頃には、上下の乳歯20本が全て生え揃う子どもが多いです。乳歯が生え揃った後は、できれば毎食後に歯磨きをしましょう。
ただし、無理やり歯磨きを行うと、お口を開けるのも嫌がったり、歯ブラシを見るだけで泣いたりする可能性があります。子どもの機嫌に合わせ、できるときに歯磨きをするという意識を持つのがよいでしょう。
子どもの歯磨きの仕方

ここでは、子どもの歯磨きの仕方をご紹介します。
子ども用の歯ブラシを使用する
子どもの歯磨きには、子ども専用の歯ブラシを使用してください。大人用の歯ブラシを使用すると、大きすぎて磨けなかったり、毛先が硬くて痛みを感じたりすることがあります。
年齢に合った歯ブラシを選択
子どもの年齢に合わせて、歯ブラシを選択することが大切です。成長には個人差がありますが、歯ブラシのパッケージに記載されている年齢を参考にすると良いでしょう。子どもの手やお口のサイズに合った、歯ブラシを選択できます。
歯科医師や歯科衛生士に相談し、子どもに合わせて歯ブラシを選んでもらうのも方法の一つです。
毛先が丸い歯ブラシを選択
子どものお口の中は敏感で、歯ブラシの毛先のタイプによっては痛みを感じることがあります。そのため、毛先が丸くなっている歯ブラシを選ぶのがよいでしょう。
特に、子どもは力加減が難しく、力強く磨くと痛みを感じることがあります。毛先の丸い歯ブラシを選んでいれば、歯茎を傷つける心配がありません。
子どもの好きなデザインや色のものを選択
毎日使う歯ブラシを、子ども自身に選んでもらうことも良いでしょう。子どもの好きなデザイン、好きな色の歯ブラシを使って歯磨きすれば、歯磨きのモチベーションを保つことができます。
歯ブラシは細かく動かす
歯磨きをする際は、歯ブラシを細かく動かすことを意識してください。1~2本の歯を磨くように、細かく歯ブラシを動かしましょう。
発泡性の少ない歯磨き粉を選ぶ
泡立ちのよい歯磨き粉を使用すると、すぐにお口の中が泡でいっぱいになり、歯磨きがしにくいです。特に、こどもの場合、泡でお口の中がいっぱいになることで、歯磨きがきちんとできていなくても磨き終わったように感じる可能性があります。
そのため、発泡性の少ないジェルの歯磨き粉を選択しましょう。
永久歯が生え揃うまでは仕上げ磨きを行う
子どもだけで十分に歯磨きするのは難しいため、永久歯が生え揃うまでの間は、仕上げ磨きを行うことが推奨されます。「子どもがある程度大きくなっても、仕上げ磨きをするの?」と思われるかもしれません。
しかし、乳歯だけが生えている時期よりも、乳歯と永久歯が両方生えている時期は磨き残しができやすいです。歯並びが変化し続けるため汚れが溜まりやすい場所が変わったり、永久歯と乳歯の大きさが違ったり、しっかりと磨くのが難しいのです。
毎日お口の中をチェックすることで、虫歯の有無や永久歯の生え変わりに異常がないか確認できるのも、仕上げ磨きを実施するメリットです。
仕上げ磨きをしてあげるときのコツ

仕上げ磨きをするときのコツは、以下の通りです。
1歯につき10~20回磨く
磨き残しは粘着性の頑固な汚れのため、1歯につき10~20回は磨きましょう。1本1本丁寧に歯磨きすることで、虫歯を予防できます。
ただし、強い力で歯磨きすると痛みを感じることがあります。毛先が曲がらない程度の力で歯ブラシを握って、優しく磨いてあげてください。
上唇小帯は避ける
上の前歯と前歯の間には、上唇小帯というヒダがあります。上唇小帯に歯ブラシが当たると、強い痛みを感じやすいです。
そのため、上の前歯を磨く際は、上唇小帯に当たらないように気を付けてください。指で上唇小帯を覆いながら、歯磨きをしてあげると良いでしょう。
虫歯になりやすい箇所を重点的に磨く
奥歯の溝や上の前歯の内側など、子どもが虫歯になりやすい箇所は、重点的に仕上げ磨きしましょう。奥歯は「アー」の口、前歯の外側は「イー」の口にしてもらうと、磨きやすいです。
子どもが歯磨きを嫌がるときの対処法

ここでは、子どもが歯磨きを嫌がる際の対処法について解説します。
日頃から口元に触られることに慣れさせる
歯磨きを嫌がる原因の多くが、お口周りや口内を触られるのが嫌いなことです。日頃から子どものお口周りを触り、口元に触れることに慣れさせるとよいでしょう。
日々続ければ、歯ブラシへの抵抗も少なくなるはずです。
歌を歌いながら磨く
歯磨き中に飽きて嫌がる場合、仕上げ磨きの際に話しかけたり、歌ったりするとよいかもしれません。数え歌や歯磨きの歌を歌えば、歯磨きの終わりが分かるようになります。どれくらいで終わるか理解できれば、歯磨きへのモチベーションを維持しやすいといえます。
鏡の前で歯磨きを行う
子どもの歯磨きが嫌いな理由として、歯磨き中に何をされているかわからないという不安も挙げられます。そのため、大きな鏡の前で歯磨きしたり、お子様に鏡を持ってもらいながら歯磨きをしたり、何をしているのか見せてあげましょう。
不安を解消できれば、歯磨きを嫌がらなくなるかもしれません。
ごほうびシールやスタンプラリー
1回の歯磨きごとに、シートにシールを貼ったり、スタンプを押したりと楽しみを作ってみましょう。毎回の歯磨き後に楽しみがあれば、子どもの歯磨きのモチベーションが高まるはずです。
また「シールが何個たまったら大きな公園に行く」など、子どもの願い事を叶えてあげるシステムを作ってもよいでしょう。お子さまが楽しく歯磨きに取り組めるよう、工夫してあげてください。
難しい場合は寝る前だけでも磨く
歯磨きへの苦手意識が強い場合、こまめな歯磨きが難しい場合があります。「毎食後の歯磨きは絶対!」「無理やりにでも歯磨きをする」など、大人が根を詰めすぎると、逆に子どもは嫌がってしまうかもしれません。歯磨きに対する苦手意識が強まることもあるでしょう。
子どもへの無理やりな歯磨きは、子どもにとっても大人にとっても大きなストレスになってしまいます。そのため、1日1回だけは歯磨きするなど、必要最低限の目標を設定しましょう。
子どもが大きくなるにつれ、いずれ自然と歯磨きはできるようになります。歯磨きへの苦手意識がなくなるまでの間は、こまめな水分補給とうがいで汚れを洗い流してください。
また、歯科医院でお口を開ける練習や歯磨きの練習をするのも有効です。
まとめ

子どもの歯磨きは、歯が生え始めたら開始しましょう。お子様が小さいうちは、無理やり歯磨きせず、まずは歯磨きの習慣を身につけることが大切です。
歯が生え揃ったら、年齢に合わせた歯ブラシを選択し、1本1本丁寧に歯磨きしましょう。小学校に入った後も、永久歯が生え揃うまでの間は仕上げ磨きをしてあげてください。
子どもの歯磨きにお悩みの方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2024.12.10更新
子どもも歯科検診を受けた方が良いの?事前に知っておきたいことまとめ
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

子どもの口の中の健康を守るためには歯の健康管理が重要です。歯科医院を受診して歯科検診をすすめられた方も少なくないでしょう。
しかし、なかには「子どもの歯科検診って本当に必要なの?」「いつから始めればいいの?」といった疑問をお持ちの保護者の方も多いのではないでしょうか。
歯医者でおこなう歯科検診は、虫歯の予防だけでなく子どもの口内の発達状態を確認する大切な機会となります。子どものうちから定期的にケアを行うことにより、将来的な歯のトラブルを防ぐことが期待できるでしょう。
そこで今回は、子どもの歯科検診の開始時期や検診内容、受診頻度などについて解説します。子どもの歯科検診について興味のある方は、ぜひ参考にしてみてください。
子どもが歯科検診を受けるべき理由

子どもの歯は生え変わるため、虫歯になっても問題ないと考えている保護者の方も多いのではないでしょうか。
しかし、子どもの定期的な歯科検診は、歯や口の中の健康には欠かせません。定期検診では、お子さまの口の中の状態を確認し、成長に合わせた適切なアドバイスを受けられます。お子さまの成長をサポートするために必要不可欠です。
ここでは、子どものうちから歯科検診を受けるべき理由について解説します。
虫歯などの早期発見につながる
乳歯から永久歯に生え変わる時期は、虫歯や歯並びの問題が発生しやすいといわれています。歯科検診を受けていれば、万が一トラブルが起こっていても早期発見・早期治療ができるので、お子さまの将来的な歯の健康を守ることが期待できるでしょう。
虫歯などのトラブルを初期段階で発見できれば、痛みを伴う大きな治療を避けられます。
正しい歯磨きの仕方が身に付く
歯科検診ではブラッシング指導もおこないます。そのため、正しい歯磨きの方法を身につけるきっかけとなるでしょう。子どものうちに正しい方法で歯を磨く習慣を身につけることは、生涯の歯の健康に大きく影響するため非常に重要です。
歯並び・噛み合わせの異常を早期に発見できる
歯並びや噛み合わせの異常は早期発見することがポイントになります。歯並び・噛み合わせに異常があると、うまく発音できなかったり食べ物を噛みきれなかったりといったトラブルの原因になります。また、将来的に顎関節症などを引き起こすリスクが高くなるでしょう。
子どもの歯科検診では、歯並びや噛み合わせに問題がないかも確認してもらえます。万が一、歯並び・噛み合わせに異常があっても、定期的に歯科医院に通っていれば適切な時期に矯正治療を始められるでしょう。
子どもの歯科検診でやること

子どもの歯科検診では、どのようなことがおこなわれるのか気になってはいませんか。お子さんの歯科検診を円滑に進めるためには、事前の準備が大切です。以下に、子どもの歯科検診でやることについて解説します。
虫歯の有無や歯並び・噛み合わせの確認
歯科医師が専用の器具を使って、お子さまの口の中を確認していきます。特に、乳歯の虫歯は進行が早いため小さな異変も見逃さないよう注意深く確認することが重要です。
歯並びについては、永久歯の生え変わり時期に合わせて、将来的な歯列矯正の必要性も判断します。また、上下の歯の噛み合わせをチェックし、あごの発達状態の確認をおこなう場合もあるでしょう。
ブラッシング指導・食事指導
お子さまの歯磨き習慣をチェックし、年齢や歯並びに応じたブラッシング方法を指導していきます。ブラッシング指導は、歯ブラシの選び方や持ち方、磨き残しが起こりやすい部分の磨き方などを指導し、自宅での歯磨きの質を向上させることを目的として行われます。
また、普段の食生活をうかがって虫歯予防の観点から、おやつの選び方や食事の摂り方についてもアドバイスをおこないます。
クリーニング
歯科医師・歯科衛生士が専用の器具を使用して、プラークや歯石の除去をおこないます。通常の歯磨きでは取りきれない部分に付着した汚れも、クリーニングで除去することで虫歯になりにくい清潔な環境に整えていきます。
クリーニングは、子どもの年齢や状態に合わせて痛くない方法で実施するケースが多いでしょう。日頃から歯のクリーニングを受ける習慣を身につけていれば、歯科治療に対する恐怖心を軽減することが期待できます。
シーラント
シーラントとは、歯の溝をプラスチック樹脂で埋める処置です。乳歯の奥歯や生えたばかりの6歳臼歯は虫歯になりやすい部分です。奥歯の溝は深いため汚れが溜まりやすく、歯ブラシが届きにくい環境になります。
ブラッシングだけでは虫歯リスクが高いと判断された場合は、虫歯予防としてシーラント処置をおこなうケースが一般的です。奥歯の溝を特殊な樹脂で埋めることで、食べかすが詰まりにくくなり、ブラッシングで容易に汚れを除去できるようになります。
痛みを伴わない安全な予防処置として注目されています。
フッ素塗布
フッ素には歯の質を強化して唾液の再石灰化作用を助ける働きがあります。また、虫歯菌の活動を抑制する働きもあるため、虫歯予防に効果的な処置です。歯を削る必要がないため小さな子どもでも抵抗なく受けられるでしょう。
フッ素塗布にかかる時間は数分です。フッ素塗布を受ける頻度は、一人ひとりのお口の中の状態によって異なります。
特に、乳歯から永久歯に生え変わる時期は、虫歯になるリスクが高いです。新しく生えてきた歯を守るためにも、定期的にフッ素塗布を受けることが推奨されます。
歯科検診は何歳から?

歯科検診は、乳歯が生え始める生後6か月頃から受けることが可能です。口の中の発達状態を確認しながら、適切な仕上げ磨きの方法などを確認することができるでしょう。
また、乳歯が次々と生えてくる1歳前後から開始する場合もあります。生えたての歯は、歯の質が弱く虫歯になりやすい状態です。
乳歯が生え始めたころから口腔ケアを行う習慣を身につけ、正しい食生活についてのアドバイスを受けることで健康な口内環境を保つことができるでしょう。特に2~3歳は乳臼歯が生え始め、食事も幼児食へと移行する時期になるため、虫歯になりやすく細やかな観察が必要です。
さらに、乳歯から永久歯への生え変わり時期である5〜6歳では、あごの発達状態もチェックする必要があります。子どものうちから歯科医院で定期検診を受けていれば、成長段階に合わせた適切なアドバイスや処置を受けることが可能です。
歯科検診はどのくらいの頻度で受けるの?

歯科検診の通院頻度は、お子さんの年齢やお口の中の状態によって異なります。一般的な目安として、3〜6か月に1回の頻度で検診を受けることをすすめられるケースが多いでしょう。
虫歯を予防するためには、乳歯が生え始める時期からしっかりとケアを行うことが重要です。そのため、虫歯になりやすい場合は、2〜3か月に1回の頻度で検診を受けることが望ましいとされています。
また、永久歯への生え変わりが始まる5〜6歳頃は、特に注意深く観察する必要があります。この時期は、あごの発達状態や永久歯の生え具合をチェックし、必要に応じて予防処置をおこないます。
そのため、3か月に1回の頻度で受診をすすめられる場合もあるでしょう。歯並びや噛み合わせが気になる場合も、短い間隔で検診を受けて経過観察する必要があります。このように、通院頻度はお子さんによって異なるため、歯科医師の指示に従いましょう。
まとめ

子どものうちから歯科検診を受けることは、健康な歯を育むためには必要不可欠だといえます。定期的に歯科検診を受けることで、虫歯や歯並びの問題を早期に発見できるでしょう。
さらに定期検診では、お子さんの成長に合わせた専門的なアドバイスを受けることができます。歯科医院で指導された内容に基づいて、ご家庭でも効果的なケアが実施できるでしょう。
定期検診を通じて子どもが自然と歯の健康に関心を持つようになることも期待できます。お子さまのお口の健康を守るためにも、定期的に歯科検診を受けましょう。
お子さんのお口の健康を守りたいとお考えの保護者の方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
ARTICLE
SEARCH
ARCHIVE
CATEGORY
- CAD/CAM冠
- IPR
- MTM
- インビザライン
- インビザライン・エクスプレス
- インビザライン・コンプリヘンシブ
- インビザライン・モデラート
- インビザライン・ライト
- インビザライン矯正
- インプラント治療
- オールセラミック
- カウンセリング
- ジルコニア
- ジルコニアセラミック
- セラミック
- セラミック歯
- セラミック治療
- デメリット
- デンタルローン
- ハイブリッドセラミック
- ブラケット
- ブリッジ
- ホワイトニング
- マウスピース
- マウスピース型
- マウスピース矯正
- メタルタトゥー
- メタルボンド
- メリット
- メンテナンス
- ラミネートベニア
- リスク
- ワイヤー
- ワイヤー矯正
- 予防歯科
- 二酸化ジルコニウム
- 人工ダイヤモンド
- 仮歯
- 保定期間
- 保険適用
- 健康保険
- 入れ歯
- 全体矯正
- 出っ歯
- 前歯
- 医療費控除
- 受け口
- 口腔外科
- 噛み合わせ
- 噛み合わせ治療
- 嚙み合わせ
- 外科治療
- 天然歯
- 失敗
- 奥歯
- 定期検診
- 定期診察
- 審美
- 審美性
- 小児歯科
- 抜歯
- 歯ぎしり
- 歯並び
- 歯列矯正
- 歯周病
- 歯周病菌
- 歯型
- 歯科技工士
- 歯科検診
- 歯科矯正
- 歯茎
- 治療期間
- 症例
- 矯正期間
- 矯正歯科
- 矯正装置
- 精密検査
- 自由診療
- 自費診療
- 虫歯
- 虫歯治療
- 虫歯菌
- 被せ物
- 親知らず
- 詰め物
- 費用
- 通院
- 通院頻度
- 部分入れ歯
- 部分矯正
- 金属
- 金属アレルギー
- 銀歯
- 顎関節症
- 食いしばり