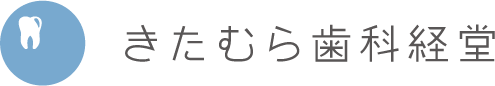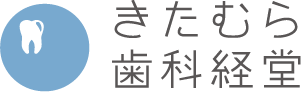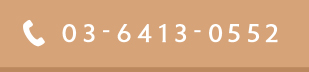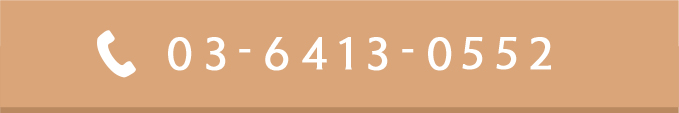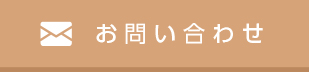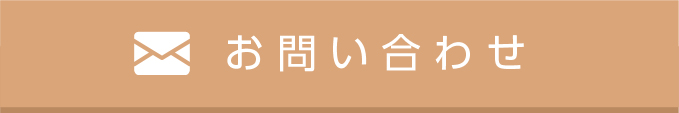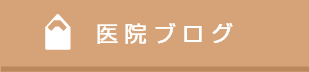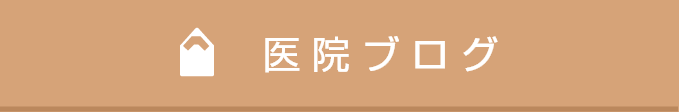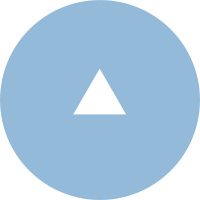2025.03.11更新
歯のクリーニングはどれくらいの頻度で受けるべき?メリットと注意点も
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

虫歯や歯周病などを予防するためには、定期的に歯のクリーニングを受けることが重要です。
しかし、どのくらいの頻度で通えばよいか分からないとお悩みの方は少なくありません。歯のクリーニングの頻度は、お口の状態や生活習慣によって異なります。
この記事では、適切な歯のクリーニングの頻度やメリット、注意点について解説します。
歯のクリーニングを受ける頻度

口内環境や生活習慣によって歯垢や歯石が溜まるスピードが異なるため、歯のクリーニングの頻度については個人差があります。ここでは、一般的な歯のクリーニングを受ける頻度について解説します。
セルフケアが適切な方
セルフケアによる磨き残しが少ない方の場合、虫歯や歯周病のリスクは少ないといえます。例えば、フロスや歯間ブラシも使用している方が挙げられるでしょう。他にも、以下の特徴がある方が挙げられます。
- 歯磨きが上手な方
- 歯並びがよい方
- 毎食後に歯磨きしている方
- フロスや歯間ブラシも使用している方
日々の歯磨きだけでも口内の汚れをしっかり落とせているため、歯のクリーニングは約3~6ヵ月に1回の頻度でかまいません。
歯磨きが苦手な方・歯並びが悪い方
歯磨きが上手にできていない方や歯磨きの頻度が低い方の場合、磨き残しができやすいです。また、歯と歯の重なりが多い方、反対に歯と歯の間に隙間が空いている方の場合、きちんと歯磨きをしていても汚れが溜まることがあります。
- 歯磨きが苦手
- 歯磨きの回数が少ない方
- 歯並びが悪い方
上記のような方の場合、虫歯や歯周病のリスクが高くなるため、約1~2ヵ月の頻度で歯のクリーニングを受けましょう。定期的な歯のクリーニングにより、虫歯や歯周病のリスクを下げ、口臭の予防にもつながります。
歯周病の方
歯周病がある方も、より頻繁にクリーニングを受けるべきでしょう。
- 歯茎から出血しやすい方
- 歯周病と診断された方
- 歯周病が進行している方
上記の方の場合は、約1~2ヵ月に1回の通院が必要といえます。歯茎から出血する原因は、磨き残しがあり、歯茎が炎症を起こしているからです。放置すると慢性的な歯肉炎になり、いずれは歯周病を発症します。
虫歯になりやすい方
きちんと歯磨きをしていても、口内環境や食生活によって虫歯のリスクは変動します。特に、食生活が乱れている方や口内が乾燥しやすい方の場合、虫歯リスクが高いので注意が必要です。
また、虫歯治療を受けた回数が多い方も、詰め物や被せ物の隙間から虫歯になることがあります。
- 甘いものを好んでよく食べる方
- 間食が多い方
- 口呼吸の方
- 唾液の量が少ない方
- 虫歯治療を受けた回数が多い方
上記に当てはまる方は、約1~2ヵ月に1回のクリーニングが適切でしょう。定期的に歯科に通院すれば虫歯の有無をチェックしてもらえるため、虫歯を未然に防ぐ効果があります。
歯石が付きやすい方
歯石の付きやすい方の場合、約1~2ヵ月に一度の頻度で歯のクリーニングを受けると良いでしょう。歯石の付きやすさは、食生活や口内環境によって左右されます。
- 甘いものを好んでよく食べる方
- 間食が多い方
- 口呼吸の方
- 唾液の少ない方
上記のような方は、定期的に歯科医院でクリーニングを受けて、口内環境を整える必要があります。
飲食物に含まれる糖分を多く摂取すると、細菌が繁殖し、歯垢の生成が促されます。また、唾液の分泌量が少なければ、汚れが洗い流されません。溜まった歯垢は歯石に変化し、歯ブラシでは取れない汚れへと変化します。
着色が付きやすい方
着色が付きやすい方や着色が気になる方は、約2~3ヵ月に1回のクリーニングが推奨されます。
ただし、審美目的の着色除去の場合、保険が適用されないことがあるため注意が必要です。
喫煙習慣のある方
喫煙習慣のある方は、約1~2ヵ月に一度の頻度で歯のクリーニングを受けると良いでしょう。喫煙習慣がある方は、歯周病の発症リスクが高く、かかった場合は進行しやすいです。また、歯石や着色汚れも付着しやすいので、頻繁にクリーニングを受けるべきです。
歯のクリーニングで行うことと流れ

ここでは、一般的な歯のクリーニングの内容と流れを解説します。
検査
まず、お口の状態を把握するために検査を行います。検査の内容は、レントゲン撮影や歯科医師による視診、歯周病検査などです。歯周病検査では、歯周ポケットの深さ、出血や歯の揺れの有無を確認します。
これらの検査を行うことで、歯周病の進行具合や磨き残しの有無、歯石の付き具合を把握でき、患者様に合った治療内容を定められます。
歯磨き指導
検査で磨き残しをチェックした後は、歯磨き指導を行います。歯ブラシの持ち方や当て方、フロスや歯間ブラシの使用方法について、詳しくアドバイスします。
スケーリング
歯垢はやわらかい汚れのため、歯磨きで取り除くことが可能です。
しかし、歯垢は数日経つと歯石へと変化し、歯ブラシでは取り除けなくなります。そのため、超音波を使用した機械やハンドスケーラーという専用の器具を使用して、除去しなければなりません。
フロッシング
フロッシングとは、フロスや歯間ブラシを使用し、歯と歯の間の汚れを取り除くことです。これらの器具を歯と歯の間に通して、歯石の取り残しがないか確認する目的もあります。
ポリッシング
歯の汚れを取り除いた後は、ポリッシングを行います。ポリッシングとは、専用のペーストを使用し、歯の表面を仕上げ磨きすることです。
歯の表面をツルツルに仕上げることで、着色汚れを除去するだけでなく、新たな歯の汚れを付きにくくする効果があります。
フッ素塗布
歯のクリーニングが終わった後は、全体にフッ素塗布を行います。フッ素には、歯の質を強くし細菌の働きを弱める効果があります。
定期的にフッ素塗布を行うことで、虫歯や歯周病を予防できるのがメリットです。
歯のクリーニングを受けるメリット

歯のクリーニングを受けるメリットは、以下の3点です。
口腔トラブルの予防
口内の汚れをすみずみまで除去することで、虫歯や歯周病を予防できます。また、たとえ虫歯になっていたとしても、早期発見・早期治療に繋げられるでしょう。
着色除去・予防
丁寧に歯磨きをしている方でも、日々の食事により着色が付くことがあります。
しかし、普段の歯磨きでは、なかなか着色汚れは取り除けません。定期的な歯のクリーニングにより、本来持っている歯の白さやツヤを取り戻せます。
口臭改善・予防
歯垢・歯石を除去することで、口臭の改善に効果があります。また、虫歯や歯周病の進行も、口臭の原因の1つです。
歯科治療とクリーニングを併用することで、口内の細菌の繁殖を予防します。虫歯や歯周病だけでなく、口臭の予防に効果があるといえます。
歯のクリーニングを受ける際の注意点

歯のクリーニングを受ける際の注意点は、以下の2点です。
出血や痛み
歯垢や歯石が付いている場合、歯茎の炎症により、クリーニングの際に出血する場合があります。また、歯石が多くついている場合、痛みが出たりクリーニング後に知覚過敏のような症状が出たりする場合があるので注意が必要です。
ただし、歯茎の炎症が治まれば、出血や痛みは自然と治まります。多くの場合、クリーニング当日、長くても2~3日程度で症状は落ち着いてきます。
色の濃い飲食物は避ける
クリーニングを受けた後の歯は、外部からの刺激を受けやすい状態です。着色が付きやすいため、色の濃い飲食物は避けましょう。
具体的には、カレーや赤ワイン、コーヒーなどです。また、熱いもの・冷たいものを摂ると、歯がしみる場合もあります。そのため、クリーニング当日は刺激のあるものも控えてください。
まとめ

セルフケアがきちんとできている方の場合、歯のクリーニングは約3~6ヵ月に1回でかまいません。歯磨きが苦手な方や歯石が付きやすい方の場合、虫歯や歯周病のリスクが高いため、約1~2ヵ月に1回と頻繁に通う必要があります。
歯石を放置すると、虫歯や歯周病を発症し歯の寿命を縮めるかもしれません。また、口臭の発生や着色により、人に不潔な印象を与えることもあります。
お口の健康を維持するためには、ご自身に合った歯のクリーニングの頻度を知っておくことが大切です。
歯のクリーニングの頻度や内容について詳しく知りたい方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
2024.12.10更新
子どもも歯科検診を受けた方が良いの?事前に知っておきたいことまとめ
こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

子どもの口の中の健康を守るためには歯の健康管理が重要です。歯科医院を受診して歯科検診をすすめられた方も少なくないでしょう。
しかし、なかには「子どもの歯科検診って本当に必要なの?」「いつから始めればいいの?」といった疑問をお持ちの保護者の方も多いのではないでしょうか。
歯医者でおこなう歯科検診は、虫歯の予防だけでなく子どもの口内の発達状態を確認する大切な機会となります。子どものうちから定期的にケアを行うことにより、将来的な歯のトラブルを防ぐことが期待できるでしょう。
そこで今回は、子どもの歯科検診の開始時期や検診内容、受診頻度などについて解説します。子どもの歯科検診について興味のある方は、ぜひ参考にしてみてください。
子どもが歯科検診を受けるべき理由

子どもの歯は生え変わるため、虫歯になっても問題ないと考えている保護者の方も多いのではないでしょうか。
しかし、子どもの定期的な歯科検診は、歯や口の中の健康には欠かせません。定期検診では、お子さまの口の中の状態を確認し、成長に合わせた適切なアドバイスを受けられます。お子さまの成長をサポートするために必要不可欠です。
ここでは、子どものうちから歯科検診を受けるべき理由について解説します。
虫歯などの早期発見につながる
乳歯から永久歯に生え変わる時期は、虫歯や歯並びの問題が発生しやすいといわれています。歯科検診を受けていれば、万が一トラブルが起こっていても早期発見・早期治療ができるので、お子さまの将来的な歯の健康を守ることが期待できるでしょう。
虫歯などのトラブルを初期段階で発見できれば、痛みを伴う大きな治療を避けられます。
正しい歯磨きの仕方が身に付く
歯科検診ではブラッシング指導もおこないます。そのため、正しい歯磨きの方法を身につけるきっかけとなるでしょう。子どものうちに正しい方法で歯を磨く習慣を身につけることは、生涯の歯の健康に大きく影響するため非常に重要です。
歯並び・噛み合わせの異常を早期に発見できる
歯並びや噛み合わせの異常は早期発見することがポイントになります。歯並び・噛み合わせに異常があると、うまく発音できなかったり食べ物を噛みきれなかったりといったトラブルの原因になります。また、将来的に顎関節症などを引き起こすリスクが高くなるでしょう。
子どもの歯科検診では、歯並びや噛み合わせに問題がないかも確認してもらえます。万が一、歯並び・噛み合わせに異常があっても、定期的に歯科医院に通っていれば適切な時期に矯正治療を始められるでしょう。
子どもの歯科検診でやること

子どもの歯科検診では、どのようなことがおこなわれるのか気になってはいませんか。お子さんの歯科検診を円滑に進めるためには、事前の準備が大切です。以下に、子どもの歯科検診でやることについて解説します。
虫歯の有無や歯並び・噛み合わせの確認
歯科医師が専用の器具を使って、お子さまの口の中を確認していきます。特に、乳歯の虫歯は進行が早いため小さな異変も見逃さないよう注意深く確認することが重要です。
歯並びについては、永久歯の生え変わり時期に合わせて、将来的な歯列矯正の必要性も判断します。また、上下の歯の噛み合わせをチェックし、あごの発達状態の確認をおこなう場合もあるでしょう。
ブラッシング指導・食事指導
お子さまの歯磨き習慣をチェックし、年齢や歯並びに応じたブラッシング方法を指導していきます。ブラッシング指導は、歯ブラシの選び方や持ち方、磨き残しが起こりやすい部分の磨き方などを指導し、自宅での歯磨きの質を向上させることを目的として行われます。
また、普段の食生活をうかがって虫歯予防の観点から、おやつの選び方や食事の摂り方についてもアドバイスをおこないます。
クリーニング
歯科医師・歯科衛生士が専用の器具を使用して、プラークや歯石の除去をおこないます。通常の歯磨きでは取りきれない部分に付着した汚れも、クリーニングで除去することで虫歯になりにくい清潔な環境に整えていきます。
クリーニングは、子どもの年齢や状態に合わせて痛くない方法で実施するケースが多いでしょう。日頃から歯のクリーニングを受ける習慣を身につけていれば、歯科治療に対する恐怖心を軽減することが期待できます。
シーラント
シーラントとは、歯の溝をプラスチック樹脂で埋める処置です。乳歯の奥歯や生えたばかりの6歳臼歯は虫歯になりやすい部分です。奥歯の溝は深いため汚れが溜まりやすく、歯ブラシが届きにくい環境になります。
ブラッシングだけでは虫歯リスクが高いと判断された場合は、虫歯予防としてシーラント処置をおこなうケースが一般的です。奥歯の溝を特殊な樹脂で埋めることで、食べかすが詰まりにくくなり、ブラッシングで容易に汚れを除去できるようになります。
痛みを伴わない安全な予防処置として注目されています。
フッ素塗布
フッ素には歯の質を強化して唾液の再石灰化作用を助ける働きがあります。また、虫歯菌の活動を抑制する働きもあるため、虫歯予防に効果的な処置です。歯を削る必要がないため小さな子どもでも抵抗なく受けられるでしょう。
フッ素塗布にかかる時間は数分です。フッ素塗布を受ける頻度は、一人ひとりのお口の中の状態によって異なります。
特に、乳歯から永久歯に生え変わる時期は、虫歯になるリスクが高いです。新しく生えてきた歯を守るためにも、定期的にフッ素塗布を受けることが推奨されます。
歯科検診は何歳から?

歯科検診は、乳歯が生え始める生後6か月頃から受けることが可能です。口の中の発達状態を確認しながら、適切な仕上げ磨きの方法などを確認することができるでしょう。
また、乳歯が次々と生えてくる1歳前後から開始する場合もあります。生えたての歯は、歯の質が弱く虫歯になりやすい状態です。
乳歯が生え始めたころから口腔ケアを行う習慣を身につけ、正しい食生活についてのアドバイスを受けることで健康な口内環境を保つことができるでしょう。特に2~3歳は乳臼歯が生え始め、食事も幼児食へと移行する時期になるため、虫歯になりやすく細やかな観察が必要です。
さらに、乳歯から永久歯への生え変わり時期である5〜6歳では、あごの発達状態もチェックする必要があります。子どものうちから歯科医院で定期検診を受けていれば、成長段階に合わせた適切なアドバイスや処置を受けることが可能です。
歯科検診はどのくらいの頻度で受けるの?

歯科検診の通院頻度は、お子さんの年齢やお口の中の状態によって異なります。一般的な目安として、3〜6か月に1回の頻度で検診を受けることをすすめられるケースが多いでしょう。
虫歯を予防するためには、乳歯が生え始める時期からしっかりとケアを行うことが重要です。そのため、虫歯になりやすい場合は、2〜3か月に1回の頻度で検診を受けることが望ましいとされています。
また、永久歯への生え変わりが始まる5〜6歳頃は、特に注意深く観察する必要があります。この時期は、あごの発達状態や永久歯の生え具合をチェックし、必要に応じて予防処置をおこないます。
そのため、3か月に1回の頻度で受診をすすめられる場合もあるでしょう。歯並びや噛み合わせが気になる場合も、短い間隔で検診を受けて経過観察する必要があります。このように、通院頻度はお子さんによって異なるため、歯科医師の指示に従いましょう。
まとめ

子どものうちから歯科検診を受けることは、健康な歯を育むためには必要不可欠だといえます。定期的に歯科検診を受けることで、虫歯や歯並びの問題を早期に発見できるでしょう。
さらに定期検診では、お子さんの成長に合わせた専門的なアドバイスを受けることができます。歯科医院で指導された内容に基づいて、ご家庭でも効果的なケアが実施できるでしょう。
定期検診を通じて子どもが自然と歯の健康に関心を持つようになることも期待できます。お子さまのお口の健康を守るためにも、定期的に歯科検診を受けましょう。
お子さんのお口の健康を守りたいとお考えの保護者の方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。
当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。
投稿者:
ARTICLE
SEARCH
ARCHIVE
CATEGORY
- CAD/CAM冠
- IPR
- MTM
- インビザライン
- インビザライン・エクスプレス
- インビザライン・コンプリヘンシブ
- インビザライン・モデラート
- インビザライン・ライト
- インビザライン矯正
- インプラント治療
- オールセラミック
- カウンセリング
- ジルコニア
- ジルコニアセラミック
- セラミック
- セラミック歯
- セラミック治療
- デメリット
- デンタルローン
- ハイブリッドセラミック
- ブラケット
- ブリッジ
- ホワイトニング
- マウスピース
- マウスピース型
- マウスピース矯正
- メタルタトゥー
- メタルボンド
- メリット
- メンテナンス
- ラミネートベニア
- リスク
- ワイヤー
- ワイヤー矯正
- 予防歯科
- 二酸化ジルコニウム
- 人工ダイヤモンド
- 仮歯
- 保定期間
- 保険適用
- 健康保険
- 入れ歯
- 全体矯正
- 出っ歯
- 前歯
- 医療費控除
- 受け口
- 口腔外科
- 噛み合わせ
- 噛み合わせ治療
- 嚙み合わせ
- 外科治療
- 天然歯
- 失敗
- 奥歯
- 定期検診
- 定期診察
- 審美
- 審美性
- 小児歯科
- 抜歯
- 歯ぎしり
- 歯並び
- 歯列矯正
- 歯周病
- 歯周病菌
- 歯型
- 歯科技工士
- 歯科検診
- 歯科矯正
- 歯茎
- 治療期間
- 症例
- 矯正期間
- 矯正歯科
- 矯正装置
- 精密検査
- 自由診療
- 自費診療
- 虫歯
- 虫歯治療
- 虫歯菌
- 被せ物
- 親知らず
- 詰め物
- 費用
- 通院
- 通院頻度
- 部分入れ歯
- 部分矯正
- 金属
- 金属アレルギー
- 銀歯
- 顎関節症
- 食いしばり